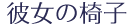










(10)
いつものスナックの電波時計が、キビタキの鳴き声で午前5時を告げた。
整頓の仕事は終わり、店内にある椅子やテーブルは全て気持ちよくきちんと並んでいる。けれども客が一人でも入れば、いや、従業員がひとりでも出勤してくれば、たちまちその位置を動かされてしまうだろう。ぼくが精一杯きれいに並べたこの状態を、誰も特に気に止めたりしない。毎日、整えては崩され整えては崩されの繰り返しだ。
本当は、もっと適当な整頓だっていいんだろう。つまり、ぼくじゃなくたっていい。そう思ったとたん、鈴村の「ずっと真夜中の整頓係でいいの?」という言葉を思い出した。
なんだよ、オマエだって昔はあんなに楽しそうに並べてたじゃないかよ。この仕事に就いた時には、天職を見つけたね、よかったねって言ってくれてたじゃないかよ。……なんて、面と向かっては言えるわけもないことを毒づいてみても空しいだけだ。
「……さん、香坂さん?」
声にはっとして振り返ると、ぼくより早く仕事を終え、ピカピカに磨かれたピアノのそばにうずくまて居眠りをしていたはずのマキちゃんが、いつの間にか目をさまして伸びをしていた。
「どうしたんですかぁ? 朝からたそがれちゃって」
「ぼくのことより、マキちゃん、おへそが丸見えだよ」
「モーニングサービスですからどうぞご鑑賞ください」
マキちゃんはそのままラジオ体操の真似事をしてみせた。なんだか気を遣われている気がする。
「そうだ、今日が最終日でしたよね? 牧野さんの展示会。香坂さん、写真撮るんですよね。一緒に行っていいですか? いいですよね?」
「授業、あるんじゃないの?」
「いいのいいの。一緒に行ってあげるから遠慮しないで」
そんなこと言って、本当は牧野に会いたいんじゃないの? と言おうと思ってやめた。マキちゃんにまで牧野のことで妬いているみたいでみっともないったらない。
後片付けをしてすぐに解散し、マキちゃんとはメッツォで待ち合わせた。
「おや、ふたりお揃いでデートかい? 社内恋愛結構結構」と、居合わせた姐さんに大声で言われて赤くなったのはぼくだけ。
「残念ながら仕事に行くんですよ、香坂さんは。ほら、牧野さんの椅子の写真を撮りに」
「ああ、整然として饒舌なあれだね」
「え? なんですか? それ。平然として情熱? あは、香坂さんそのものですね!」
と、分かってないのかとぼけているのか、マキちゃんが混ぜっ返す。
「整然として饒舌で、平然として情熱か。はははぁ……よく言ったもんだねぇ!」
どうでもいいけど、ふたりとも声がでかい。
初めてこの豪快な姐さんに会ったのは、ぼくがまだ、小さな業界誌の編集部でカメラマンをしていた時だ。取材の対象は姐さんで、場所はこのメッツォだった。
店内で写真を撮ることになってファインダーを覗いたぼくは、カウンターの高いスツールに寄りかかるように腰掛けた姐さんの周りにある椅子やテーブルの位置が気になってしまい、カメラを置くとそれらを並べ直して回った。同行していた同僚は「またか」という呆れた顔をしてぼくの袖を掴むと、「おい、いい加減にしとけよ」と小声で注意した。
ぼくは元のポジションに戻ってカメラを構えた。ところが新たな客がテーブルに着き、構図の端に映る椅子の位置がわずかにゆがんだ。
ぼくはまた、それを直しに行った。同僚はわざとらしいため息をつき、お待たせしてすみませんと姐さんに謝る。
何度それを繰り返したのか、ぼくには分からない。最後は姐さんが自分の近くの椅子を足先でついと乱暴に押しやって言ったのだ。
「あんた、そんなカメラマンなんか辞めて、あたしんところで働きなさいよ」と。
そうしてカメラと整頓の位置関係が逆転し、ぼくはずっと、整頓屋を仕事として続けてきた。
姐さんという母親の作った真夜中の暗い蚕の中で、ぼくは椅子を並べて賃金を得ているのだ。時々、趣味として写真を撮らせてもらいながら。そう、写真を……。
「おい、香坂、聞いてるのかい? こう見えてもあたしはあんたの撮る写真が好きなんだよ。整然でも平然でもなんでもいいから、いい写真を撮っておいで。そんで、写真集が出来たら必ず持ってくるんだよ、あたしが一番に買うんだから」
姐さんはいつかの約束を繰り返して、文字通りぼくの尻を叩いた。
そうだ、写真を撮るんだ。
それがたぶん、ぼくと関わる人すべてから望まれていることであり、誰よりぼくが望むことでもあり、そして、牧野と対峙できるただひとつの方法なんだろう。
つづく
整頓の仕事は終わり、店内にある椅子やテーブルは全て気持ちよくきちんと並んでいる。けれども客が一人でも入れば、いや、従業員がひとりでも出勤してくれば、たちまちその位置を動かされてしまうだろう。ぼくが精一杯きれいに並べたこの状態を、誰も特に気に止めたりしない。毎日、整えては崩され整えては崩されの繰り返しだ。
本当は、もっと適当な整頓だっていいんだろう。つまり、ぼくじゃなくたっていい。そう思ったとたん、鈴村の「ずっと真夜中の整頓係でいいの?」という言葉を思い出した。
なんだよ、オマエだって昔はあんなに楽しそうに並べてたじゃないかよ。この仕事に就いた時には、天職を見つけたね、よかったねって言ってくれてたじゃないかよ。……なんて、面と向かっては言えるわけもないことを毒づいてみても空しいだけだ。
「……さん、香坂さん?」
声にはっとして振り返ると、ぼくより早く仕事を終え、ピカピカに磨かれたピアノのそばにうずくまて居眠りをしていたはずのマキちゃんが、いつの間にか目をさまして伸びをしていた。
「どうしたんですかぁ? 朝からたそがれちゃって」
「ぼくのことより、マキちゃん、おへそが丸見えだよ」
「モーニングサービスですからどうぞご鑑賞ください」
マキちゃんはそのままラジオ体操の真似事をしてみせた。なんだか気を遣われている気がする。
「そうだ、今日が最終日でしたよね? 牧野さんの展示会。香坂さん、写真撮るんですよね。一緒に行っていいですか? いいですよね?」
「授業、あるんじゃないの?」
「いいのいいの。一緒に行ってあげるから遠慮しないで」
そんなこと言って、本当は牧野に会いたいんじゃないの? と言おうと思ってやめた。マキちゃんにまで牧野のことで妬いているみたいでみっともないったらない。
後片付けをしてすぐに解散し、マキちゃんとはメッツォで待ち合わせた。
「おや、ふたりお揃いでデートかい? 社内恋愛結構結構」と、居合わせた姐さんに大声で言われて赤くなったのはぼくだけ。
「残念ながら仕事に行くんですよ、香坂さんは。ほら、牧野さんの椅子の写真を撮りに」
「ああ、整然として饒舌なあれだね」
「え? なんですか? それ。平然として情熱? あは、香坂さんそのものですね!」
と、分かってないのかとぼけているのか、マキちゃんが混ぜっ返す。
「整然として饒舌で、平然として情熱か。はははぁ……よく言ったもんだねぇ!」
どうでもいいけど、ふたりとも声がでかい。
初めてこの豪快な姐さんに会ったのは、ぼくがまだ、小さな業界誌の編集部でカメラマンをしていた時だ。取材の対象は姐さんで、場所はこのメッツォだった。
店内で写真を撮ることになってファインダーを覗いたぼくは、カウンターの高いスツールに寄りかかるように腰掛けた姐さんの周りにある椅子やテーブルの位置が気になってしまい、カメラを置くとそれらを並べ直して回った。同行していた同僚は「またか」という呆れた顔をしてぼくの袖を掴むと、「おい、いい加減にしとけよ」と小声で注意した。
ぼくは元のポジションに戻ってカメラを構えた。ところが新たな客がテーブルに着き、構図の端に映る椅子の位置がわずかにゆがんだ。
ぼくはまた、それを直しに行った。同僚はわざとらしいため息をつき、お待たせしてすみませんと姐さんに謝る。
何度それを繰り返したのか、ぼくには分からない。最後は姐さんが自分の近くの椅子を足先でついと乱暴に押しやって言ったのだ。
「あんた、そんなカメラマンなんか辞めて、あたしんところで働きなさいよ」と。
そうしてカメラと整頓の位置関係が逆転し、ぼくはずっと、整頓屋を仕事として続けてきた。
姐さんという母親の作った真夜中の暗い蚕の中で、ぼくは椅子を並べて賃金を得ているのだ。時々、趣味として写真を撮らせてもらいながら。そう、写真を……。
「おい、香坂、聞いてるのかい? こう見えてもあたしはあんたの撮る写真が好きなんだよ。整然でも平然でもなんでもいいから、いい写真を撮っておいで。そんで、写真集が出来たら必ず持ってくるんだよ、あたしが一番に買うんだから」
姐さんはいつかの約束を繰り返して、文字通りぼくの尻を叩いた。
そうだ、写真を撮るんだ。
それがたぶん、ぼくと関わる人すべてから望まれていることであり、誰よりぼくが望むことでもあり、そして、牧野と対峙できるただひとつの方法なんだろう。
つづく
Copyright(c) sakurai All rights reserved.