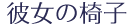











(11)
展示会を祝う花かごがいくつか、控えめに入り口の付近を飾っている。立ち止まったぼくの脇をすり抜けるようにしてマキちゃんがドアを開けると、
「やっと来てくれましたね」と微笑む牧野の横で、
「遅いよ、香坂君」と、鈴村がぼくを出迎えた。おそらくずっと受付を手伝っていたのだろう。見たこともない、かっちりとしたスーツを着ている。
仲良く並んで立っている牧野と鈴村。
驚くほど意外でもなかったし、嫉妬するほどショックでもなかった。
あとは片づけるばかりの会場にはもう、ぼくら4人の他には人が居ない。例によってマキちゃんは、「香坂さんの彼女さんですね、はじめまして!」と勝手に自己紹介をしたかと思うと、ぱらぱらと芳名帳をめくり、「わぁ、たくさん来てるぅ!」とひとりではしゃいでいる。その声がぴゅんと部屋中に響いて、ぼくの口はやっと「おめでとう」という言葉を思い出した。牧野という男がひとまわり大きくなったように思えて、「おめでとう」とだけ軽く言うつもりが「おめでとうございます」と深く頭を下げていた。なんだか、何をどう考えたらいいのか、ぼうっとしてしまう。
「香坂さん、今すぐ仕事にかかりますか? ぼくら、居た方がいいですか、居ない方がいいですか?」
「え?」
ぼくらというのが、牧野と鈴村を差すのか、牧野とマキちゃんを差すのか分からずに戸惑っていると、
「居てもらってもいいよね、香坂君」と、鈴村がぼくの腕を取り、「早くやろうよ、あれ! だって、写真撮るんでしょ?」と、引っ張る。肩からずり落ちそうになったカメラのバッグを、牧野がすくい上げて床に下ろしてくれた。急に身軽になったぼくは鈴村と一緒に椅子たちの前に立つ。
その途端、そこは何年も前の高校の教室だった。誰も居なくなった放課後。鈴村とふたりきり……まだぼくはぼぅっとしている。
「ねぇ、わたし、ずっと言おうと思っていたことがある」
まず最初に教会の椅子を持ち上げ、入り口に向けてまっすぐに置きながら鈴村が言った。
「なに?」
「本当はたくさんある。でも、根っこはひとつなんだと思う」
「根っこ?」
ぼくは残りのたくさんの椅子の中から、肘掛けの曲線が急な一脚を選んで教会の椅子の後ろに並べた。
「たとえば、そう……映画のこととかね……」
鈴村は今度はディレクターズチェアーのような背もたれの椅子を選び出した。教会の椅子の後ろに置き、慎重に位置を整える。
「一緒に観たかった映画があったよね。でも、わたしひとりで観に行ったんだよ」
そんなことは何度もあったように思う。何しろずっと生活時間がすれ違っているのだから、最後に一緒に映画を観たのがいつだったかも覚えていない。
それよりもなぜ、映画のことなんか彼女は言うのか……。言わなかったことって、牧野のことじゃないのか。
「その映画がとても良かったから、香坂君にも観て貰いたかった。だから、DVDが出たときに買って持っていった。一緒に観たかった。でもやっぱり、時間がなかった」
ああ……と、ぼくはぼんやりと思い出しながら、次の椅子を選んで運んだ。そのDVDならぼくの部屋の本棚にある。まだ、封も切られないまま。タイトルも、ごめん、忘れている。
いつだって観られると、そう思っていたからだ。
時間があれば、ぼく自身が観たいと思う映画の方を先に観た。鈴村がいいというものはいいのだろうけれど、もうそれで充分に思えてしまうのだ。
「整頓クラブ、楽しかったよね。ただ香坂君と同じことをするのが嬉しかった。こうやって並べながらいろんなこと話したんだよね」
まるで牧野に聞かせる為みたいに鈴村は話す。牧野は壁により掛かり、マキちゃんは受付の椅子に座って見ているようだ。だからというわけじゃないけれど、ぼくは丁寧にゆっくりと、牧野の椅子を運ぶ。
そう、整頓クラブ。あの頃はなんでも同じものを追いかけた。同じものを観て同じものを読んで同じものを聴いて、感じたことを話し合うのに夢中だった。互いの感性に少しでも早くたくさん触れたくて、追いかけっこをしているようだった。
ゆっくりと、後回しにできるようになったのはいつからだろう。
どんなことも、なんとなく分かり合えるのが当たり前になった。気になっても訊かなかったり、話さないことがあるのも、そのうちに分かるだろう伝わるだろう、そんな機会が必ず来るだろうと思うからだ。
それが鈴村にとっては物足りなさの根っこなんだろうか。そりゃあ、確かにあの頃は楽しかった。でも、「あの頃」がよかったとばかり言われるのはかなわないとぼくは思う。あの頃はあの頃だ。今とは違って当たり前じゃないか。
それとも、「あの頃」をいつまでも大事にしている牧野をサポートしていくことの方が、ずっと生き甲斐があると言いたいのか……?
それにしてはなんだか楽しそうだ。「話したかったこと」なんかもう、どうでもいいみたいに夢中で椅子を並べている。自分で言いだしてひとりで納得して……。そうやって言わずに飲み込んだ言葉を、彼女はどこに隠しているんだろう。
高校の、放課後の教室で、初めてぼくの変な趣味を理解してくれたクラスメイト。ぼくに自信をくれて、励まし続けてくれた鈴村。それなのに最近のぼくは、彼女がたまに口にする助言さえ、少し煩く思うようになっていた。「彼女の好きなぼく」であることに、なんていうか、怠惰になっていたんだろう。牧野が現れなければ、それに気づくこともなかったかもしれない。
「ごめん……」
「え? なにが?」
「いろいろ」
ぼくが小さすぎたと思う。でもそれは、牧野に聞こえる場所では言いたくなかった。
「やだな、香坂君はなんにも悪くないよ」
笑顔で鈴村は言う。でも、そんなことないだろう。ないだろうけれど、ここで言い合いたくもなかったから、あとは黙って作業を続けた。
つづく
「やっと来てくれましたね」と微笑む牧野の横で、
「遅いよ、香坂君」と、鈴村がぼくを出迎えた。おそらくずっと受付を手伝っていたのだろう。見たこともない、かっちりとしたスーツを着ている。
仲良く並んで立っている牧野と鈴村。
驚くほど意外でもなかったし、嫉妬するほどショックでもなかった。
あとは片づけるばかりの会場にはもう、ぼくら4人の他には人が居ない。例によってマキちゃんは、「香坂さんの彼女さんですね、はじめまして!」と勝手に自己紹介をしたかと思うと、ぱらぱらと芳名帳をめくり、「わぁ、たくさん来てるぅ!」とひとりではしゃいでいる。その声がぴゅんと部屋中に響いて、ぼくの口はやっと「おめでとう」という言葉を思い出した。牧野という男がひとまわり大きくなったように思えて、「おめでとう」とだけ軽く言うつもりが「おめでとうございます」と深く頭を下げていた。なんだか、何をどう考えたらいいのか、ぼうっとしてしまう。
「香坂さん、今すぐ仕事にかかりますか? ぼくら、居た方がいいですか、居ない方がいいですか?」
「え?」
ぼくらというのが、牧野と鈴村を差すのか、牧野とマキちゃんを差すのか分からずに戸惑っていると、
「居てもらってもいいよね、香坂君」と、鈴村がぼくの腕を取り、「早くやろうよ、あれ! だって、写真撮るんでしょ?」と、引っ張る。肩からずり落ちそうになったカメラのバッグを、牧野がすくい上げて床に下ろしてくれた。急に身軽になったぼくは鈴村と一緒に椅子たちの前に立つ。
その途端、そこは何年も前の高校の教室だった。誰も居なくなった放課後。鈴村とふたりきり……まだぼくはぼぅっとしている。
「ねぇ、わたし、ずっと言おうと思っていたことがある」
まず最初に教会の椅子を持ち上げ、入り口に向けてまっすぐに置きながら鈴村が言った。
「なに?」
「本当はたくさんある。でも、根っこはひとつなんだと思う」
「根っこ?」
ぼくは残りのたくさんの椅子の中から、肘掛けの曲線が急な一脚を選んで教会の椅子の後ろに並べた。
「たとえば、そう……映画のこととかね……」
鈴村は今度はディレクターズチェアーのような背もたれの椅子を選び出した。教会の椅子の後ろに置き、慎重に位置を整える。
「一緒に観たかった映画があったよね。でも、わたしひとりで観に行ったんだよ」
そんなことは何度もあったように思う。何しろずっと生活時間がすれ違っているのだから、最後に一緒に映画を観たのがいつだったかも覚えていない。
それよりもなぜ、映画のことなんか彼女は言うのか……。言わなかったことって、牧野のことじゃないのか。
「その映画がとても良かったから、香坂君にも観て貰いたかった。だから、DVDが出たときに買って持っていった。一緒に観たかった。でもやっぱり、時間がなかった」
ああ……と、ぼくはぼんやりと思い出しながら、次の椅子を選んで運んだ。そのDVDならぼくの部屋の本棚にある。まだ、封も切られないまま。タイトルも、ごめん、忘れている。
いつだって観られると、そう思っていたからだ。
時間があれば、ぼく自身が観たいと思う映画の方を先に観た。鈴村がいいというものはいいのだろうけれど、もうそれで充分に思えてしまうのだ。
「整頓クラブ、楽しかったよね。ただ香坂君と同じことをするのが嬉しかった。こうやって並べながらいろんなこと話したんだよね」
まるで牧野に聞かせる為みたいに鈴村は話す。牧野は壁により掛かり、マキちゃんは受付の椅子に座って見ているようだ。だからというわけじゃないけれど、ぼくは丁寧にゆっくりと、牧野の椅子を運ぶ。
そう、整頓クラブ。あの頃はなんでも同じものを追いかけた。同じものを観て同じものを読んで同じものを聴いて、感じたことを話し合うのに夢中だった。互いの感性に少しでも早くたくさん触れたくて、追いかけっこをしているようだった。
ゆっくりと、後回しにできるようになったのはいつからだろう。
どんなことも、なんとなく分かり合えるのが当たり前になった。気になっても訊かなかったり、話さないことがあるのも、そのうちに分かるだろう伝わるだろう、そんな機会が必ず来るだろうと思うからだ。
それが鈴村にとっては物足りなさの根っこなんだろうか。そりゃあ、確かにあの頃は楽しかった。でも、「あの頃」がよかったとばかり言われるのはかなわないとぼくは思う。あの頃はあの頃だ。今とは違って当たり前じゃないか。
それとも、「あの頃」をいつまでも大事にしている牧野をサポートしていくことの方が、ずっと生き甲斐があると言いたいのか……?
それにしてはなんだか楽しそうだ。「話したかったこと」なんかもう、どうでもいいみたいに夢中で椅子を並べている。自分で言いだしてひとりで納得して……。そうやって言わずに飲み込んだ言葉を、彼女はどこに隠しているんだろう。
高校の、放課後の教室で、初めてぼくの変な趣味を理解してくれたクラスメイト。ぼくに自信をくれて、励まし続けてくれた鈴村。それなのに最近のぼくは、彼女がたまに口にする助言さえ、少し煩く思うようになっていた。「彼女の好きなぼく」であることに、なんていうか、怠惰になっていたんだろう。牧野が現れなければ、それに気づくこともなかったかもしれない。
「ごめん……」
「え? なにが?」
「いろいろ」
ぼくが小さすぎたと思う。でもそれは、牧野に聞こえる場所では言いたくなかった。
「やだな、香坂君はなんにも悪くないよ」
笑顔で鈴村は言う。でも、そんなことないだろう。ないだろうけれど、ここで言い合いたくもなかったから、あとは黙って作業を続けた。
つづく
Copyright(c) sakurai All rights reserved.