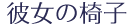












(12)
三列に並んだ椅子を正面から眺めるぼくの隣りに、鈴村も来て並んだ。
「まっすぐだよね」
と、確かめるように彼女が言う。 「うん」
形も大きさも違うそれぞれの個性を主張しながら、椅子たちは整然と並んでいた。
展示会のためにレイアウトしたときには感じられなかった興奮を、ぼくは感じていた。もっと牧野の椅子がたくさんあって、もっと広い場所があったらと、想像するとさらにわくわくする。目に浮かんでくる。
「やっぱりすごいな、香坂君」
「鈴村が手伝ってくれたからだよ」
「ほんとほんと?」
「うん」
「よかった。まだ香坂君の役に立つんだね、わたし」
「なんだよそれ」
当たり前じゃないか。それどころか、こんなこと「すごい」と言ってくれるのは鈴村だけだろう。
「座ってみて」
「え?」
「一番後ろの、左はしの椅子」
と、ぼくは鈴村を促した。
「撮るの?」
鈴村は驚いていた。
「香坂君がわたしを撮るって、はじめてだよ? 知ってる?」
何も言わないうちにマキちゃんが近づいてきて、カメラを手渡してくれた。
レンズを通して見る鈴村は高校の頃そのままにぼくには見えた。彼女が変わっていないのではなく、たぶんぼくの見方が変わっていないからなのだろう。
今まで一度も彼女を撮らなかったのは、その時その時の彼女を切り取ってしまいたくなかったからだった。この写真の時、この写真の時……と、なにかの区切りができてしまうのが怖くて、ぼくは彼女を撮らなかった。
その気持ちはやっぱり今も変わらない。
ぼくはシャッターを切ったふりだけをして、今度は牧野を鈴村の反対の端に座らせた。
仲のいい姉弟にも、若い夫婦にも、恋人同士にも友だち同士にも、なんにでも見える、椅子一つ置いて並んだふたりを、ぼくはレンズに収めて、そして、その時間を切り取った。
カシャッ
それからはもう、ひとりの世界だった。
整然と並べた椅子たちを、ぼくはあらゆる角度から撮った。並べ直しては、また撮った。
牧野やマキちゃんのことはすっかり忘れていた。もしかしたら、その場にはいなかったのかもしれない。ともかくぼくはただ、自分の世界にいて、ただ鈴村が部屋の正面に立ち、そう、ちょうど教室の教壇の上に立っているみたいにして、見ているのを感じていた。
どれだけ時間が経ったのだろう。
何本めかのフイルムが終わって、ぼくはカメラを下ろした。
撮った。
そう思えた。ぼくは十分に撮れたと。自信、のようなものに満たされて、ぼくの胸は食パン3枚分くらいは膨らんでいた。
マキちゃんがいつになく神妙な顔でぼくの手からカメラを受け取ると、そばのテーブルにそっと置いてくれた。
左腕には鈴村を感じた。
そうして、彼女のその細い指先がゆっくりとぼくの肘の内側を通って手の平に届くころ、牧野が目の前にやってきて、右手を差し出した。
その手の意味が理解できないくらい、一瞬ぼくは混乱して、鈴村の触れている左手を牧野の前に出そうとする。それを鈴村がぐっと押さえたから、ぼくは初めて鈴村の方を見た。
鈴村がぼくを見ている。微笑んでいる。いつもならすいと目をそらしてしまっただろう。でもぼくは彼女の目を久しぶりにじっと見た。
長い間口にはしなかったけれど、確かにずっとそこにあったものを改めて確認しあえた。そんな気がしていた。
「もういいですか?」
「え?」
「いつまでもふたりで見つめ合ってないで、握手してくださいよ、香坂さん」
「あぁ、そうか、ごめんごめん」
ぼくは牧野に右手を差し出した。
「香坂さん、ありがとうございます。本当に」
牧野はそういって両手でぼくの右手を取った。
「こちらこそ……」
「ね、そうですよね。いろいろと感謝してくださいよ、香坂さんも」
そう言って牧野は笑った。ちっとも押しつけがましさのない屈託のない笑顔は、鈴村と出会った小学生の頃のままなんじゃないかと思えてくる。
「ミツくん、またどんどんいい椅子を作ってね」
「ありがとう、ハナちゃん。そうしたらまた、香坂さんに撮ってもらうよ」
「ぼくも楽しみにしています。その時は鈴村、また一緒に椅子を並べよう」
「もちろん!」
「あーあ、そうやってわたしばっかりのけ者にしてないで、みんなで打ち上げ行きましょうよ、ね! 行きましょう行きましょう!」
そう言ってマキちゃんは、握手したままだった牧野の手をぼくから引き離すようにして引っ張った。
ぼくの左手はまだしっかりと、鈴村の指を捕らえていた。
つづく
Copyright(c) sakurai All rights reserved.