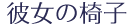


(2)
ぼくの仕事は整頓屋だ。
『用具箱』と呼ばれる小さな事務所には、スチールの机がひとつと大きいだけが取り柄の古びた黒いソファーが奥にあり、窓のない壁一面にはバケツにモップ、棚には様々な洗剤が並んで、大量の雑巾が吊るされたロープは運動会の万国旗のようにたわんでいる。
でもそれらのほとんどは『掃除屋』の道具で、ぼくら『整頓屋』は独自の道具を使っていた。もっとも、ぼく自身に関して言えば、なんの用意もいらないのだけれど。
「香坂、あんたメッツォのテーブルレイアウトを変えちまったんだって?」
その日ぼくが事務所の扉を開けると、掃除用具の奥から首を伸ばすようにこっちを見た「姐さん」が、だみ声を飛ばして来た。
白髪の目立つ髪をこれでもかと絞り上げるようにひとつに結んだ姐さんは、『用具箱』の主、つまりぼくの雇い主。メッツォというのは、その姐さん所有のビルの中にある喫茶店の名前であり、ぼくの仕事場のひとつだ。
「すみませんでした」
とりあえず姐さんの前までいって素直に頭を下げた。
ぼくの仕事は「整頓」することであって、レイアウトすることじゃない。メッツォのテーブルが、いかにいい加減に並んでいて毎回どんなに気に障っても、勝手に並べ方を変えるのが良くないことはわかっていた。分かっていてやった。
「今後は、余計なことするんじゃないよ」
そう言われるのは当然だ。でも、……と言いわけしたくなる口を閉じて奥歯をきりりと噛む。
ところが姐さんは急にカラカラと笑い出し、
「マスターが喜んじゃってたよ。あんたの出しゃばりのせいで客の回転がよくなったんだってさ」
そう言いながら煙草臭い指でぼくの鼻をつまんで軽く捻る真似をする。
「まぁ、あたしのビルん中のレイアウトなら全部、香坂に任せたいくらいなんだけどさ。そうもいかない」
あぁ、もしそれができるのだとしたら、どんなに楽しいだろう。
子どもの頃からぼくは、椅子がきちんと並んだ状態が好きだった。
小学校の入学式の日に、広い体育館にたくさんの椅子が整然と並んでいるのを見てぞくぞくしたことを覚えている。
中学高校の頃には、西日の射し込む放課後の教室に残り、一日の努めを終えた机や椅子を並べ直すのが、ぼくの密かな楽しみだった。
まず、床の板目に合わせて窓際の机を一列に並べ、それから慎重に前列を揃える。
縦方向の板目しかない床だと、横の列を揃えるのはなかなか難しかった。さらにやっかいなのは、使い古されて微妙に歪んだ椅子たちだった。いくら机がまっすぐでも、椅子の背は、ただ単純に机に押し込んだだけではまっすぐに並ばない。それぞれ、机との微妙な距離を必要とした。
そうしてやっと出来上がった整然とした状態を、ぼくは教壇の上や教室の後ろから、時間の許す限り眺めた。時には写真に撮った。それは、女の子のふくらはぎや胸を盗み見るよりも、ずっと貴重な時間だったのだ。
そんな高校二年のある放課後のことだった。
いつものように図書室で時間をつぶしてから教室に戻って来ると、誰もいなくなっているはずのその場所に、女生徒がひとりだけ残っていた。舌打ちしたいような気持ちできびすを返そうとすると、その子はぼくに気づいて席から立ち上がり、
「遅かったじゃない」と、笑いかけてきた。
それが鈴村華子だった。
鈴村は転校してきたばかりで、背がすらりと高く、かわいいと言うより美人と呼ぶ方が似合う顔立ちのせいもあり、学年の男子どころか、学校中の男子に注目されていた存在だった。当然ぼくに手の届く相手ではないし、同じクラスでもまだ、言葉を交わしたこともなかった。なのに鈴村は、まるでずっと以前からの友だちのように、「ねぇねぇ、見て」と言ってぼくの手を引き、「わたしもなかなか上手でしょ?」と、いたずらっぽく笑った。
ぼくは鈴村に促されるままに教壇に上り、教室を見回した。
驚いたことに、椅子も机もかなりいい線にまっすぐ揃えられていた。
それでもぼくは教壇から降りると、いくつかの机の位置を微妙に直してみせた。ぼくが来るまで鈴村が座っていた椅子も、もう一度まっすぐに揃えてやった。
今度は鈴村が教壇に上がって見渡す番だった。
「すごい! やっぱり香坂君はすごいよ」
鈴村は感嘆の声をあげ、 「きちんとしてるのって気持ちいいよね!」と、きっちりとぼくに向かって微笑んだのだった。
つづく
『用具箱』と呼ばれる小さな事務所には、スチールの机がひとつと大きいだけが取り柄の古びた黒いソファーが奥にあり、窓のない壁一面にはバケツにモップ、棚には様々な洗剤が並んで、大量の雑巾が吊るされたロープは運動会の万国旗のようにたわんでいる。
でもそれらのほとんどは『掃除屋』の道具で、ぼくら『整頓屋』は独自の道具を使っていた。もっとも、ぼく自身に関して言えば、なんの用意もいらないのだけれど。
「香坂、あんたメッツォのテーブルレイアウトを変えちまったんだって?」
その日ぼくが事務所の扉を開けると、掃除用具の奥から首を伸ばすようにこっちを見た「姐さん」が、だみ声を飛ばして来た。
白髪の目立つ髪をこれでもかと絞り上げるようにひとつに結んだ姐さんは、『用具箱』の主、つまりぼくの雇い主。メッツォというのは、その姐さん所有のビルの中にある喫茶店の名前であり、ぼくの仕事場のひとつだ。
「すみませんでした」
とりあえず姐さんの前までいって素直に頭を下げた。
ぼくの仕事は「整頓」することであって、レイアウトすることじゃない。メッツォのテーブルが、いかにいい加減に並んでいて毎回どんなに気に障っても、勝手に並べ方を変えるのが良くないことはわかっていた。分かっていてやった。
「今後は、余計なことするんじゃないよ」
そう言われるのは当然だ。でも、……と言いわけしたくなる口を閉じて奥歯をきりりと噛む。
ところが姐さんは急にカラカラと笑い出し、
「マスターが喜んじゃってたよ。あんたの出しゃばりのせいで客の回転がよくなったんだってさ」
そう言いながら煙草臭い指でぼくの鼻をつまんで軽く捻る真似をする。
「まぁ、あたしのビルん中のレイアウトなら全部、香坂に任せたいくらいなんだけどさ。そうもいかない」
あぁ、もしそれができるのだとしたら、どんなに楽しいだろう。
子どもの頃からぼくは、椅子がきちんと並んだ状態が好きだった。
小学校の入学式の日に、広い体育館にたくさんの椅子が整然と並んでいるのを見てぞくぞくしたことを覚えている。
中学高校の頃には、西日の射し込む放課後の教室に残り、一日の努めを終えた机や椅子を並べ直すのが、ぼくの密かな楽しみだった。
まず、床の板目に合わせて窓際の机を一列に並べ、それから慎重に前列を揃える。
縦方向の板目しかない床だと、横の列を揃えるのはなかなか難しかった。さらにやっかいなのは、使い古されて微妙に歪んだ椅子たちだった。いくら机がまっすぐでも、椅子の背は、ただ単純に机に押し込んだだけではまっすぐに並ばない。それぞれ、机との微妙な距離を必要とした。
そうしてやっと出来上がった整然とした状態を、ぼくは教壇の上や教室の後ろから、時間の許す限り眺めた。時には写真に撮った。それは、女の子のふくらはぎや胸を盗み見るよりも、ずっと貴重な時間だったのだ。
そんな高校二年のある放課後のことだった。
いつものように図書室で時間をつぶしてから教室に戻って来ると、誰もいなくなっているはずのその場所に、女生徒がひとりだけ残っていた。舌打ちしたいような気持ちできびすを返そうとすると、その子はぼくに気づいて席から立ち上がり、
「遅かったじゃない」と、笑いかけてきた。
それが鈴村華子だった。
鈴村は転校してきたばかりで、背がすらりと高く、かわいいと言うより美人と呼ぶ方が似合う顔立ちのせいもあり、学年の男子どころか、学校中の男子に注目されていた存在だった。当然ぼくに手の届く相手ではないし、同じクラスでもまだ、言葉を交わしたこともなかった。なのに鈴村は、まるでずっと以前からの友だちのように、「ねぇねぇ、見て」と言ってぼくの手を引き、「わたしもなかなか上手でしょ?」と、いたずらっぽく笑った。
ぼくは鈴村に促されるままに教壇に上り、教室を見回した。
驚いたことに、椅子も机もかなりいい線にまっすぐ揃えられていた。
それでもぼくは教壇から降りると、いくつかの机の位置を微妙に直してみせた。ぼくが来るまで鈴村が座っていた椅子も、もう一度まっすぐに揃えてやった。
今度は鈴村が教壇に上がって見渡す番だった。
「すごい! やっぱり香坂君はすごいよ」
鈴村は感嘆の声をあげ、 「きちんとしてるのって気持ちいいよね!」と、きっちりとぼくに向かって微笑んだのだった。
つづく
Copyright(c) sakurai All rights reserved.