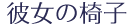



(3)
その日から、ぼくが放課後の教室で椅子を並べていると、鈴村も顔を出すようになった。
彼女はぼくらの放課後を「整頓クラブ」と名付け、自分たちの教室だけでは飽き足らず、ぼくを引っ張るようにして隣の教室へ、また隣の教室へと、活動の場所を広げていった。
ぼくらは一緒に机や椅子を揃えながら、色々な話をした。他愛のないおしゃべりの中で得た情報のひとつひとつをきちんと並べるうちに、少しずつぼくの中に鈴村像が出来上がっていくようだった。
話してみれば鈴村は、外見に似合わず平凡な、むしろ地味な女の子だった。もちろん、そうでなければぼくなどには関わっていなかったのかもしれない。外見が華やかな彼女は、放課後の誘いなら引きも切らなかったし、美術部に所属したとたん、モデルにしたいと顧問にしつこく迫られていることも噂になっていたくらいだ。
けれども、鈴村が誰かの誘いに頷いているところをぼくは見たことがない。まるで全身で「わたしを誘わないで!」と主張しているようにさえ見えていた。
「わたしね、転校してきてからずっと、毎朝一番に登校して、一番に教室に入っていたのよ」
どうして? とぼくが言おうとすると、
「どうしてって訊かないでね」と、急いで鈴村が言った。
整頓の終わった教室の、窓際にある棚の上に腰をかけて、彼女は少し見下ろすような形でぼくを見ていた。「訊かないでね」なんて、ぼくはそれこそ、「どうして?」って笑いたかったけれど……。
「わたしね、どうして? って聞かれると、なんだか責められているような気がしてしまうのよ。わたしの言うことやしていることは、人には理解しがたいことなのかなって」
それなら、ぼくのしていることこそ他人には理解しがたいことだろう。今さら誰も、理由なんか訊いてくれないくらいだ。
いったい「どうして?」の何がいけないんだろう。
「理由があるときはわたしから話すから。だから、先回りして“どうして?”って訊かないでおいて欲しいの。そうしてね、香坂君」
「いいけど……」
じゃあ、朝一番に登校してたのはどうして? と、話の先を促すこともできなくて、ぼくはしばらく黙って彼女の話を待つことになった。
「毎朝一番に登校していたのは、みんなが昇降口にいるところに居合わせると、いろいろ話しかけられたり言われたりして、なんだか面倒だったからなんだけどね……」
そんな贅沢な悩み、ぼくは一生経験しそうにもないぞ。
「朝一番に来るようになってすぐに気がついたのよ。うちの教室だけいつもきちっと椅子や机が並んでること。それでわたし、学校に来る楽しみができた。どうしてこんなにきちんと出来るんだろうって、不思議だったなぁ。少しでも乱しちゃうのがもったいなくて、誰かが来るまでは自分の椅子にも座らないで教室を眺めていたくらいよ。変よね」
鈴村は下を向いておかしそうに笑った。
ぼくは自分の変な趣味を笑われることには慣れていたけれど、鈴村が笑っているのはぼくのことではなく鈴村自身のことなのだ。
それがぼくには嬉しかった。
-----
転校生としての物珍しさが薄れて行くに連れて、付き合いも悪く、なかなか回りに馴染まない鈴村は、「美人だけどなんか変な人」として少しずつ孤立して行った。もっともそれは彼女の望むところだったのかもしれない。悪意からか「問題を起こして転校して来たらしい」「美術部の顧問を振ったらしい」などと噂も流れたけれど、彼女はたいして気にする様子もなかった。
「香坂君がいるから大丈夫だもん」
そんな風に言ってふざけて胸を張ってみせた。ぼくだけが鈴村をよく知っている。クラスの誰よりも知っているんだと、ぼくは得意になっていた。だから、
「ねぇ、前の学校に恋人がいるって噂は本当?」
と訊いてみたのは、今度もいい加減な噂であって、そんな相手なんかいないだろうという自惚れからだったかもしれない。けれども、
「うん、いる。あ、でも、恋人は変かな。心の支えっていうか、親友っていうか……そういう人ならいるよ」
あまりにもあっさりと返されて、ぼくは並べていた椅子を倒しかけてしまった。
「ど、どうして?」と口にしかけて、「どういう人?」と、ぼくは言い直した。
「うーん……。話していると楽しくてね、一緒にいるとすごく落ち着くんだ……。といっても、前の学校の人じゃないし、あんまり会えないんだけどね、遠いから」
「そうなんだ……」
「わたしね、中学の時いろいろあって……。
ね、いろいろって何か、訊きたい?」
「いや……」
もはや、知りたいのは相手の男のことだけだった。
「ざっと話しちゃうとね、わたし、誤解とかいじめとかいろいろあって、中2の夏休み前からずっと、長野へ逃げてたんだ。母と一緒に。その長野でミツくんていう3つ年下の男の子と知り合ったの。そのミツくんがわたしの大事な人だよ」
なんだよ、3つ下っていったら、そのときは小学生だろ? 今は中学生か?
ぼくは鈴村にからかわれているのかと思った。
恋人がいると噂に聞いたとき、ぼくが想像したのは(おそらくクラスの誰もが想像していたのは)、もっと性の匂いのする年上の相手だったのだ。
想像とは大きく違ったけれど、それから鈴村が話してくれた「長野の夏」の話は、少なからずぼくにはショックだった。
町の外れに大きなケヤキの木があって、いつもその木の下でふたりが会っていたこと。太い木の根の上に腰を掛けて、日が暮れるまで話をしたこと、歌ったこと。
ミツくんが相手だとなんでも素直に話せたこと、大きな麦わら帽子をかぶっていても、すっかり日に焼けてしまったこと。ミツくんはもともと真っ黒だったこと……。
「夏の間ずっとミツくんと一緒にいて、わたし、すごく自分の心の中が柔らかくなっていくのがわかったの。学校にちゃんと戻れたのは、ミツくんのおかげだと思ってる」
中学生の頃からすでに大人びていたと思われる鈴村が、小学生だったヤツに慰められるという図は想像しにくかったけれど、その後も中3、高1の夏休みを鈴村は長野で過ごしたし、手紙のやりとりは今でもあるらしい。
「香坂君と初めて話をしたとき、ミツくんを思い出したよ」という言葉には、喜んでいいのか悲しむべきなのかわからなかった。
「香坂君とこうして“整頓クラブ”をしているのは、わたしにとって、あの頃ミツくんと欅の下で話していたのと同じ感覚なんだよね……」
ぼくはそいつの代わりなんだろうか? それならそれでも、かまわないような気がしていた。まだまだこれからだ。今、鈴村のそばにいるのはぼくなのだから。
-----
ぼくらは学校で毎日のように会い、週末も長い休みも一緒に過ごし、時間で言えばそれは確実に「ミツくんとの夏」の長さを越していった。
夏休みになっても、鈴村は長野へは行かなかった。ぼくらは毎日のように図書館で一緒に宿題をし、時にはこっそり、閉館間際の閲覧室の椅子をきれいに並べ直してみたりした。
やがてぼくらは手をつないで歩くようになり、JRの高架下で初めてのキスをした。ほとんど同じだった身長も、いつの間にかぼくの方が鈴村をぐいと追い越していた。
ふたりで語り合える思い出話も増えていた。
高校を卒業後、ぼくは写真の専門学校に進み、そこを出るとカメラを持って職を転々とし、短大を出た鈴村は伯父さんの画廊の手伝いを始めて互いに忙しくなった。
その上、ぼくが「用具箱」の姐さんのところで働くようになってからは夜の仕事ばかりで、とうとうふたりの生活は完璧にすれ違うようになってしまった。
それでもぼくらはいつも互いのそばにいる。
一番近くにいる。
少なくともぼくはずっと、そう信じていた。
つづく
彼女はぼくらの放課後を「整頓クラブ」と名付け、自分たちの教室だけでは飽き足らず、ぼくを引っ張るようにして隣の教室へ、また隣の教室へと、活動の場所を広げていった。
ぼくらは一緒に机や椅子を揃えながら、色々な話をした。他愛のないおしゃべりの中で得た情報のひとつひとつをきちんと並べるうちに、少しずつぼくの中に鈴村像が出来上がっていくようだった。
話してみれば鈴村は、外見に似合わず平凡な、むしろ地味な女の子だった。もちろん、そうでなければぼくなどには関わっていなかったのかもしれない。外見が華やかな彼女は、放課後の誘いなら引きも切らなかったし、美術部に所属したとたん、モデルにしたいと顧問にしつこく迫られていることも噂になっていたくらいだ。
けれども、鈴村が誰かの誘いに頷いているところをぼくは見たことがない。まるで全身で「わたしを誘わないで!」と主張しているようにさえ見えていた。
「わたしね、転校してきてからずっと、毎朝一番に登校して、一番に教室に入っていたのよ」
どうして? とぼくが言おうとすると、
「どうしてって訊かないでね」と、急いで鈴村が言った。
整頓の終わった教室の、窓際にある棚の上に腰をかけて、彼女は少し見下ろすような形でぼくを見ていた。「訊かないでね」なんて、ぼくはそれこそ、「どうして?」って笑いたかったけれど……。
「わたしね、どうして? って聞かれると、なんだか責められているような気がしてしまうのよ。わたしの言うことやしていることは、人には理解しがたいことなのかなって」
それなら、ぼくのしていることこそ他人には理解しがたいことだろう。今さら誰も、理由なんか訊いてくれないくらいだ。
いったい「どうして?」の何がいけないんだろう。
「理由があるときはわたしから話すから。だから、先回りして“どうして?”って訊かないでおいて欲しいの。そうしてね、香坂君」
「いいけど……」
じゃあ、朝一番に登校してたのはどうして? と、話の先を促すこともできなくて、ぼくはしばらく黙って彼女の話を待つことになった。
「毎朝一番に登校していたのは、みんなが昇降口にいるところに居合わせると、いろいろ話しかけられたり言われたりして、なんだか面倒だったからなんだけどね……」
そんな贅沢な悩み、ぼくは一生経験しそうにもないぞ。
「朝一番に来るようになってすぐに気がついたのよ。うちの教室だけいつもきちっと椅子や机が並んでること。それでわたし、学校に来る楽しみができた。どうしてこんなにきちんと出来るんだろうって、不思議だったなぁ。少しでも乱しちゃうのがもったいなくて、誰かが来るまでは自分の椅子にも座らないで教室を眺めていたくらいよ。変よね」
鈴村は下を向いておかしそうに笑った。
ぼくは自分の変な趣味を笑われることには慣れていたけれど、鈴村が笑っているのはぼくのことではなく鈴村自身のことなのだ。
それがぼくには嬉しかった。
-----
転校生としての物珍しさが薄れて行くに連れて、付き合いも悪く、なかなか回りに馴染まない鈴村は、「美人だけどなんか変な人」として少しずつ孤立して行った。もっともそれは彼女の望むところだったのかもしれない。悪意からか「問題を起こして転校して来たらしい」「美術部の顧問を振ったらしい」などと噂も流れたけれど、彼女はたいして気にする様子もなかった。
「香坂君がいるから大丈夫だもん」
そんな風に言ってふざけて胸を張ってみせた。ぼくだけが鈴村をよく知っている。クラスの誰よりも知っているんだと、ぼくは得意になっていた。だから、
「ねぇ、前の学校に恋人がいるって噂は本当?」
と訊いてみたのは、今度もいい加減な噂であって、そんな相手なんかいないだろうという自惚れからだったかもしれない。けれども、
「うん、いる。あ、でも、恋人は変かな。心の支えっていうか、親友っていうか……そういう人ならいるよ」
あまりにもあっさりと返されて、ぼくは並べていた椅子を倒しかけてしまった。
「ど、どうして?」と口にしかけて、「どういう人?」と、ぼくは言い直した。
「うーん……。話していると楽しくてね、一緒にいるとすごく落ち着くんだ……。といっても、前の学校の人じゃないし、あんまり会えないんだけどね、遠いから」
「そうなんだ……」
「わたしね、中学の時いろいろあって……。
ね、いろいろって何か、訊きたい?」
「いや……」
もはや、知りたいのは相手の男のことだけだった。
「ざっと話しちゃうとね、わたし、誤解とかいじめとかいろいろあって、中2の夏休み前からずっと、長野へ逃げてたんだ。母と一緒に。その長野でミツくんていう3つ年下の男の子と知り合ったの。そのミツくんがわたしの大事な人だよ」
なんだよ、3つ下っていったら、そのときは小学生だろ? 今は中学生か?
ぼくは鈴村にからかわれているのかと思った。
恋人がいると噂に聞いたとき、ぼくが想像したのは(おそらくクラスの誰もが想像していたのは)、もっと性の匂いのする年上の相手だったのだ。
想像とは大きく違ったけれど、それから鈴村が話してくれた「長野の夏」の話は、少なからずぼくにはショックだった。
町の外れに大きなケヤキの木があって、いつもその木の下でふたりが会っていたこと。太い木の根の上に腰を掛けて、日が暮れるまで話をしたこと、歌ったこと。
ミツくんが相手だとなんでも素直に話せたこと、大きな麦わら帽子をかぶっていても、すっかり日に焼けてしまったこと。ミツくんはもともと真っ黒だったこと……。
「夏の間ずっとミツくんと一緒にいて、わたし、すごく自分の心の中が柔らかくなっていくのがわかったの。学校にちゃんと戻れたのは、ミツくんのおかげだと思ってる」
中学生の頃からすでに大人びていたと思われる鈴村が、小学生だったヤツに慰められるという図は想像しにくかったけれど、その後も中3、高1の夏休みを鈴村は長野で過ごしたし、手紙のやりとりは今でもあるらしい。
「香坂君と初めて話をしたとき、ミツくんを思い出したよ」という言葉には、喜んでいいのか悲しむべきなのかわからなかった。
「香坂君とこうして“整頓クラブ”をしているのは、わたしにとって、あの頃ミツくんと欅の下で話していたのと同じ感覚なんだよね……」
ぼくはそいつの代わりなんだろうか? それならそれでも、かまわないような気がしていた。まだまだこれからだ。今、鈴村のそばにいるのはぼくなのだから。
-----
ぼくらは学校で毎日のように会い、週末も長い休みも一緒に過ごし、時間で言えばそれは確実に「ミツくんとの夏」の長さを越していった。
夏休みになっても、鈴村は長野へは行かなかった。ぼくらは毎日のように図書館で一緒に宿題をし、時にはこっそり、閉館間際の閲覧室の椅子をきれいに並べ直してみたりした。
やがてぼくらは手をつないで歩くようになり、JRの高架下で初めてのキスをした。ほとんど同じだった身長も、いつの間にかぼくの方が鈴村をぐいと追い越していた。
ふたりで語り合える思い出話も増えていた。
高校を卒業後、ぼくは写真の専門学校に進み、そこを出るとカメラを持って職を転々とし、短大を出た鈴村は伯父さんの画廊の手伝いを始めて互いに忙しくなった。
その上、ぼくが「用具箱」の姐さんのところで働くようになってからは夜の仕事ばかりで、とうとうふたりの生活は完璧にすれ違うようになってしまった。
それでもぼくらはいつも互いのそばにいる。
一番近くにいる。
少なくともぼくはずっと、そう信じていた。
つづく
Copyright(c) since2004 sakurai All rights reserved.