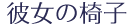







(7)
ひとつひとつの椅子と、一対一ではうまく向き合えないのかもしれない。
ひとりになってレンズを覗きながらそう思った。なにかがしっくりこなかった。
牧野が作った椅子だから、なんだろうか。
部屋全体を眺めて見ても、あれほど考えて並べたはずの椅子たちが、ただ雑然と置かれたようにしか見えなくなってしまった。
結局、ぼくの力なんかなにほどでもないんだと、ますます気持ちが萎えてくる。
しばらくすると牧野がひとりで戻ってきた。
「写真、どうですか?」と聞かれてぼくは正直に首を横に振ってしまった。
牧野はテイクアウトのコーヒーを手渡してくれてから、
「ひとつ、訊いてもいいですか?」と、例の教会の椅子に腰を下ろしてぼくに目線を上げた。
「どうして彼女のこと、俺に何も聞かないんですか?」
-----
写真は、展示会の最終日に改めて撮ることになった。
前祝いに三人で飲みにいきましょうよというマキちゃんの提案を断って、ぼくはひとり、アパートに帰った。今夜は姐さんのところの仕事も無い。
ドアを開ければ正面に、鈴村の椅子が待っている。
ふと思いついてぼくは下ろしたばかりのバッグからカメラを出して構えてみた。
からっぽの聖書入れ。座る人の居ない座面。背もたれにくりぬかれた一本の木……
シャッター音の向こうから鈴村の声がよみがえる。
--- いつもケヤキの下でミツくんとね……
これは、その時のケヤキをかたどっているんだろうか……
そうと決まっているわけでもないのに、胸にもやもやとしたものが広がった。
それで思い切り椅子を蹴り飛ばしてみたくなって右足を引き上げた。けれども、ぼくはただそのままベッドの上に仰向けに身体を投げ出すしかできなかった。
見慣れた天井。
その天井には小さなシミが並んでいる。いつだったか、ぼくの下で鈴村が腕を伸ばして指さし、「台形!」と言ったシミだ。そんなものあったけ? と、彼女を抱いたまま身体を反転させて探すと、窓のある壁の近くに点々と雨が染みたような跡があった。それは確かに、つなげれば台形のようだったけれど、それならそれで椅子みたいだとか富士山みたいだとか、例え方もあるんじゃないかと可笑しかった。
「ジョウテイタスカテイ、カケルタカサ、ワルニ」と、彼女の重みと温かさを全身に感じながらぼくは唱えた。台形といえばそれしか思い浮かばなかったのだ。
鈴村は笑って、
「台形はね、向かい合った一組の辺だけが平行な四角形なの」と、言った。
「ああ、そういえばそうだな」
「わたしと香坂君はどっちの一組だと思う?」
「そりゃ……平行じゃない方の一組だろ。こうして交わってるんだから」
「やだ……もう」
鈴村は怒ったような顔をしながら頬を染めていた。
でも……と、今になってぼくは思う。
交わった後の二本の直線は、どんどん離れて行くのだ。それならばずっと平行に向き合っている方がいいんじゃないのか。
おそらく、鈴村と牧野は一組の平行な辺の方なのだ。ずっとずっと昔から……
ばからしい。
どうしてぼくらを台形に例える必要がある?
-----
「どうして彼女のこと、俺に何も訊かないんですか?」
昼間、牧野にそう言われたとき、ぼくは一瞬、マキちゃんのことかと勘違いしかけた。
「訊かないと、おかしいかな……」
やぁ、キミ、鈴村のこと知ってるだろ? とかなんとか?
「おかしいことはないけれど、いや、俺も、ハナちゃんに聞いたときにすぐ言えれば良かったんですけど、なんとなく話題にし損なってしまって……」
「幼なじみ……なんだよね?」
ただの幼なじみ。そういう風に確かめればよかったのか?
「そうです。知り合ったのはほんとにガキの頃で……」
「いい思い出みたいだよね」
「はい。それはもう、本当に」
高校の頃、鈴村からさんざんその話を聞かされたとは、なぜか言いたくなかった。あれは、あくまでも僕と鈴村の高校時代の思い出だ。誰の話でも何の話でも関係ない。
「それで?」
それで、牧野はどうして今、その話を?
「あれ? 俺、何がいいたかったんだろう……」
そう言って牧野が黙ってしまうと、なんだかぼくは、妹との交際を咎めている兄のような気分になった。その気分のまま、「二度と妹には近づかないように!」と、言える立場だったらどんなにすっきりするだろう。
「鈴村を、……好きなの?」
我ながら、格好悪い訊き方だ。
なのに牧野は笑顔まで見せて、「はい」と答えた。「はい」かよ。どうすんだよ。
「でも、そう、それとこれとは別で、つまり、こうして香坂さんと俺が知り合ったことにハナちゃんは関係がなくて、メッツォで香坂さんを紹介されたのも、写真を見せて貰ったのも偶然なんです。本当に、俺は純粋にただ、あなたに写真を撮ってもらいたいと思っているんですよ」
牧野はぼくが何か、鈴村のことでこだわりを持っていると思っていたんだろうか。
いや、実際、こだわっていたんだけれど……。
「変なこと言ってすみません。ただどうしても、言っておいた方がいいような気がして……」
「それとこれとは別。それでいいんだろ?」
「ええ」
牧野はほっとしたようにカップに口を付けた。それから急に慌てて、「香坂さん、ミルクとか砂糖とか必要でしたか?!」と立ち上がった。ぼくはいらないよと手を振った。本当はブラックは苦手だったけれど、無理をして飲んだ。
−−−
仰向けで天井を見ながらその時のことを思い出して、ぼくの口の中にはまた苦さが広がった。
台形を見つけたときの鈴村の温かさや重さは、思い出せなかった。
つづく
ひとりになってレンズを覗きながらそう思った。なにかがしっくりこなかった。
牧野が作った椅子だから、なんだろうか。
部屋全体を眺めて見ても、あれほど考えて並べたはずの椅子たちが、ただ雑然と置かれたようにしか見えなくなってしまった。
結局、ぼくの力なんかなにほどでもないんだと、ますます気持ちが萎えてくる。
しばらくすると牧野がひとりで戻ってきた。
「写真、どうですか?」と聞かれてぼくは正直に首を横に振ってしまった。
牧野はテイクアウトのコーヒーを手渡してくれてから、
「ひとつ、訊いてもいいですか?」と、例の教会の椅子に腰を下ろしてぼくに目線を上げた。
「どうして彼女のこと、俺に何も聞かないんですか?」
-----
写真は、展示会の最終日に改めて撮ることになった。
前祝いに三人で飲みにいきましょうよというマキちゃんの提案を断って、ぼくはひとり、アパートに帰った。今夜は姐さんのところの仕事も無い。
ドアを開ければ正面に、鈴村の椅子が待っている。
ふと思いついてぼくは下ろしたばかりのバッグからカメラを出して構えてみた。
からっぽの聖書入れ。座る人の居ない座面。背もたれにくりぬかれた一本の木……
シャッター音の向こうから鈴村の声がよみがえる。
--- いつもケヤキの下でミツくんとね……
これは、その時のケヤキをかたどっているんだろうか……
そうと決まっているわけでもないのに、胸にもやもやとしたものが広がった。
それで思い切り椅子を蹴り飛ばしてみたくなって右足を引き上げた。けれども、ぼくはただそのままベッドの上に仰向けに身体を投げ出すしかできなかった。
見慣れた天井。
その天井には小さなシミが並んでいる。いつだったか、ぼくの下で鈴村が腕を伸ばして指さし、「台形!」と言ったシミだ。そんなものあったけ? と、彼女を抱いたまま身体を反転させて探すと、窓のある壁の近くに点々と雨が染みたような跡があった。それは確かに、つなげれば台形のようだったけれど、それならそれで椅子みたいだとか富士山みたいだとか、例え方もあるんじゃないかと可笑しかった。
「ジョウテイタスカテイ、カケルタカサ、ワルニ」と、彼女の重みと温かさを全身に感じながらぼくは唱えた。台形といえばそれしか思い浮かばなかったのだ。
鈴村は笑って、
「台形はね、向かい合った一組の辺だけが平行な四角形なの」と、言った。
「ああ、そういえばそうだな」
「わたしと香坂君はどっちの一組だと思う?」
「そりゃ……平行じゃない方の一組だろ。こうして交わってるんだから」
「やだ……もう」
鈴村は怒ったような顔をしながら頬を染めていた。
でも……と、今になってぼくは思う。
交わった後の二本の直線は、どんどん離れて行くのだ。それならばずっと平行に向き合っている方がいいんじゃないのか。
おそらく、鈴村と牧野は一組の平行な辺の方なのだ。ずっとずっと昔から……
ばからしい。
どうしてぼくらを台形に例える必要がある?
-----
「どうして彼女のこと、俺に何も訊かないんですか?」
昼間、牧野にそう言われたとき、ぼくは一瞬、マキちゃんのことかと勘違いしかけた。
「訊かないと、おかしいかな……」
やぁ、キミ、鈴村のこと知ってるだろ? とかなんとか?
「おかしいことはないけれど、いや、俺も、ハナちゃんに聞いたときにすぐ言えれば良かったんですけど、なんとなく話題にし損なってしまって……」
「幼なじみ……なんだよね?」
ただの幼なじみ。そういう風に確かめればよかったのか?
「そうです。知り合ったのはほんとにガキの頃で……」
「いい思い出みたいだよね」
「はい。それはもう、本当に」
高校の頃、鈴村からさんざんその話を聞かされたとは、なぜか言いたくなかった。あれは、あくまでも僕と鈴村の高校時代の思い出だ。誰の話でも何の話でも関係ない。
「それで?」
それで、牧野はどうして今、その話を?
「あれ? 俺、何がいいたかったんだろう……」
そう言って牧野が黙ってしまうと、なんだかぼくは、妹との交際を咎めている兄のような気分になった。その気分のまま、「二度と妹には近づかないように!」と、言える立場だったらどんなにすっきりするだろう。
「鈴村を、……好きなの?」
我ながら、格好悪い訊き方だ。
なのに牧野は笑顔まで見せて、「はい」と答えた。「はい」かよ。どうすんだよ。
「でも、そう、それとこれとは別で、つまり、こうして香坂さんと俺が知り合ったことにハナちゃんは関係がなくて、メッツォで香坂さんを紹介されたのも、写真を見せて貰ったのも偶然なんです。本当に、俺は純粋にただ、あなたに写真を撮ってもらいたいと思っているんですよ」
牧野はぼくが何か、鈴村のことでこだわりを持っていると思っていたんだろうか。
いや、実際、こだわっていたんだけれど……。
「変なこと言ってすみません。ただどうしても、言っておいた方がいいような気がして……」
「それとこれとは別。それでいいんだろ?」
「ええ」
牧野はほっとしたようにカップに口を付けた。それから急に慌てて、「香坂さん、ミルクとか砂糖とか必要でしたか?!」と立ち上がった。ぼくはいらないよと手を振った。本当はブラックは苦手だったけれど、無理をして飲んだ。
−−−
仰向けで天井を見ながらその時のことを思い出して、ぼくの口の中にはまた苦さが広がった。
台形を見つけたときの鈴村の温かさや重さは、思い出せなかった。
つづく
Copyright(c)