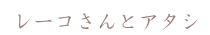
(12)「またいつか」なんてないのかもしれない
朝から外で、ガチャンガチャンと大きな音がしていた。その音がお昼頃まで続いたと思ったら、6階なのに、窓の外に見知らぬ男の顔が見えてびっくり。アタシは水槽の中で跳ねてしまって、覆いになってるプラスチックの天井にしこたま頭をぶつけた。
レーコさんは、人の気配にあわててカーテンを閉めた。
どうやら、マンションの回りに鉄パイプの「足場」というやつが組まれたらしい。
「外壁の塗り直しが終わるまで、こんな風に薄暗いのは憂鬱だなぁ……」
「でも、昼間からカーテンって、なんだか隠微ですよね」
そう言ったのはハラッポ。
「隠微じゃなくて、ただの陰気よ。ねぇ、どこか、出かけよう」
そう言うとレーコさんはさっさとテーブルの上のカップを片づけ始めたけれど、ハラッポは座ったまま、手の平で包んだマグカップを離そうとしない。
「この塗装が終わる頃には、オレもう、この町にいないね」
「そう……か。そうだね」
そういえば、親父が腰を傷めたんで実家に戻って手伝わないといけないかもしれないとか、そんな話をこの間からハラッポがしていたんだ。ハラッポ、どっか行っちゃうのかな。
「向こうに帰ったらもう、こっちには戻れないかもしれない」
「でも……やりがいのある仕事があるんだもの……いいじゃない」
「遠いんだよ?」
「遠いって言ったって、毎朝こっちから通うわけじゃないし……」
おいおい、レーコさん、ハラッポが言ってるのはそういうことじゃないと思うぞ。
「こんな風に会うことも、メールも、たぶんもう、あんまりできない」
「そう……」
「しばらく忙しいだろうし、返事もなかなか……」
「ねぇ、できないできないばっかり言うのよそうよ……」
だよね。だってさ、できないって決めているのはハラッポだよね。今とは違う環境の中で「無理してまで今と同じことはしない」ということだよね。それは、レーコさんは二の次ってことだよね?
アタシだったら、二の次なのはしょうがないにしても、そんな話はあんまり聞きたくないと思うな。
外は、組まれた足場ごと、緑色のシートで覆われ始めていた。ときどきびっくりするほど大きな作業員の声が飛び込んでくるけれど、ふたりとも手元を見ながら、黙ってぼんやりと座っていた。
「原くんが決めたことだからさ」
しばらくしてレーコさんがそうつぶやいた。
「もう決めたんだから、それでいいよ……」
「なんだか、あっさりしてるね」
ハラッポは小さな声で抗議するように言った。まるで、外の人に聞かれるのを恐れるかのようなかすれた声だった。
「だって、他になんて言えばいいの? キミを必要としている人がいて、キミはその力になりたい。だから行くんでしょ? わたしに何か相談している訳じゃないでしょ?」
「ごめん……」
「謝らないでよ」
それを聞いてハラッポは、ぎゅっとマグカップを握りしめた。
こんなとき、高級なガラスのコップならパリンと割れたりして、血が流れたりして、ハラッポかっこいいのにな、なんて、アタシは無責任に思う。そうしたらレーコさん、もっと、我を忘れるくらいオロオロしたりするのかな。
レーコさんは窓のそばに行って、カーテンをそっとつまんで、何も見えない外を覗いた。少しだけ、部屋の中が明るくなるような気がしたけれど、カーテンの向こうにはまた緑色の覆いがある。
「変わるかも、しれないじゃない?」
「え?」
「なにもかも、ずっとなんて続かない。それならまたいつか……ってことだって、あるかもしれないじゃない? この覆いだっていつかは外されて、またいつもの景色が見えるようになるんだしさ……」
「……」
「あ、べつに、待ってるとか言ってるんじゃないから……そうじゃないから、気にしないでいいよ」
馬鹿だな、気にしないでいいわけないくせに。
「あれからわたしなりにずっと考えてて、それで、覚悟はしてたんだ……」
「覚悟って?」
そりゃ、サヨナラじゃないの? だってレーコさんずっと、ずいぶん暗かったよ。何かが変わるって、どんなことだって不安だよね、今までがよかったのなら、なおさらだよね。
そのうち、ハラッポも立ち上がって窓のそばに来た。レーコさんとは違う窓から外を見る。何も見えないのに、ふたりしていつまでもそうやって立っている。
ひょっとしたら、「またいつか」なんてないのかもしれないって、アタシは思った。
レーコさんは、人の気配にあわててカーテンを閉めた。
どうやら、マンションの回りに鉄パイプの「足場」というやつが組まれたらしい。
「外壁の塗り直しが終わるまで、こんな風に薄暗いのは憂鬱だなぁ……」
「でも、昼間からカーテンって、なんだか隠微ですよね」
そう言ったのはハラッポ。
「隠微じゃなくて、ただの陰気よ。ねぇ、どこか、出かけよう」
そう言うとレーコさんはさっさとテーブルの上のカップを片づけ始めたけれど、ハラッポは座ったまま、手の平で包んだマグカップを離そうとしない。
「この塗装が終わる頃には、オレもう、この町にいないね」
「そう……か。そうだね」
そういえば、親父が腰を傷めたんで実家に戻って手伝わないといけないかもしれないとか、そんな話をこの間からハラッポがしていたんだ。ハラッポ、どっか行っちゃうのかな。
「向こうに帰ったらもう、こっちには戻れないかもしれない」
「でも……やりがいのある仕事があるんだもの……いいじゃない」
「遠いんだよ?」
「遠いって言ったって、毎朝こっちから通うわけじゃないし……」
おいおい、レーコさん、ハラッポが言ってるのはそういうことじゃないと思うぞ。
「こんな風に会うことも、メールも、たぶんもう、あんまりできない」
「そう……」
「しばらく忙しいだろうし、返事もなかなか……」
「ねぇ、できないできないばっかり言うのよそうよ……」
だよね。だってさ、できないって決めているのはハラッポだよね。今とは違う環境の中で「無理してまで今と同じことはしない」ということだよね。それは、レーコさんは二の次ってことだよね?
アタシだったら、二の次なのはしょうがないにしても、そんな話はあんまり聞きたくないと思うな。
外は、組まれた足場ごと、緑色のシートで覆われ始めていた。ときどきびっくりするほど大きな作業員の声が飛び込んでくるけれど、ふたりとも手元を見ながら、黙ってぼんやりと座っていた。
「原くんが決めたことだからさ」
しばらくしてレーコさんがそうつぶやいた。
「もう決めたんだから、それでいいよ……」
「なんだか、あっさりしてるね」
ハラッポは小さな声で抗議するように言った。まるで、外の人に聞かれるのを恐れるかのようなかすれた声だった。
「だって、他になんて言えばいいの? キミを必要としている人がいて、キミはその力になりたい。だから行くんでしょ? わたしに何か相談している訳じゃないでしょ?」
「ごめん……」
「謝らないでよ」
それを聞いてハラッポは、ぎゅっとマグカップを握りしめた。
こんなとき、高級なガラスのコップならパリンと割れたりして、血が流れたりして、ハラッポかっこいいのにな、なんて、アタシは無責任に思う。そうしたらレーコさん、もっと、我を忘れるくらいオロオロしたりするのかな。
レーコさんは窓のそばに行って、カーテンをそっとつまんで、何も見えない外を覗いた。少しだけ、部屋の中が明るくなるような気がしたけれど、カーテンの向こうにはまた緑色の覆いがある。
「変わるかも、しれないじゃない?」
「え?」
「なにもかも、ずっとなんて続かない。それならまたいつか……ってことだって、あるかもしれないじゃない? この覆いだっていつかは外されて、またいつもの景色が見えるようになるんだしさ……」
「……」
「あ、べつに、待ってるとか言ってるんじゃないから……そうじゃないから、気にしないでいいよ」
馬鹿だな、気にしないでいいわけないくせに。
「あれからわたしなりにずっと考えてて、それで、覚悟はしてたんだ……」
「覚悟って?」
そりゃ、サヨナラじゃないの? だってレーコさんずっと、ずいぶん暗かったよ。何かが変わるって、どんなことだって不安だよね、今までがよかったのなら、なおさらだよね。
そのうち、ハラッポも立ち上がって窓のそばに来た。レーコさんとは違う窓から外を見る。何も見えないのに、ふたりしていつまでもそうやって立っている。
ひょっとしたら、「またいつか」なんてないのかもしれないって、アタシは思った。
Copyright(c) sakurai All rights reserved.

