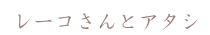
(13)一匹でもひとりじゃない
ある日、アタシが知ってるオトコの中で、一番最初のアイツがやってきた。
「おまえ、まだひとりだったんだな」と、アタシを見てそいつが言った。
名前はなんだっけ。「金魚を見ながら飯は食えない」って言って、アタシを食卓の上から寝室に追いやった、あのオトコだ。
「え? なんか言った?」
キッチンの方からレーコさんの声がくる。
「金魚のこと! いまだに一匹でいるんだなって思ってさ」と、オトコは大きな声で返してから、後は小声でアタシに言う。「あれからずっとひとりだったわけじゃないんだろうけど、とにかく今はひとりだよな。な、そうだろ? レーコって変なとこで気ぃ強いし、強情張ってかわいくないところあるしな」
うーん、ノーコメント。
「世の中にはさ、もっとかわいい女の子がたくさんいるわけだよ。オレってこれでもモテるんだぜ? たださ、かわいい女ってぇーのは、すぐつまんなくなるんだよな。やっぱり、レーコみたいな女こそオレ色に塗り替えて……って、なんだよおまえ、ムリムリって尾っぽを振ってるんだな?」
……アタリ。
「なにぶつぶつ言ってるの?」
「いや、久しぶりに会ったからさ、コイツとも積もる話がある」
「嫌ってなかったっけ? 金魚のこと」
「嫌いじゃねぇよ。食いたくはないだけで」
オトコはくるっとアタシに背を向けて座ると、缶ビールのプルトップを片手で開けた。その腕にはいろんなものがジャラジャラ着いている。
レーコさんは、なんでこのオトコとまた会ってるんだろう。別れたんじゃなかったっけ? なんだか楽しそうにさえも見えるのがアタシには面白くない。
「久しぶりと言えばさ、このマンションどうなってんの。いきなり外壁は白くなってるし、ドアはピンクだし」
……いきなりじゃないぞ、ずいぶん長いことかかって、その間ずっと暗かったんだから。部屋も、レーコさんも。
「部屋の中も外に合わせて乙女チックにしたら? って、妹に言われたわ」
「アッちゃんはピンクとかぬいぐるみとか、そういうの好きそうだよな」
「そうそう」
「そのくせ友だちには、わたしって悪趣味でしょ? っていう、変な自慢の仕方をするんだ」
「そうそう! よくわかってるじゃない」
「そりゃまぁ、姉を射んとせば妹を射よって、一時期は必死でアッちゃんのご機嫌もとったしな……」
それを聞くとレーコさんは急に何かを思い出したように吹き出した。
「温子はね、じぶんがその気にならなかったから、あなたは姉のわたしの方を選んだと思ってるのよ。こっちでいいやってね」
「なんだ? それ」
「おねえちゃんは、ギターのピックのスペアみたいなものよって言われたもん」
レーコさんはなおも笑い続ける。
「別にわたしはどっちだっていいけどね」
そうか、アッちゃんは自分の方がレーコさんより魅力的って、思ってそうだもんなぁ。そういうのは、見る人によって違うんだろうけど。
「なんだよ、どっちでもいいって。オレは真剣だったのに。あんまり笑うと押し倒すぞこら」
それでもレーコさんは笑っていた。オトコも苦笑いしているだけだった。
「そうそう、それで、肝心のケータのことだけどさ」
「ああ、うん」
「悪い奴じゃないよ。アッちゃんのことも遊びじゃない。
バンドやってる連中には、そりゃ、いろんな奴がいるけど、ケータはいいと思うよ。バイトだって休まず真面目にやってるし。まぁ、音楽の才能とか、そういう話になると何とも言えないし、ギターで食って行けるのかって訊かれたら、そりゃぁ、イエスとは言いにくいけどな……」
「でも、とにかく、ちゃんとした人なんだね?」
「おぅ。まともな奴だよ。オレに言えるのはそれだけ」
「そっか。ありがとう」
ふーん。何がありがとうなんだか、アタシにはよくわからないや。
「なに、まさか、結婚したいとか言ってるわけ? あのふたり」
「ううん、まだそんなことは言わないけど、うちの両親がね、心配してるわけよ」
「どこの馬の骨とも分からない……ってやつだよな、親にしてみれば」
「バンドやってるような奴に惚れ込むのは、わたしの影響なんじゃないかって思ってるみたい。いい迷惑だわ」
「なるほどね。じゃあ、その姉の影響でもって、すぐに別れる可能性もあるな」
「金魚は一匹か二匹かでもめて……?」
「寝室か食卓かで争ってさ……」
え? じゃあ、アタシが別れの原因だったわけ? ヤメテヨネー。
「レーコは今でも、一匹でいいと思ってるのか?」
「あら、一匹に見えたって、一匹じゃないってこともあるのよ?」
「へ? そうなの?」
オトコは立ち上がってアタシの水槽を覗きに来た。
わかってないよなぁ、相変わらず。
「おまえ、まだひとりだったんだな」と、アタシを見てそいつが言った。
名前はなんだっけ。「金魚を見ながら飯は食えない」って言って、アタシを食卓の上から寝室に追いやった、あのオトコだ。
「え? なんか言った?」
キッチンの方からレーコさんの声がくる。
「金魚のこと! いまだに一匹でいるんだなって思ってさ」と、オトコは大きな声で返してから、後は小声でアタシに言う。「あれからずっとひとりだったわけじゃないんだろうけど、とにかく今はひとりだよな。な、そうだろ? レーコって変なとこで気ぃ強いし、強情張ってかわいくないところあるしな」
うーん、ノーコメント。
「世の中にはさ、もっとかわいい女の子がたくさんいるわけだよ。オレってこれでもモテるんだぜ? たださ、かわいい女ってぇーのは、すぐつまんなくなるんだよな。やっぱり、レーコみたいな女こそオレ色に塗り替えて……って、なんだよおまえ、ムリムリって尾っぽを振ってるんだな?」
……アタリ。
「なにぶつぶつ言ってるの?」
「いや、久しぶりに会ったからさ、コイツとも積もる話がある」
「嫌ってなかったっけ? 金魚のこと」
「嫌いじゃねぇよ。食いたくはないだけで」
オトコはくるっとアタシに背を向けて座ると、缶ビールのプルトップを片手で開けた。その腕にはいろんなものがジャラジャラ着いている。
レーコさんは、なんでこのオトコとまた会ってるんだろう。別れたんじゃなかったっけ? なんだか楽しそうにさえも見えるのがアタシには面白くない。
「久しぶりと言えばさ、このマンションどうなってんの。いきなり外壁は白くなってるし、ドアはピンクだし」
……いきなりじゃないぞ、ずいぶん長いことかかって、その間ずっと暗かったんだから。部屋も、レーコさんも。
「部屋の中も外に合わせて乙女チックにしたら? って、妹に言われたわ」
「アッちゃんはピンクとかぬいぐるみとか、そういうの好きそうだよな」
「そうそう」
「そのくせ友だちには、わたしって悪趣味でしょ? っていう、変な自慢の仕方をするんだ」
「そうそう! よくわかってるじゃない」
「そりゃまぁ、姉を射んとせば妹を射よって、一時期は必死でアッちゃんのご機嫌もとったしな……」
それを聞くとレーコさんは急に何かを思い出したように吹き出した。
「温子はね、じぶんがその気にならなかったから、あなたは姉のわたしの方を選んだと思ってるのよ。こっちでいいやってね」
「なんだ? それ」
「おねえちゃんは、ギターのピックのスペアみたいなものよって言われたもん」
レーコさんはなおも笑い続ける。
「別にわたしはどっちだっていいけどね」
そうか、アッちゃんは自分の方がレーコさんより魅力的って、思ってそうだもんなぁ。そういうのは、見る人によって違うんだろうけど。
「なんだよ、どっちでもいいって。オレは真剣だったのに。あんまり笑うと押し倒すぞこら」
それでもレーコさんは笑っていた。オトコも苦笑いしているだけだった。
「そうそう、それで、肝心のケータのことだけどさ」
「ああ、うん」
「悪い奴じゃないよ。アッちゃんのことも遊びじゃない。
バンドやってる連中には、そりゃ、いろんな奴がいるけど、ケータはいいと思うよ。バイトだって休まず真面目にやってるし。まぁ、音楽の才能とか、そういう話になると何とも言えないし、ギターで食って行けるのかって訊かれたら、そりゃぁ、イエスとは言いにくいけどな……」
「でも、とにかく、ちゃんとした人なんだね?」
「おぅ。まともな奴だよ。オレに言えるのはそれだけ」
「そっか。ありがとう」
ふーん。何がありがとうなんだか、アタシにはよくわからないや。
「なに、まさか、結婚したいとか言ってるわけ? あのふたり」
「ううん、まだそんなことは言わないけど、うちの両親がね、心配してるわけよ」
「どこの馬の骨とも分からない……ってやつだよな、親にしてみれば」
「バンドやってるような奴に惚れ込むのは、わたしの影響なんじゃないかって思ってるみたい。いい迷惑だわ」
「なるほどね。じゃあ、その姉の影響でもって、すぐに別れる可能性もあるな」
「金魚は一匹か二匹かでもめて……?」
「寝室か食卓かで争ってさ……」
え? じゃあ、アタシが別れの原因だったわけ? ヤメテヨネー。
「レーコは今でも、一匹でいいと思ってるのか?」
「あら、一匹に見えたって、一匹じゃないってこともあるのよ?」
「へ? そうなの?」
オトコは立ち上がってアタシの水槽を覗きに来た。
わかってないよなぁ、相変わらず。
Copyright(c) sakurai All rights reserved.

