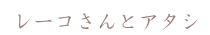
(18)極上じゃないチョコレート
藤野が3度目に来たのは、2月15日の日曜日だった。
最後に藤野を見てからずいぶんたったような気がする。ほら、レーコさんたちの同級生だった千春さんが旦那さんに浮気を疑われていて、その相手を藤野だと旦那さんが思い込んでいるのをいいことに、千春さんが藤野にアリバイ工作を頼んだっていうあの日。旦那さんに尾行された藤野が、自分の恋人は千春さんじゃなくレーコさんだっていう芝居をするためにここに来たあの日以来のことだ。
アタシは藤野が本当にレーコさんの恋人になったらいいのにと思うんだけど、男女の仲というのは金魚の思い通りにはいかないらしいね。
「悪いな、日曜日に邪魔して」
藤野はそう言って、持ってきた包みをテーブルの上にことんと置いた。
「大丈夫よ。べつに予定もないし」
デイトもないし。
「いてくれて助かったよ」
藤野はアタシに背を向ける位置に座った。ちっ。顔が見えないじゃん。
「それで? これが例のゴディバってわけね」
レーコさんは藤野の持ってきた箱を持ち上げてちょっと振った。なんだか笑いを堪えているように見える。
「見ていいの?」
……と聞いたのは、添えられていたカードのことだ。そうして、くくっと鼻を鳴らした。
「変な笑い方するなよ」
「だって、いかにも千春らしいんだもの。『極上の男友達に乾杯!』だなんて、こういうことわたしには書けないよ。極上なの? 藤野君」
「知るかよ。人を物みたいに。俺もう、なんていうか、この脱力感を誰かと分かち合わずにはいられなかったわけよ。分かるだろ? レイちゃんに笑い飛ばしてもらいたいというこの気持ち」
「いいのかなぁ、笑っちゃって。本当はこのチョコ、なにか深い意味があるんじゃないの?」
「ないない。っていうか、あったら困るから笑って欲しいんじゃないかよ。もう千春と関わるのは懲り懲りだよ」
藤野の肘が涙をぬぐうようにして動いた。もちろん、ただの泣き真似だろうけど。
「どうやって受け取ったの?」
「夕べ遅く仕事から帰ったら、ドアにその袋がぶら下がってた」
「うそ」
レーコさんはまた笑い出した。
「お礼の電話はしたの?」
「まだしてない。だって、もう遅かったしさ……」
「しなさいよ、今。見ててあげるから。きっと待ってるわよ。ちゃんと届いたか、心配してるかもしれないし」
「だったらドアなんかに掛けとかなきゃいいだろ」
「いいからいいから、ほら、電話しなさい」
「わかったよ、もう」
藤野は携帯電話を取り出して、ちょっと横を向いた。それでアタシから藤野の横顔が見えるようになった。もみあげがいい。うん、清潔感溢れるもみあげ。アタシの胸びれみたいに無駄のない長さ。それに比べるとハラッポの髪は中途半端だったな。あ、ハラッポと比べることないか。
藤野と千春さんの電話は長かった。
終わりそうになるとまた始まるの繰り返しで、最初のうちは頬杖をついて面白そうに眺めていたレーコさんだったけれど、そのうちに立ち上がって財布を持ち、「買い物してくるね」というゼスチャーをして出ていってしまった。
ほとんど相槌を打つばかりだから話の内容は分からなかった。それでも藤野が長電話にうんざりしていることはアタシにもわかった。藤野はレーコさんが出て行ってしばらくすると「悪いけどさ、そろそろ行かないと」と、電話の向こうに言いながらわざわざ勢いよく立ち上がって、さっきまでとは少し違う乱暴さで話を切り上げた。
「お返しを期待してるわぁ……だなんて、いやになるよなぁ」
藤野はやれやれというように椅子に座り直し、背もたれに肘をかけながらこちらを向いてアタシに話しかけた。アタシはその場泳ぎで「そうよそうよ」と頷いたつもり。
「昔からそうなんだよ。いつだってなんだって、千春は見返りを待ってるんだ。萎えるんだよなぁ、そういうのがわかっちゃってると。……って、金魚に言ってもしょうがないか」
しょうがなくない。もっとしゃべってよとアタシは思ったけど藤野はそれきり背中を戻して黙ってしまった。そのままじっと藤野は腕と足を組んで座っている。タバコも吸わなければ主のいない部屋をじろじろ見たりもしない。落ち着いて座っている藤野はうなじも綺麗だ。背中さえかっこいい。う、眩しい。……大丈夫かな、アタシ。
「ただいま……あれ? 寝てた?」
「うん、いや……考えごと」
なんだ……動かないと思ったら寝てたのか。
「せっかくだから食べようね、千春のチョコレート。コーヒーでも煎れるよ」
「ああ」
「千春、なんて言ってた?」
「ん? いつものようにいろいろと理想を語ってたよ。
どんな? とか訊かないでくれよな。思い出すの面倒だから」
そうだろうそうだろう。
「わかった。ところで、はい、これ。一日遅れだけどわたしからの」
レーコさんはコンビニの袋からハート型のチョコレートを出した。
「ありがとう。……って、今買ってきたのか?」
「今じゃ悪い? 最後の一個だったぞ」
「極上の俺様に不二家のハートチョコレートかよ」
「極上はやめなさい」
まったくだ。
「でも懐かしいな。俺、子供の頃はおふくろから毎年これを貰ってたんだ」
「藤野君も?」
「も……って?」
「うん、いや、そういう人がいたのよ。その人は藤野君と違って極上じゃないから80円のチョコでもすごく喜んでくれてね、レーコさんのハートだからって、その場で丸ごとぱくっと口に入れたのよ。思いっ切り大袈裟に口を開けてね。それが銀座の歩行者天国を歩きながらなんだからもう、おかしいやら恥ずかしいやら……。そうそう、おまけにね、虫歯にピーナッツが挟まっちゃって……」
あ、きっとハラッポのことだって、アタシはぴんときた。
「へぇー……」
「なによ」
「レイちゃんてそういう顔するんだ。好きな人の話をするとき」
「やあね……。昔の話よ、昔の!」
「そんな昔かな……。ま、いいや。
俺は一口で食べるなんて、そういう野蛮なことはしないからね。いくらレイちゃんの義理がいっぱい詰まったハートでも!」
「第一、藤野君がそういうことするのって似合わない。やっぱり藤野君にはゴディバなんだろうな。義理でもゴディバ」
そうそう。藤野がでっかい口を開けてハートチョコを一度に口に押し込むなんて、絶対にしてほしくない。いい男がそういうことをすると妙にみっともないものなんだ。
「藤野君のことだから、他にもたくさんチョコ貰ったんだろうね」
「まぁ、それはそれとしてですね、まず、千春のゴディバをさっさと食べて消化しちゃうのが今日の課題なんで、ご協力のほどよろしくお願いしますよ、レーコさま」
そう言うと藤野はレーコさんにもらったハートチョコを、するっと胸ポケットにしまった。
もしかして、あとでこっそりと大口開けて、一口で食べてみたりするんだろうか。
いやだいやだ。そんな想像したくないぞ。
最後に藤野を見てからずいぶんたったような気がする。ほら、レーコさんたちの同級生だった千春さんが旦那さんに浮気を疑われていて、その相手を藤野だと旦那さんが思い込んでいるのをいいことに、千春さんが藤野にアリバイ工作を頼んだっていうあの日。旦那さんに尾行された藤野が、自分の恋人は千春さんじゃなくレーコさんだっていう芝居をするためにここに来たあの日以来のことだ。
アタシは藤野が本当にレーコさんの恋人になったらいいのにと思うんだけど、男女の仲というのは金魚の思い通りにはいかないらしいね。
「悪いな、日曜日に邪魔して」
藤野はそう言って、持ってきた包みをテーブルの上にことんと置いた。
「大丈夫よ。べつに予定もないし」
デイトもないし。
「いてくれて助かったよ」
藤野はアタシに背を向ける位置に座った。ちっ。顔が見えないじゃん。
「それで? これが例のゴディバってわけね」
レーコさんは藤野の持ってきた箱を持ち上げてちょっと振った。なんだか笑いを堪えているように見える。
「見ていいの?」
……と聞いたのは、添えられていたカードのことだ。そうして、くくっと鼻を鳴らした。
「変な笑い方するなよ」
「だって、いかにも千春らしいんだもの。『極上の男友達に乾杯!』だなんて、こういうことわたしには書けないよ。極上なの? 藤野君」
「知るかよ。人を物みたいに。俺もう、なんていうか、この脱力感を誰かと分かち合わずにはいられなかったわけよ。分かるだろ? レイちゃんに笑い飛ばしてもらいたいというこの気持ち」
「いいのかなぁ、笑っちゃって。本当はこのチョコ、なにか深い意味があるんじゃないの?」
「ないない。っていうか、あったら困るから笑って欲しいんじゃないかよ。もう千春と関わるのは懲り懲りだよ」
藤野の肘が涙をぬぐうようにして動いた。もちろん、ただの泣き真似だろうけど。
「どうやって受け取ったの?」
「夕べ遅く仕事から帰ったら、ドアにその袋がぶら下がってた」
「うそ」
レーコさんはまた笑い出した。
「お礼の電話はしたの?」
「まだしてない。だって、もう遅かったしさ……」
「しなさいよ、今。見ててあげるから。きっと待ってるわよ。ちゃんと届いたか、心配してるかもしれないし」
「だったらドアなんかに掛けとかなきゃいいだろ」
「いいからいいから、ほら、電話しなさい」
「わかったよ、もう」
藤野は携帯電話を取り出して、ちょっと横を向いた。それでアタシから藤野の横顔が見えるようになった。もみあげがいい。うん、清潔感溢れるもみあげ。アタシの胸びれみたいに無駄のない長さ。それに比べるとハラッポの髪は中途半端だったな。あ、ハラッポと比べることないか。
藤野と千春さんの電話は長かった。
終わりそうになるとまた始まるの繰り返しで、最初のうちは頬杖をついて面白そうに眺めていたレーコさんだったけれど、そのうちに立ち上がって財布を持ち、「買い物してくるね」というゼスチャーをして出ていってしまった。
ほとんど相槌を打つばかりだから話の内容は分からなかった。それでも藤野が長電話にうんざりしていることはアタシにもわかった。藤野はレーコさんが出て行ってしばらくすると「悪いけどさ、そろそろ行かないと」と、電話の向こうに言いながらわざわざ勢いよく立ち上がって、さっきまでとは少し違う乱暴さで話を切り上げた。
「お返しを期待してるわぁ……だなんて、いやになるよなぁ」
藤野はやれやれというように椅子に座り直し、背もたれに肘をかけながらこちらを向いてアタシに話しかけた。アタシはその場泳ぎで「そうよそうよ」と頷いたつもり。
「昔からそうなんだよ。いつだってなんだって、千春は見返りを待ってるんだ。萎えるんだよなぁ、そういうのがわかっちゃってると。……って、金魚に言ってもしょうがないか」
しょうがなくない。もっとしゃべってよとアタシは思ったけど藤野はそれきり背中を戻して黙ってしまった。そのままじっと藤野は腕と足を組んで座っている。タバコも吸わなければ主のいない部屋をじろじろ見たりもしない。落ち着いて座っている藤野はうなじも綺麗だ。背中さえかっこいい。う、眩しい。……大丈夫かな、アタシ。
「ただいま……あれ? 寝てた?」
「うん、いや……考えごと」
なんだ……動かないと思ったら寝てたのか。
「せっかくだから食べようね、千春のチョコレート。コーヒーでも煎れるよ」
「ああ」
「千春、なんて言ってた?」
「ん? いつものようにいろいろと理想を語ってたよ。
どんな? とか訊かないでくれよな。思い出すの面倒だから」
そうだろうそうだろう。
「わかった。ところで、はい、これ。一日遅れだけどわたしからの」
レーコさんはコンビニの袋からハート型のチョコレートを出した。
「ありがとう。……って、今買ってきたのか?」
「今じゃ悪い? 最後の一個だったぞ」
「極上の俺様に不二家のハートチョコレートかよ」
「極上はやめなさい」
まったくだ。
「でも懐かしいな。俺、子供の頃はおふくろから毎年これを貰ってたんだ」
「藤野君も?」
「も……って?」
「うん、いや、そういう人がいたのよ。その人は藤野君と違って極上じゃないから80円のチョコでもすごく喜んでくれてね、レーコさんのハートだからって、その場で丸ごとぱくっと口に入れたのよ。思いっ切り大袈裟に口を開けてね。それが銀座の歩行者天国を歩きながらなんだからもう、おかしいやら恥ずかしいやら……。そうそう、おまけにね、虫歯にピーナッツが挟まっちゃって……」
あ、きっとハラッポのことだって、アタシはぴんときた。
「へぇー……」
「なによ」
「レイちゃんてそういう顔するんだ。好きな人の話をするとき」
「やあね……。昔の話よ、昔の!」
「そんな昔かな……。ま、いいや。
俺は一口で食べるなんて、そういう野蛮なことはしないからね。いくらレイちゃんの義理がいっぱい詰まったハートでも!」
「第一、藤野君がそういうことするのって似合わない。やっぱり藤野君にはゴディバなんだろうな。義理でもゴディバ」
そうそう。藤野がでっかい口を開けてハートチョコを一度に口に押し込むなんて、絶対にしてほしくない。いい男がそういうことをすると妙にみっともないものなんだ。
「藤野君のことだから、他にもたくさんチョコ貰ったんだろうね」
「まぁ、それはそれとしてですね、まず、千春のゴディバをさっさと食べて消化しちゃうのが今日の課題なんで、ご協力のほどよろしくお願いしますよ、レーコさま」
そう言うと藤野はレーコさんにもらったハートチョコを、するっと胸ポケットにしまった。
もしかして、あとでこっそりと大口開けて、一口で食べてみたりするんだろうか。
いやだいやだ。そんな想像したくないぞ。
Copyright(c) sakurai All rights reserved.

