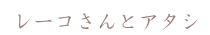
(30)赤いビニールプールに沈める
夕べ遅くに温子さんが来た。ケータと喧嘩をしたらしく、「お姉ちゃん、聞いてよ聞いてよ」と、夜中まで話して珍しくそのまま泊まった。その温子さんが「おそようございます」と起きて来たのはもうお昼になろうかという頃。レーコさんは居間でシュコシュコシュコシュコと空気の音をさせながら足踏みをしている。
「どうしたの? そのビニールプール」
「うん……なんかさ、こういうの見ると、膨らましたくならない?」
「そりゃ、分かんないこともないけど…。だからどうしたのよ、それ」
「こないだセリカが、ほら、千春の娘、あの子がうちに寄った時にさ、お父さんに買ってもらったんだけど、って、言ってね…」
ああ、そうそう、先週セリカが来たんだよ。両親の離婚で普段は離れて暮らしているお父さんと会って、その後でなぜだか知らないけど、レーコさんところで母親の千春さんが迎えにくるのを待ってたんだ。そのときに「お父さんが買ってくれたんだけど、でも、ちょっと困ってる」とセリカが言っていた赤いビニールプール。それをレーコさんは蛇腹の空気入れで膨らませているんだ。
どうするつもりだろう。
「セリカちゃんて、いくつだっけ」
「小学校の3年か、4年…かな。ね、ちょっと、あっちゃんこれ踏むの代わって」
「いいよ、面白そうだし。貸してみ」
今度は温子さんがシュコシュコを踏み始めた。すごい迫力。
「千春たちが住んでいるアパートじゃビニールプールを広げる場所もないんだよね。でも、だから要らないとは、父親に言えなかったらしいんだ、あの子」
そもそも、もうビニールプールなんかで遊ぶような子供じゃないと思うんだけど、セリカの父親の中では、小さな娘のイメージが更新されていないんだろうな。
「だからって、ここに置いてったって仕方ないじゃん」
「まぁ、そうなんだけど。セリカとしては、千春に見せない方がいいと思ったらしいのよ。それで隠して、置いてった」
「……で、それを膨らましていると。なんで?」
「だから、膨らませてみたかったから……」
変なレーコさん。
やがて、赤い三本のチューブに空気が入って、丸いプールの形が出来た。
「おおー、なんか懐かしいね、この臭い。このチューブのところにさ、鈴が入ってたよね、うちのは」
「そうそう。よく覚えてるねあっちゃん。……ね、水、入れてみようか」
マジ? どうしちゃったのレーコさん。
「えー? そこまでやるの? わたしはもう疲れた。お腹がすいたよ」
そう言うと温子さんは、ぼさぼさの頭を掻きながらどっかりと椅子に座り込んでしまった。
レーコさんはさっさとビニールプールを持ち上げるとベランダに持って行った。丸いプールは狭いベランダで少し楕円になる。
「どうでもいいけど、どうやって水入れるの?」
「あ、そっか…」
長いホースなんかないし、水を運べるのはやかんとか、鍋とか洗面器……? と思っていたらレーコさんは、アタシの水槽の水を換える時に使うバケツを持って来て、キッチンからベランダへとせっせと水を運び出した。いったい何往復するつもりなんだろう。
「ねぇねぇ、お姉ちゃん、朝、なに食べたの?」
「あ……そういえば食べてない」
「食べないでよくそんな重労働ができるね」
っていうか、手伝えよ。
「わたしから見たら、温子みたいに動かないで食べてばかりいられる方が不思議なんだけど」
「もう、ケータとおんなじこと言わないでよ」
温子さんは椅子に座ってだらしなく足を投げ出したまま、テーブルの上にあった雑誌をぱパラパラとめくる。レーコさんは何度目かのバケツの水を、静かにプールに注ぎながら水面に見とれている。温子さんはちらっとそんなレーコさんを見て、それからアタシを見て、
「ねぇ、この金魚をそこに泳がせて、キンギョすくいやろっか」と言った。
とんでもねー奴。
レーコさんはちょっとだけ笑って、それからやっぱり水面を見ていた。夏の日差しがきらきらしている。遠くではミーンミーンと蝉の声。
「お姉ちゃんさー、ほんとに引っ越すの?」
ええー? 引っ越しぃ? 初耳だよ!
「まだ決めたわけじゃないけど……」
「わたし、ここ気に入ってんだけどなぁ。古いけど広いから居心地よくてさ。
これ、ページに印してあるやつ、みんな狭いじゃん。わたしとケータと八木さんとお姉ちゃん、4人でいたら窒息しそうじゃん」
「4人でいたら……って、あんたたち遊びに来過ぎなんだから」
そうか、こないだからずっとテーブルの上にあったのはそういう雑誌だったのか。
「お姉ちゃんが引っ越すって聞いた時は、あの生徒会長と暮らすのかと思ったんだけどな」
「ありえないよ」
ありえないのかぁ……。
「それに藤野君は、生徒会やってたけど会長じゃないよ」
「ふーん。ま、どっちでもいいけど。最近、あの人見かけないね」
「そう?」
そうだよー。最近来るのはヤギベエばっかりだよ。
「ねぇねぇ、ケータのアパートの近くに探してみたらどう? あの辺なら手頃な物件が結構たくさんあるし、買い物にも便利だよ。ミーコさんの美容室も最高だし、歯医者さんだって……」
ミーコさん、美容室って、それって、ひょっとしてハラッポの? やばいじゃん。
「だめ。あの街はいや」
「なんで?」
「なんでって、そう、方角が悪いの」
「ちぇー。お姉ちゃんがそばにいたら心強かったんだけどなー」
全然分かってないんだな、温子さん。分かるわけもないんだけど。
「ねぇ、アッちゃんもこっち来てごらんよ、きれいだよ、水。きらきらして。底に描いてある変なクマの絵もユラユラしてる」
「いやだよー、暑いじゃーん」
「何かないかなぁ、水に浮かべられるものとか……」
「だからさ、キンギョを泳がせたらいいじゃん」
いやだよー、暑いじゃーん。
暑いといえば藤野はさ、暑くてもだらだらと汗かいたりしないんだよね。汗をかいてても、かいてますって顔しないんだ。ハラッポは汗っかきだったな、うん。なんか、辛そうに汗をかいてたっけ。ヤギヤギはもう、汗がどうこうより「暑い暑い」って言うのが煩さすぎ。アブラ蝉みたいなやつだ。
次のオトコが現れるとしたら、どんな人なんだろうな。どうせなら藤野よりいい男だったらいいなって、アタシは楽しみにしてるんだけど、なかなか現れそうにない。ああ、面白くないなぁ、なんか面白いことないかなぁ。でも、引っ越しはやだなぁ。揺らされると酔うんだよね、アタシ。
「ねぇ、温子、そこのケータイ取って」
レーコさん、いつの間にか小さなプールの中に立っていた。たくし上げたスカートの下、レーコさんの白い足首が水の中でゆらゆらしている。
「えー? 写真でも撮るの? 自分で取りに来てよぅ」
「投げていいから」
「え?」
「そこから投げて」
「だってこれ、随分前のモデルなのに、お姉ちゃんが気に入ってずっと使ってる奴じゃん。大事なんじゃないの?」
仕方ないなぁというふうに、温子さんが立ち上がってその携帯電話を手渡しに行こうとすると、
「いいから投げてよ。あんたソフトボール部だったじゃん」と、レーコさんは繰り返した。「失敗してもなんにも言わないから、投げてみて」
なにやってんだろうね、この姉妹は。たった3メートルくらいの距離のことで。
「んもう、なんなのよ。相変わらずわけわかんない姉貴だよ。いくよ、ちゃんと受け取ってよ。落として壊れてもわたしのせいにしないでよね。それから、早く朝ご飯を食べさせてよね」
「うん、わかったから」
レーコさん、プールの中で少しだけ後退りして、右手を差し出した。
「いくよ」
青いビーズのストラップのついた白い携帯電話を、温子さんは右手に乗せて下から後ろに引くと、慣れた動作ですっと軽く山なりにベランダの方に放った。その途端に、レーコさんは差し出していた手を引っこめる。携帯は、レーコさんの胸の下あたりに当たってスルリ、
ぽちゃん。
水の中に落ちた。
「わぁ、お姉ちゃん! だからやばいって言ったのにぃ! 早くし…」
「いいのよ。いいんだ、これで」
「だって、データ……」
「実は昨日、新しいケータイ買ってね、電話帳は自分で移したんだ。必要なのだけ。だからここの中に残ってるものはもう…いいんだ」
「なんだー、驚かせないでよ」
「ごめん…」
ぜんっぜん説明になってないと思うけど、レーコさんのそんな行動には慣れているのか、温子さんはそれ以上気にしない。携帯電話に残っていたものってなんだろう。投げさせたのはなぜだろう。そうでもしないと、自分では壊すことのできなかったものって、なんだろう。
小さなビニールプールの底、きらきら光る水面の下、レーコさんの足もとに、白い携帯電話は静かに沈んで動かない。変な絵のクマだけが、今のレーコさんの表情を見ている。
「あ、お姉ちゃん、どっかでケータイが鳴ってるよ。どこ?」
「いい、自分で行く」
そばにあったタオルで急いで足を拭くと、レーコさんは別の部屋へ行った。なんだろあの素早さ。誰かからの電話を待ってたのかな。
「んもう、いつまでも開けっ放しじゃ、エアコンが効かないじゃん」
のろのろと立ち上がってベランダに向かった温子さん、閉じようとした窓のサッシを掴んだまま、レーコさんの真似をして水面を見下ろす。
「ケータのやつ、謝りのメールもくれない。わたしもこのケータイ、水ん中入れちゃおうかなぁー……なんてね。わたしにはとてもそこまで出来ないよ」
温子さんは大げさに肩をすくめると、窓は開けたままアタシのところに来た。
いやな予感。
「ねぇ、アンタってばあの説明不足のお姉ちゃんと暮らしてて疲れない?」
でも、あれで結構わかりやすいとこもあるんだよ。布団かぶって大声あげて泣いたり。それにアタシ、想像してみるの嫌いじゃないし。
「あのためにわざわざプールを膨らませて水を入れたのかな」
いや、それは違うでしょう。きらきらの水を見ているうちに、なんか、吹っ切りたくなったんだと思うよ。
「どうすんだろね、あの水。
ねぇねぇ、アンタさ、広いところで泳いでみたくない? でもって、わたしと遊ばない? こんな狭い水槽なんか出てさ、太陽の下で泳ごうぜい」
なんだなんだ? 急にテンションが上がって来たぞ、温子さん。
「えーと……なんか、ポイの代わりになるものないかなぁ……おたまやスプーンんじゃつまんないよなぁ…。あ、そうだ、ケータも呼ぼう、仲直りのしるしに一緒に……」
うわぁー、キンギョすくいごっこなんていやだよぅ。早く戻って来てなんか言ってやってよ、レーコさーん。
「どうしたの? そのビニールプール」
「うん……なんかさ、こういうの見ると、膨らましたくならない?」
「そりゃ、分かんないこともないけど…。だからどうしたのよ、それ」
「こないだセリカが、ほら、千春の娘、あの子がうちに寄った時にさ、お父さんに買ってもらったんだけど、って、言ってね…」
ああ、そうそう、先週セリカが来たんだよ。両親の離婚で普段は離れて暮らしているお父さんと会って、その後でなぜだか知らないけど、レーコさんところで母親の千春さんが迎えにくるのを待ってたんだ。そのときに「お父さんが買ってくれたんだけど、でも、ちょっと困ってる」とセリカが言っていた赤いビニールプール。それをレーコさんは蛇腹の空気入れで膨らませているんだ。
どうするつもりだろう。
「セリカちゃんて、いくつだっけ」
「小学校の3年か、4年…かな。ね、ちょっと、あっちゃんこれ踏むの代わって」
「いいよ、面白そうだし。貸してみ」
今度は温子さんがシュコシュコを踏み始めた。すごい迫力。
「千春たちが住んでいるアパートじゃビニールプールを広げる場所もないんだよね。でも、だから要らないとは、父親に言えなかったらしいんだ、あの子」
そもそも、もうビニールプールなんかで遊ぶような子供じゃないと思うんだけど、セリカの父親の中では、小さな娘のイメージが更新されていないんだろうな。
「だからって、ここに置いてったって仕方ないじゃん」
「まぁ、そうなんだけど。セリカとしては、千春に見せない方がいいと思ったらしいのよ。それで隠して、置いてった」
「……で、それを膨らましていると。なんで?」
「だから、膨らませてみたかったから……」
変なレーコさん。
やがて、赤い三本のチューブに空気が入って、丸いプールの形が出来た。
「おおー、なんか懐かしいね、この臭い。このチューブのところにさ、鈴が入ってたよね、うちのは」
「そうそう。よく覚えてるねあっちゃん。……ね、水、入れてみようか」
マジ? どうしちゃったのレーコさん。
「えー? そこまでやるの? わたしはもう疲れた。お腹がすいたよ」
そう言うと温子さんは、ぼさぼさの頭を掻きながらどっかりと椅子に座り込んでしまった。
レーコさんはさっさとビニールプールを持ち上げるとベランダに持って行った。丸いプールは狭いベランダで少し楕円になる。
「どうでもいいけど、どうやって水入れるの?」
「あ、そっか…」
長いホースなんかないし、水を運べるのはやかんとか、鍋とか洗面器……? と思っていたらレーコさんは、アタシの水槽の水を換える時に使うバケツを持って来て、キッチンからベランダへとせっせと水を運び出した。いったい何往復するつもりなんだろう。
「ねぇねぇ、お姉ちゃん、朝、なに食べたの?」
「あ……そういえば食べてない」
「食べないでよくそんな重労働ができるね」
っていうか、手伝えよ。
「わたしから見たら、温子みたいに動かないで食べてばかりいられる方が不思議なんだけど」
「もう、ケータとおんなじこと言わないでよ」
温子さんは椅子に座ってだらしなく足を投げ出したまま、テーブルの上にあった雑誌をぱパラパラとめくる。レーコさんは何度目かのバケツの水を、静かにプールに注ぎながら水面に見とれている。温子さんはちらっとそんなレーコさんを見て、それからアタシを見て、
「ねぇ、この金魚をそこに泳がせて、キンギョすくいやろっか」と言った。
とんでもねー奴。
レーコさんはちょっとだけ笑って、それからやっぱり水面を見ていた。夏の日差しがきらきらしている。遠くではミーンミーンと蝉の声。
「お姉ちゃんさー、ほんとに引っ越すの?」
ええー? 引っ越しぃ? 初耳だよ!
「まだ決めたわけじゃないけど……」
「わたし、ここ気に入ってんだけどなぁ。古いけど広いから居心地よくてさ。
これ、ページに印してあるやつ、みんな狭いじゃん。わたしとケータと八木さんとお姉ちゃん、4人でいたら窒息しそうじゃん」
「4人でいたら……って、あんたたち遊びに来過ぎなんだから」
そうか、こないだからずっとテーブルの上にあったのはそういう雑誌だったのか。
「お姉ちゃんが引っ越すって聞いた時は、あの生徒会長と暮らすのかと思ったんだけどな」
「ありえないよ」
ありえないのかぁ……。
「それに藤野君は、生徒会やってたけど会長じゃないよ」
「ふーん。ま、どっちでもいいけど。最近、あの人見かけないね」
「そう?」
そうだよー。最近来るのはヤギベエばっかりだよ。
「ねぇねぇ、ケータのアパートの近くに探してみたらどう? あの辺なら手頃な物件が結構たくさんあるし、買い物にも便利だよ。ミーコさんの美容室も最高だし、歯医者さんだって……」
ミーコさん、美容室って、それって、ひょっとしてハラッポの? やばいじゃん。
「だめ。あの街はいや」
「なんで?」
「なんでって、そう、方角が悪いの」
「ちぇー。お姉ちゃんがそばにいたら心強かったんだけどなー」
全然分かってないんだな、温子さん。分かるわけもないんだけど。
「ねぇ、アッちゃんもこっち来てごらんよ、きれいだよ、水。きらきらして。底に描いてある変なクマの絵もユラユラしてる」
「いやだよー、暑いじゃーん」
「何かないかなぁ、水に浮かべられるものとか……」
「だからさ、キンギョを泳がせたらいいじゃん」
いやだよー、暑いじゃーん。
暑いといえば藤野はさ、暑くてもだらだらと汗かいたりしないんだよね。汗をかいてても、かいてますって顔しないんだ。ハラッポは汗っかきだったな、うん。なんか、辛そうに汗をかいてたっけ。ヤギヤギはもう、汗がどうこうより「暑い暑い」って言うのが煩さすぎ。アブラ蝉みたいなやつだ。
次のオトコが現れるとしたら、どんな人なんだろうな。どうせなら藤野よりいい男だったらいいなって、アタシは楽しみにしてるんだけど、なかなか現れそうにない。ああ、面白くないなぁ、なんか面白いことないかなぁ。でも、引っ越しはやだなぁ。揺らされると酔うんだよね、アタシ。
「ねぇ、温子、そこのケータイ取って」
レーコさん、いつの間にか小さなプールの中に立っていた。たくし上げたスカートの下、レーコさんの白い足首が水の中でゆらゆらしている。
「えー? 写真でも撮るの? 自分で取りに来てよぅ」
「投げていいから」
「え?」
「そこから投げて」
「だってこれ、随分前のモデルなのに、お姉ちゃんが気に入ってずっと使ってる奴じゃん。大事なんじゃないの?」
仕方ないなぁというふうに、温子さんが立ち上がってその携帯電話を手渡しに行こうとすると、
「いいから投げてよ。あんたソフトボール部だったじゃん」と、レーコさんは繰り返した。「失敗してもなんにも言わないから、投げてみて」
なにやってんだろうね、この姉妹は。たった3メートルくらいの距離のことで。
「んもう、なんなのよ。相変わらずわけわかんない姉貴だよ。いくよ、ちゃんと受け取ってよ。落として壊れてもわたしのせいにしないでよね。それから、早く朝ご飯を食べさせてよね」
「うん、わかったから」
レーコさん、プールの中で少しだけ後退りして、右手を差し出した。
「いくよ」
青いビーズのストラップのついた白い携帯電話を、温子さんは右手に乗せて下から後ろに引くと、慣れた動作ですっと軽く山なりにベランダの方に放った。その途端に、レーコさんは差し出していた手を引っこめる。携帯は、レーコさんの胸の下あたりに当たってスルリ、
ぽちゃん。
水の中に落ちた。
「わぁ、お姉ちゃん! だからやばいって言ったのにぃ! 早くし…」
「いいのよ。いいんだ、これで」
「だって、データ……」
「実は昨日、新しいケータイ買ってね、電話帳は自分で移したんだ。必要なのだけ。だからここの中に残ってるものはもう…いいんだ」
「なんだー、驚かせないでよ」
「ごめん…」
ぜんっぜん説明になってないと思うけど、レーコさんのそんな行動には慣れているのか、温子さんはそれ以上気にしない。携帯電話に残っていたものってなんだろう。投げさせたのはなぜだろう。そうでもしないと、自分では壊すことのできなかったものって、なんだろう。
小さなビニールプールの底、きらきら光る水面の下、レーコさんの足もとに、白い携帯電話は静かに沈んで動かない。変な絵のクマだけが、今のレーコさんの表情を見ている。
「あ、お姉ちゃん、どっかでケータイが鳴ってるよ。どこ?」
「いい、自分で行く」
そばにあったタオルで急いで足を拭くと、レーコさんは別の部屋へ行った。なんだろあの素早さ。誰かからの電話を待ってたのかな。
「んもう、いつまでも開けっ放しじゃ、エアコンが効かないじゃん」
のろのろと立ち上がってベランダに向かった温子さん、閉じようとした窓のサッシを掴んだまま、レーコさんの真似をして水面を見下ろす。
「ケータのやつ、謝りのメールもくれない。わたしもこのケータイ、水ん中入れちゃおうかなぁー……なんてね。わたしにはとてもそこまで出来ないよ」
温子さんは大げさに肩をすくめると、窓は開けたままアタシのところに来た。
いやな予感。
「ねぇ、アンタってばあの説明不足のお姉ちゃんと暮らしてて疲れない?」
でも、あれで結構わかりやすいとこもあるんだよ。布団かぶって大声あげて泣いたり。それにアタシ、想像してみるの嫌いじゃないし。
「あのためにわざわざプールを膨らませて水を入れたのかな」
いや、それは違うでしょう。きらきらの水を見ているうちに、なんか、吹っ切りたくなったんだと思うよ。
「どうすんだろね、あの水。
ねぇねぇ、アンタさ、広いところで泳いでみたくない? でもって、わたしと遊ばない? こんな狭い水槽なんか出てさ、太陽の下で泳ごうぜい」
なんだなんだ? 急にテンションが上がって来たぞ、温子さん。
「えーと……なんか、ポイの代わりになるものないかなぁ……おたまやスプーンんじゃつまんないよなぁ…。あ、そうだ、ケータも呼ぼう、仲直りのしるしに一緒に……」
うわぁー、キンギョすくいごっこなんていやだよぅ。早く戻って来てなんか言ってやってよ、レーコさーん。
Copyright(c)sakurai All rights reserved.

