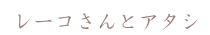
(31)不登校なシフォンケーキ
シャカシャカとかギイィーンだとか、今まで聞いたことのない音がキッチンから聞こえている。
「あの子ったら、ああやって毎日ケーキばかり焼いてるのよ」
そう言って台所に向かってあごをしゃくったのは、レーコさんの従姉妹の葉月さん。雨の土曜日、葉月さんは娘の美月さんを連れて来た。大きな荷物がふたつ。そのひとつには、お菓子の道具がわんさか入っていた。
「レーコちゃんのところにオーブンがあってよかったわ。そうじゃなかったら、オーブンごと持って来なくちゃならなかった」
葉月さんはレーコさんよりもいくつか年上で、いく回りも太めの人だ。マニキュアを塗った爪がやけに小さく見える。金魚の鱗みたい。
「ねぇ、美月を預けて本当に迷惑じゃない? 三連休なのに出かけないの? 泊まりに来る恋人とか、いないの?」
「大丈夫です。美月ちゃんが金魚さえ苦手じゃなきゃ」
「ああ、金魚くらいなら大丈夫」
そう言って葉月さんはちらっとアタシを見た。なんだよ、「金魚くらい」って。
14歳の美月はずっと「フトーコー」で「ヒキコモリ」なのだと、こないだ葉月さんがひとりで来た時に話していた。ひょっとしたらしばらく家を離れてみるのも気分転換になるんじゃないかと言ってみたら、美月が「レーコさんのところなら行ってもいい」と言ったらしい。「親戚関係で、一人暮らししているのがレーコちゃんくらいだからかもしれないわ。あの子、人がたくさんいるとダメなのよ」だそうで、ふん、どうせ”金魚くらい”なら大丈夫なんだ。
「お母さん」
いつの間にか美月が葉月さんの後ろに立っていた。背がひょろっとして、でも猫背で、なんだか暗い感じのする子だ。
「もう帰っていいよ」
声もなんだか低くて暗いんだな。
「あ、そう? じゃ、レーコちゃん、あとはよろしくね」
葉月さんはなんだか逃げるように帰って行った。美月と離れて気分転換が必要なのは母親の方なのかもしれない。
美月はまたキッチンに戻って自分の世界に入る。レーコさん、きっとどうしていいか分からないだろうなぁ。水槽の中のアタシだってなんとなく泳ぎ方がぎくしゃくしちゃうよ。
「ねぇ、何か、足りないものとかない?」
レーコさん、キッチンの前で言ってみる。
「大丈夫です。全部持って来ましたし」
なんと、テーブルの上には卵が4ダースも乗っているんだ。あんなにたくさんの卵、アタシは初めて見たよ。
「じゃ、何か手伝えることないかな」
「いいです。いつもひとりでやってるし」
「お母さんに教えてもらったの?」
「いいえ。あの人は食べるだけ。それも最近は迷惑そう」
「そうなんだ……」
だろうね、あんだけ太っちゃったらさ。
「この黄身はどうするの?」
ガラスのカップの中にある、卵の黄身だけを見つけてレーコさんが言った。
「あ、それは余りです。シフォンケーキは白身をたくさん使うから、卵黄は余っちゃうんです」
「そうなんだ…」
……で、また沈黙かと思ったら玄関の呼び鈴が鳴った。美月がびくっとしてレーコさんを見る。誰だろうとつぶやきながらレーコさんが出ると、「やあやあ!」って暢気な声。ヤギヤギ、またオマエなのか……。
「ん? なんか、バニラくさいぞ?」
そう言ってどんどん勝手に上がって来るし。ほら、美月がボウルを持ったまま固まってる。
「あ、この子、従姉妹の子供で美月ちゃん」
「ふーん。じゃあ、レーコと血が繋がってんだ」
「だれ……ですか?」
美月はとがめるような目でレーコさんを見た。誰も来ないって言ったじゃんと言いたそうな目だ。
「この人は八木さん。すぐ帰るから大丈夫」
「なんだよ。泊まってくよ、おれ」
「もう、そういうややこしい冗談を言わないで。大丈夫よ、美月ちゃん。この人忙しいし、本当にすぐ帰っちゃうから」
そうそう、早く帰れ。
もう、何しに来たのよとレーコさんが小突くと、近所に引っ越し準備の段ボールを運んで来る用があっただとか、午後の仕事がキャンセルになってとか言いながら、ヤギヤギはお菓子の道具の入った袋を覗き込んで「へぇー」と唸る。それから美月の手元を見ながら、
「ねぇ、あんたの”ず”は、つにテンテン? すにテンテン?」なんて言うから、アタシは目がテンテンだ。
美月は背中でボウルを隠すようにして手を動かし続けている。
「真剣だねぇ。おれはシュークリームだったなぁ」
はぁ?
「高校ん時、好きになった子がシュークリームを好きだって言うからさ、上手くできるまで作りまくったんだ」
うわぁー、なに、その女の子みたいな発想。
「自分で焼いてプレゼントしようと思うなんて、すごいね」
と、美月ちゃんの前だからなのか、レーコさんはさも感心したように言う。
「だってさ、ケーキ屋に行って買うのは恥ずかしいだろ」
「それで、上手くできたの?」
「それがさー、最初のうちは皮が全然シュゥって膨らまなくってさぁ…」
ガチャンと、美月がオーブンの扉を閉じた。ピピピピと温度と時間を合わせて、動き出すのをしばらく眺めている。その姿勢のまま、
「絶対に途中で開けちゃだめなんですよ」と言った。
「え?」というレーコさん押しのけるようにして、
「な、な、そうなんだよな。途中で開けるから膨らまなかったんだよな」と、ヤギヤギが身を乗り出した。そうか、シュークリームの話か。
「本に、書いてなかったですか?」
「なかったんだよなぁ、それが。いや、あったのかなぁ……」
「書いてありますよ、ふつう」
「まぁさ、それで、何回目だったかなぁ、たまたまその時はさ……」
ヤギヤギはずりずりと椅子を引っ張って来て反対向きにまたがると、背もたれに腕を乗せるようにして美月のそばに座って話し続ける。美月は使った道具を洗いながら、時々はヤギヤギを見てぼそっと何か言うから聞いているんだろう。おやおや、なんだろうこの雰囲気。
そうやって、中学生とお菓子の話なんかしているヤギヤギの姿は新鮮だ。レーコさんも、不思議なものを見るような顔で、座ることもできずに突っ立って見ている。
「それで、どうなったの? その好きな子とは」
と訊いたのはレーコさん。
「ああ、プレゼントする前に振られた。でも、シュークリームの作り方はうまくなった」
「で、次に好きになった子がギターを好きだったからギターを……とか言うんじゃないでしょうね」
「なんで分かるんだよ」
うう、なんて分かり易い男なんだ。
「かっこいいとこ見せたくてさ、学校なんか行かないで一日中、練習しまくったよ。なんせ文化祭まで日もなくてさ……。それがきっかけでまぁ、今があるようなものだな、うん」
でもきっと、その子にも振られたんだね。ふふふん。
「おじさんは、ミュージシャンかなにかなんですか?」
と、美月。
「このおじさんは、ただの引っ越し屋さんよ」
と、レーコさん。
「なんだよ、お兄さんはミュージシャンだよ。ミュージシャンが引っ越し屋もやってちゃいけないのかよ。……いや、いけないよなぁ。おれ最近、手が心配になってきた。いや、腰も心配だけどよ、重いもの持ったりなんだりしてて、腕とか指を傷めたら、ミュージシャンとしちゃやばいよな」
ミュージシャンというところに妙に力を込めるから変に聞こえる。
「でもそんなこと言ってたら他のことはなんにもできないじゃない? ほら、タバコなんか吸ってヤケドしたらどうするの?」
「うっせ。そんなことより早く灰皿を出しなさい。アチチ…」
そんなやり取りを見るうちに、いつの間にか美月の顔つきが柔らかくなっている。
「ところでこのコップの中の黄身はどうすんの?」
「余りなんですって」とレーコさん。
「いらないの?」
「えぇ…まぁ…」と美月。
「んじゃ、ミュージシャンのお兄さんがこの卵黄でカスタードクリームを作ってあげようじゃないの。んで、オーブンが空いたら、シュー皮も焼いてしんぜよう」
えー? 本当に作れるの? 似合わねぇー。
「そんなこと、今までしてみせたことないじゃない」
「男にはね、女に隠している才能のひとつやふたつあるもんよ。それに、オマエにはほら、金魚をすくってやったじゃないか。あれをオマエにすくってやる為に、おれが人知れずどれだけの鍛錬を重ねたと思ってるの?」
だからさ、アタシをすくったのはレーコさんだっつのに。
そう言っている間にも、ヤギヤギはちゃっちゃと手を動かしているようだった。美月が助手のようにそばに立って手を貸したりするのをまた、レーコさんは珍しそうに眺めていた。
部屋の中には甘い匂いが漂って、ちょっと幸せな雰囲気も漂う。
午後になって出来立てのお菓子を頬張るころには、美月もずいぶん打ち解けて話をするようになっていた。不登校になったのは、学校がいやなんじゃなく、いじめがあるからでもない。ただなんとなく、人の目が気になって、人に会うのが嫌で外に出たくないだけなんだという。そんな話を、レーコさんは心の中にメモを取るようにして聞いていた。あとで葉月さんに報告するんだろう。
「行きたくないときは行かないでいいんじゃないの? 義務教育だしさ、卒業は出来るっしょ」
と、ヤギヤギは無責任に言う。「ジュケン」が心配だって、葉月さんは言ってたけどね。
「それよりどうよ、ミュージシャンのシュークリーム」
「まあまあですね」
「レーコは?」
「最高に美味しい……美月ちゃんのシフォンケーキ」
「そっちかよ。でも、うん、確かに美味い。美月、おまえはシフォンで卒業してシフォンで高校に行け」
なんだよ、それって。
まったく意味を成さない言葉だけど、美月はちょっと満足そうにニヤっとして、それから「このコーヒーも美味しいです」とレーコさんにお世辞を使った。
「こいつはこう見えてもアバウトでね、コーヒーくらいしかちゃんと量らないんだ。だいたいここんちには、秤ってものがないんだから」
「悪かったわね」
秤があったら、もっと前にヤギヤギはシュークリームを作ってみせてたのかな。
「あの…」
ふと思い出したように美月が言った。
「わたしの”ず”は、つにテンテンです」
あ、目に点々の話?
「お、そうか、ミヅキなのか」
「はい。美しい月って書きます。名前負けだけど」
「おれはね、カヅキ。香ばしい月」
ヒョエー……そうだったの?
「音だけ聞くとみんなカズキだと思うんだよね、そんなありふれた名前と違うっつのに」
「少女漫画みたいな名前よね?」
「でも……なんか、かっこいいです。他のカズキは似合わないです」
「だろー?」
アタシにはなんだか分からないけど、「つにテンテン」同士ってことで、美月とヤギヤギの話は盛り上がる。
それにしても、来たばっかりの時とは美月の印象は随分変わった。ヤギヤギの影響だと思うとなんだか悔しいけど、でもきっと、いいことなんだろう。ここだけの話、レーコさんひとりじゃどうしようもなかったんじゃないかな。
「なんだ美月、ここに泊まってくのか? おれも一緒に泊まってこうかなぁ」
って言ったけれど、それは「だめ」って美月にもきっぱり断られてヤギヤギは帰って行った。
急に静かになった部屋で、「さて」とレーコさん。「次は何を作る?」
そうやって、信じられないことに夜遅くまで甘い匂いは続いた。
明日起きたら、秤を買いに行くからつきあってねと、寝る前にレーコさんは言った。
「あの子ったら、ああやって毎日ケーキばかり焼いてるのよ」
そう言って台所に向かってあごをしゃくったのは、レーコさんの従姉妹の葉月さん。雨の土曜日、葉月さんは娘の美月さんを連れて来た。大きな荷物がふたつ。そのひとつには、お菓子の道具がわんさか入っていた。
「レーコちゃんのところにオーブンがあってよかったわ。そうじゃなかったら、オーブンごと持って来なくちゃならなかった」
葉月さんはレーコさんよりもいくつか年上で、いく回りも太めの人だ。マニキュアを塗った爪がやけに小さく見える。金魚の鱗みたい。
「ねぇ、美月を預けて本当に迷惑じゃない? 三連休なのに出かけないの? 泊まりに来る恋人とか、いないの?」
「大丈夫です。美月ちゃんが金魚さえ苦手じゃなきゃ」
「ああ、金魚くらいなら大丈夫」
そう言って葉月さんはちらっとアタシを見た。なんだよ、「金魚くらい」って。
14歳の美月はずっと「フトーコー」で「ヒキコモリ」なのだと、こないだ葉月さんがひとりで来た時に話していた。ひょっとしたらしばらく家を離れてみるのも気分転換になるんじゃないかと言ってみたら、美月が「レーコさんのところなら行ってもいい」と言ったらしい。「親戚関係で、一人暮らししているのがレーコちゃんくらいだからかもしれないわ。あの子、人がたくさんいるとダメなのよ」だそうで、ふん、どうせ”金魚くらい”なら大丈夫なんだ。
「お母さん」
いつの間にか美月が葉月さんの後ろに立っていた。背がひょろっとして、でも猫背で、なんだか暗い感じのする子だ。
「もう帰っていいよ」
声もなんだか低くて暗いんだな。
「あ、そう? じゃ、レーコちゃん、あとはよろしくね」
葉月さんはなんだか逃げるように帰って行った。美月と離れて気分転換が必要なのは母親の方なのかもしれない。
美月はまたキッチンに戻って自分の世界に入る。レーコさん、きっとどうしていいか分からないだろうなぁ。水槽の中のアタシだってなんとなく泳ぎ方がぎくしゃくしちゃうよ。
「ねぇ、何か、足りないものとかない?」
レーコさん、キッチンの前で言ってみる。
「大丈夫です。全部持って来ましたし」
なんと、テーブルの上には卵が4ダースも乗っているんだ。あんなにたくさんの卵、アタシは初めて見たよ。
「じゃ、何か手伝えることないかな」
「いいです。いつもひとりでやってるし」
「お母さんに教えてもらったの?」
「いいえ。あの人は食べるだけ。それも最近は迷惑そう」
「そうなんだ……」
だろうね、あんだけ太っちゃったらさ。
「この黄身はどうするの?」
ガラスのカップの中にある、卵の黄身だけを見つけてレーコさんが言った。
「あ、それは余りです。シフォンケーキは白身をたくさん使うから、卵黄は余っちゃうんです」
「そうなんだ…」
……で、また沈黙かと思ったら玄関の呼び鈴が鳴った。美月がびくっとしてレーコさんを見る。誰だろうとつぶやきながらレーコさんが出ると、「やあやあ!」って暢気な声。ヤギヤギ、またオマエなのか……。
「ん? なんか、バニラくさいぞ?」
そう言ってどんどん勝手に上がって来るし。ほら、美月がボウルを持ったまま固まってる。
「あ、この子、従姉妹の子供で美月ちゃん」
「ふーん。じゃあ、レーコと血が繋がってんだ」
「だれ……ですか?」
美月はとがめるような目でレーコさんを見た。誰も来ないって言ったじゃんと言いたそうな目だ。
「この人は八木さん。すぐ帰るから大丈夫」
「なんだよ。泊まってくよ、おれ」
「もう、そういうややこしい冗談を言わないで。大丈夫よ、美月ちゃん。この人忙しいし、本当にすぐ帰っちゃうから」
そうそう、早く帰れ。
もう、何しに来たのよとレーコさんが小突くと、近所に引っ越し準備の段ボールを運んで来る用があっただとか、午後の仕事がキャンセルになってとか言いながら、ヤギヤギはお菓子の道具の入った袋を覗き込んで「へぇー」と唸る。それから美月の手元を見ながら、
「ねぇ、あんたの”ず”は、つにテンテン? すにテンテン?」なんて言うから、アタシは目がテンテンだ。
美月は背中でボウルを隠すようにして手を動かし続けている。
「真剣だねぇ。おれはシュークリームだったなぁ」
はぁ?
「高校ん時、好きになった子がシュークリームを好きだって言うからさ、上手くできるまで作りまくったんだ」
うわぁー、なに、その女の子みたいな発想。
「自分で焼いてプレゼントしようと思うなんて、すごいね」
と、美月ちゃんの前だからなのか、レーコさんはさも感心したように言う。
「だってさ、ケーキ屋に行って買うのは恥ずかしいだろ」
「それで、上手くできたの?」
「それがさー、最初のうちは皮が全然シュゥって膨らまなくってさぁ…」
ガチャンと、美月がオーブンの扉を閉じた。ピピピピと温度と時間を合わせて、動き出すのをしばらく眺めている。その姿勢のまま、
「絶対に途中で開けちゃだめなんですよ」と言った。
「え?」というレーコさん押しのけるようにして、
「な、な、そうなんだよな。途中で開けるから膨らまなかったんだよな」と、ヤギヤギが身を乗り出した。そうか、シュークリームの話か。
「本に、書いてなかったですか?」
「なかったんだよなぁ、それが。いや、あったのかなぁ……」
「書いてありますよ、ふつう」
「まぁさ、それで、何回目だったかなぁ、たまたまその時はさ……」
ヤギヤギはずりずりと椅子を引っ張って来て反対向きにまたがると、背もたれに腕を乗せるようにして美月のそばに座って話し続ける。美月は使った道具を洗いながら、時々はヤギヤギを見てぼそっと何か言うから聞いているんだろう。おやおや、なんだろうこの雰囲気。
そうやって、中学生とお菓子の話なんかしているヤギヤギの姿は新鮮だ。レーコさんも、不思議なものを見るような顔で、座ることもできずに突っ立って見ている。
「それで、どうなったの? その好きな子とは」
と訊いたのはレーコさん。
「ああ、プレゼントする前に振られた。でも、シュークリームの作り方はうまくなった」
「で、次に好きになった子がギターを好きだったからギターを……とか言うんじゃないでしょうね」
「なんで分かるんだよ」
うう、なんて分かり易い男なんだ。
「かっこいいとこ見せたくてさ、学校なんか行かないで一日中、練習しまくったよ。なんせ文化祭まで日もなくてさ……。それがきっかけでまぁ、今があるようなものだな、うん」
でもきっと、その子にも振られたんだね。ふふふん。
「おじさんは、ミュージシャンかなにかなんですか?」
と、美月。
「このおじさんは、ただの引っ越し屋さんよ」
と、レーコさん。
「なんだよ、お兄さんはミュージシャンだよ。ミュージシャンが引っ越し屋もやってちゃいけないのかよ。……いや、いけないよなぁ。おれ最近、手が心配になってきた。いや、腰も心配だけどよ、重いもの持ったりなんだりしてて、腕とか指を傷めたら、ミュージシャンとしちゃやばいよな」
ミュージシャンというところに妙に力を込めるから変に聞こえる。
「でもそんなこと言ってたら他のことはなんにもできないじゃない? ほら、タバコなんか吸ってヤケドしたらどうするの?」
「うっせ。そんなことより早く灰皿を出しなさい。アチチ…」
そんなやり取りを見るうちに、いつの間にか美月の顔つきが柔らかくなっている。
「ところでこのコップの中の黄身はどうすんの?」
「余りなんですって」とレーコさん。
「いらないの?」
「えぇ…まぁ…」と美月。
「んじゃ、ミュージシャンのお兄さんがこの卵黄でカスタードクリームを作ってあげようじゃないの。んで、オーブンが空いたら、シュー皮も焼いてしんぜよう」
えー? 本当に作れるの? 似合わねぇー。
「そんなこと、今までしてみせたことないじゃない」
「男にはね、女に隠している才能のひとつやふたつあるもんよ。それに、オマエにはほら、金魚をすくってやったじゃないか。あれをオマエにすくってやる為に、おれが人知れずどれだけの鍛錬を重ねたと思ってるの?」
だからさ、アタシをすくったのはレーコさんだっつのに。
そう言っている間にも、ヤギヤギはちゃっちゃと手を動かしているようだった。美月が助手のようにそばに立って手を貸したりするのをまた、レーコさんは珍しそうに眺めていた。
部屋の中には甘い匂いが漂って、ちょっと幸せな雰囲気も漂う。
午後になって出来立てのお菓子を頬張るころには、美月もずいぶん打ち解けて話をするようになっていた。不登校になったのは、学校がいやなんじゃなく、いじめがあるからでもない。ただなんとなく、人の目が気になって、人に会うのが嫌で外に出たくないだけなんだという。そんな話を、レーコさんは心の中にメモを取るようにして聞いていた。あとで葉月さんに報告するんだろう。
「行きたくないときは行かないでいいんじゃないの? 義務教育だしさ、卒業は出来るっしょ」
と、ヤギヤギは無責任に言う。「ジュケン」が心配だって、葉月さんは言ってたけどね。
「それよりどうよ、ミュージシャンのシュークリーム」
「まあまあですね」
「レーコは?」
「最高に美味しい……美月ちゃんのシフォンケーキ」
「そっちかよ。でも、うん、確かに美味い。美月、おまえはシフォンで卒業してシフォンで高校に行け」
なんだよ、それって。
まったく意味を成さない言葉だけど、美月はちょっと満足そうにニヤっとして、それから「このコーヒーも美味しいです」とレーコさんにお世辞を使った。
「こいつはこう見えてもアバウトでね、コーヒーくらいしかちゃんと量らないんだ。だいたいここんちには、秤ってものがないんだから」
「悪かったわね」
秤があったら、もっと前にヤギヤギはシュークリームを作ってみせてたのかな。
「あの…」
ふと思い出したように美月が言った。
「わたしの”ず”は、つにテンテンです」
あ、目に点々の話?
「お、そうか、ミヅキなのか」
「はい。美しい月って書きます。名前負けだけど」
「おれはね、カヅキ。香ばしい月」
ヒョエー……そうだったの?
「音だけ聞くとみんなカズキだと思うんだよね、そんなありふれた名前と違うっつのに」
「少女漫画みたいな名前よね?」
「でも……なんか、かっこいいです。他のカズキは似合わないです」
「だろー?」
アタシにはなんだか分からないけど、「つにテンテン」同士ってことで、美月とヤギヤギの話は盛り上がる。
それにしても、来たばっかりの時とは美月の印象は随分変わった。ヤギヤギの影響だと思うとなんだか悔しいけど、でもきっと、いいことなんだろう。ここだけの話、レーコさんひとりじゃどうしようもなかったんじゃないかな。
「なんだ美月、ここに泊まってくのか? おれも一緒に泊まってこうかなぁ」
って言ったけれど、それは「だめ」って美月にもきっぱり断られてヤギヤギは帰って行った。
急に静かになった部屋で、「さて」とレーコさん。「次は何を作る?」
そうやって、信じられないことに夜遅くまで甘い匂いは続いた。
明日起きたら、秤を買いに行くからつきあってねと、寝る前にレーコさんは言った。
Copyright(c)sakurai All rights reserved.

