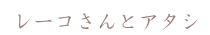
(6)自分を生きてきたんだよ
ある日突然、レーコさんのおばあちゃんが来た。
もっとも、突然だと思ったのはアタシだけで、知らない所ではちゃんと話し合いがあったのかもしれない。
おばあちゃんの荷物は、草色の風呂敷包みひとつだった。
小さな背中は柔らかく丸まっていて、足音も物音もほとんどたてない、とても物静かな人だった。もちろんアタシの水槽を叩いてみたりもしなくて、ただ、「おじゃましますよ」と挨拶をしてくれた。
レーコさんがいない昼間、おばあちゃんはテレビを小さな音で鳴らしながら(たぶん、ほとんど聞こえないと思うんだけど)画面をにこにこ眺めて頷いたり、ソファーの前にちょこんと正座して、長いこと手紙を書いていたりした。
そうして夕方になると、鈴のついたがま口とその手紙を持って買い物にでかけ、帰ってくると魚の煮付けとか野菜の煮ものだとかの、お醤油とかつお出汁の匂いのする料理をして、レーコさんを待つ。
アタシはそんなおばあちゃんが好きになって、夕方になっても風呂敷が解いたままになっていると、ああ、まだ今夜も居てくれるんだなぁとほっとしていた。
レーコさんは会社から帰って食卓に着いても、なかなか話すこともみつからないらしく、ときどき本気で「おいしい!」と声をあげたりするくらいで、いつものように無口だった。おばあちゃんはおばあちゃんで、そんなレーコさんをにこにこ眺めているだけで、やっぱり特別な話はしないのだけれど、それでもなんだかとても穏やかで平和な食卓だった。
アタシはレーコさんの無防備な笑顔を、初めて見るような気がしていた。
ある晩の食事が終わりかけたとき、
「ねぇ、おばあちゃん、あさってはお休みだし、どこかこの辺を案内しようか」
と、レーコさんはちょっと思い切ったように言った。「公園とか、神社とか……」
でもおばあちゃんはゆっくり首をふった。
「気を使わなくていいんだよ。こうして毎日早く帰ってきてくれるけど、レイちゃんが大事な人と会ったりする時間とか、無駄にさせてないかねぇ……」
あ、おばあちゃんて案外するどいじゃん? と、アタシは思った。最近、レーコさんの「残業」がちっともないんだ。なんだか、色がないの。色が。
「大事な人って……男の人のことだったら、今はいないよ、特別な人は」
「そうなのかい?」
……ソウナノカイ?
「あ……そういえば、わたしがおばあちゃんの孫の中では一番年長の女の子だからって、まだ小さいわたしに、『早く大きくなって結婚してひ孫の顔を見せて』って、よくおばあちゃん言ってたね……。
ごめんね、なかなか見せてあげられなくて」
おばあちゃんは湯飲みを手のひらの中であっためながら、「そんなことあったかしらねぇ」とつぶやいた。
「そういうこと言うのは静子じゃないかい?」
静子というのはおばあちゃんの娘、つまり、レーコさんのお母さんのことらしい。
「ひ孫の顔だなんて、わたしはそんなことはどうでもいいよ。
レイちゃんがいい人と、本当にいい人と出会うことができて、その人との時間を大切に過ごせたらそれでいい」
「会えるかな、そういう人に」
「会うのよ。ちゃんとあなたらしく生きていけば、きっと会うの」
レーコさんはちょっと目をまんまるにした。アタシも驚いた。このおばあちゃんのどこからこんな強い言葉が出てくるんだろう。気のせいか背筋もぴんとして。
「おばあちゃんは? そういう人いる? いた? 亡くなった……おじいちゃんじゃなくても……」
あれ? レーコさんが突っ込んだ質問するなんて珍しいとアタシは思った。
でもおばあちゃんは、ふっと湯飲みから顔を上げると声の調子を変えて、
「ねぇ、レイちゃん、おばあちゃんは気になっているんだけど、そのちゃんちゃんこは重くないかい?」と、唐突に訊いた。
「え?」
「今はこっちのほら、こういうのが軽くてあったかいんだろう?」
おばあちゃんはそばにあったフリースの上着に手を伸ばしていた。実際、レーコさんがいつも部屋で羽織っていたのはそのフリースだったんだ。おばあちゃんが来るまでは。
「でもほら、これ、懐かしくて……。
わたしが受験の時に、おばあちゃんが縫ってくれたんだよね」
「そうだったね。温子ちゃんにはあっさり辞退されたけれど、レイちゃんは大事に着てくれたねぇ……」
その、小さなこま犬と鞠の柄の綿入れのちゃんちゃんこは、黒い半襟のところがだいぶ擦れていて、裾にも赤黒い染みがあって、レーコさんが長いこと着ていたことを物語っていた。
それでも捨てられずに、ずっと押し入れにしまったままにしていたんだろう。
「おばあちゃんね、やっぱり明日、帰ることにするよ」
「え? なんで急に? あさってじゃだめ? あさってだったら送っていってあげられるのに……」
「やだねぇ、ちゃんとひとりで帰れますよ」
「それは……そうだろうけど……」
その晩、おばあちゃんは遅くまで起きていた。次の日も、昼間はずっとうずくまって針仕事をしていた。
そうして夕方になると風呂敷をひとつかかえて、アタシに「おじゃましましたね」というと、来たときとおなじようにあっさりと帰っていった。
会社から帰ってきたレーコさんは、電気をつけるとおばあちゃんのいなくなった室内を寂しそうに見回して、それからストーブがあったまるのを待ちながら、その前で電話をかけた。
「もしもしお母さん? わたし、レーコ。
おばあちゃんはちゃんと帰っている?
ならいいんだ……。
大丈夫、おばあちゃん、全然変じゃなかったよ。
ほんとだよ。ちっともおかしくなんてないよ。
ううん、そのことは何も聞かなかった。手紙? 書いていたかもしれない。
いいじゃない。
きっとその人はおばあちゃんのとても大事な人なんだよ。ずっと前からそうだったんだと思うよ。お母さんが気づかなかっただけで。
いつから……って、そんなことわかんないけど……
宛先不明になったのは、先方に何かあったからかもしれないね……急に亡くなったとか……。
だめだよ、知らないふりしてようよ。
だからさ、お母さんにはわからないかもしれないけど……
え ……あのねぇ、そういう言い方はひどくない?
とにかく、もうしばらくそっとしておいた方がいいと思うんだ。
……だから、なんで? って……
ねぇ、おばあちゃんは生きているんだよ。自分を生きてきたんだよ。お母さんの知らないことだってあって当たり前だし、それでいいじゃない。おばあちゃんがにこにこしていられるなら、それが幸せということじゃない? わたしはそう思う」
レーコさんはため息と一緒に電話を切ると、そっと食卓の前に座った。
ふたつのイスには新しく、それぞれに四枚はぎのパッチワークの座布団が敷かれていた。それはあの、かわいらしいこま犬と鞠のちゃんちゃんこで、おばあちゃんが作り直したものだった。
次の日から、宛先不明の付箋を貼られて、レーコさんのところに手紙が何通か返送されてきた。おばあちゃんがこの部屋からあるところに出したものらしかった。
ちゃんとここの住所を書いていたなんて……と、アタシは思った。
レーコさんはその手紙を、もちろん一通も開かずに、そっと引き出しにしまった。
もっとも、突然だと思ったのはアタシだけで、知らない所ではちゃんと話し合いがあったのかもしれない。
おばあちゃんの荷物は、草色の風呂敷包みひとつだった。
小さな背中は柔らかく丸まっていて、足音も物音もほとんどたてない、とても物静かな人だった。もちろんアタシの水槽を叩いてみたりもしなくて、ただ、「おじゃましますよ」と挨拶をしてくれた。
レーコさんがいない昼間、おばあちゃんはテレビを小さな音で鳴らしながら(たぶん、ほとんど聞こえないと思うんだけど)画面をにこにこ眺めて頷いたり、ソファーの前にちょこんと正座して、長いこと手紙を書いていたりした。
そうして夕方になると、鈴のついたがま口とその手紙を持って買い物にでかけ、帰ってくると魚の煮付けとか野菜の煮ものだとかの、お醤油とかつお出汁の匂いのする料理をして、レーコさんを待つ。
アタシはそんなおばあちゃんが好きになって、夕方になっても風呂敷が解いたままになっていると、ああ、まだ今夜も居てくれるんだなぁとほっとしていた。
レーコさんは会社から帰って食卓に着いても、なかなか話すこともみつからないらしく、ときどき本気で「おいしい!」と声をあげたりするくらいで、いつものように無口だった。おばあちゃんはおばあちゃんで、そんなレーコさんをにこにこ眺めているだけで、やっぱり特別な話はしないのだけれど、それでもなんだかとても穏やかで平和な食卓だった。
アタシはレーコさんの無防備な笑顔を、初めて見るような気がしていた。
ある晩の食事が終わりかけたとき、
「ねぇ、おばあちゃん、あさってはお休みだし、どこかこの辺を案内しようか」
と、レーコさんはちょっと思い切ったように言った。「公園とか、神社とか……」
でもおばあちゃんはゆっくり首をふった。
「気を使わなくていいんだよ。こうして毎日早く帰ってきてくれるけど、レイちゃんが大事な人と会ったりする時間とか、無駄にさせてないかねぇ……」
あ、おばあちゃんて案外するどいじゃん? と、アタシは思った。最近、レーコさんの「残業」がちっともないんだ。なんだか、色がないの。色が。
「大事な人って……男の人のことだったら、今はいないよ、特別な人は」
「そうなのかい?」
……ソウナノカイ?
「あ……そういえば、わたしがおばあちゃんの孫の中では一番年長の女の子だからって、まだ小さいわたしに、『早く大きくなって結婚してひ孫の顔を見せて』って、よくおばあちゃん言ってたね……。
ごめんね、なかなか見せてあげられなくて」
おばあちゃんは湯飲みを手のひらの中であっためながら、「そんなことあったかしらねぇ」とつぶやいた。
「そういうこと言うのは静子じゃないかい?」
静子というのはおばあちゃんの娘、つまり、レーコさんのお母さんのことらしい。
「ひ孫の顔だなんて、わたしはそんなことはどうでもいいよ。
レイちゃんがいい人と、本当にいい人と出会うことができて、その人との時間を大切に過ごせたらそれでいい」
「会えるかな、そういう人に」
「会うのよ。ちゃんとあなたらしく生きていけば、きっと会うの」
レーコさんはちょっと目をまんまるにした。アタシも驚いた。このおばあちゃんのどこからこんな強い言葉が出てくるんだろう。気のせいか背筋もぴんとして。
「おばあちゃんは? そういう人いる? いた? 亡くなった……おじいちゃんじゃなくても……」
あれ? レーコさんが突っ込んだ質問するなんて珍しいとアタシは思った。
でもおばあちゃんは、ふっと湯飲みから顔を上げると声の調子を変えて、
「ねぇ、レイちゃん、おばあちゃんは気になっているんだけど、そのちゃんちゃんこは重くないかい?」と、唐突に訊いた。
「え?」
「今はこっちのほら、こういうのが軽くてあったかいんだろう?」
おばあちゃんはそばにあったフリースの上着に手を伸ばしていた。実際、レーコさんがいつも部屋で羽織っていたのはそのフリースだったんだ。おばあちゃんが来るまでは。
「でもほら、これ、懐かしくて……。
わたしが受験の時に、おばあちゃんが縫ってくれたんだよね」
「そうだったね。温子ちゃんにはあっさり辞退されたけれど、レイちゃんは大事に着てくれたねぇ……」
その、小さなこま犬と鞠の柄の綿入れのちゃんちゃんこは、黒い半襟のところがだいぶ擦れていて、裾にも赤黒い染みがあって、レーコさんが長いこと着ていたことを物語っていた。
それでも捨てられずに、ずっと押し入れにしまったままにしていたんだろう。
「おばあちゃんね、やっぱり明日、帰ることにするよ」
「え? なんで急に? あさってじゃだめ? あさってだったら送っていってあげられるのに……」
「やだねぇ、ちゃんとひとりで帰れますよ」
「それは……そうだろうけど……」
その晩、おばあちゃんは遅くまで起きていた。次の日も、昼間はずっとうずくまって針仕事をしていた。
そうして夕方になると風呂敷をひとつかかえて、アタシに「おじゃましましたね」というと、来たときとおなじようにあっさりと帰っていった。
会社から帰ってきたレーコさんは、電気をつけるとおばあちゃんのいなくなった室内を寂しそうに見回して、それからストーブがあったまるのを待ちながら、その前で電話をかけた。
「もしもしお母さん? わたし、レーコ。
おばあちゃんはちゃんと帰っている?
ならいいんだ……。
大丈夫、おばあちゃん、全然変じゃなかったよ。
ほんとだよ。ちっともおかしくなんてないよ。
ううん、そのことは何も聞かなかった。手紙? 書いていたかもしれない。
いいじゃない。
きっとその人はおばあちゃんのとても大事な人なんだよ。ずっと前からそうだったんだと思うよ。お母さんが気づかなかっただけで。
いつから……って、そんなことわかんないけど……
宛先不明になったのは、先方に何かあったからかもしれないね……急に亡くなったとか……。
だめだよ、知らないふりしてようよ。
だからさ、お母さんにはわからないかもしれないけど……
え ……あのねぇ、そういう言い方はひどくない?
とにかく、もうしばらくそっとしておいた方がいいと思うんだ。
……だから、なんで? って……
ねぇ、おばあちゃんは生きているんだよ。自分を生きてきたんだよ。お母さんの知らないことだってあって当たり前だし、それでいいじゃない。おばあちゃんがにこにこしていられるなら、それが幸せということじゃない? わたしはそう思う」
レーコさんはため息と一緒に電話を切ると、そっと食卓の前に座った。
ふたつのイスには新しく、それぞれに四枚はぎのパッチワークの座布団が敷かれていた。それはあの、かわいらしいこま犬と鞠のちゃんちゃんこで、おばあちゃんが作り直したものだった。
次の日から、宛先不明の付箋を貼られて、レーコさんのところに手紙が何通か返送されてきた。おばあちゃんがこの部屋からあるところに出したものらしかった。
ちゃんとここの住所を書いていたなんて……と、アタシは思った。
レーコさんはその手紙を、もちろん一通も開かずに、そっと引き出しにしまった。
Copyright(c) since2004 sakurai All rights reserved.

