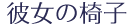

(1)
女子高生たちの制服で車窓を彩られた夕方の都電。それを横目に見ながら、ぼくは線路沿いの歩き慣れた道を急いでいる。
「大塚まで迎えに来てくれない?」と鈴村から電話があった時にはまだ、ベッドの中だった。
どうして駅まで迎えに? ……と、理由を求めかけて口をつぐみ、15分だけ待つように言ってあわてて身支度をして来た。都電の車内から女学生がこっちを見て笑っているような気がする。どこか、ぼくの身なりにおかしいところがあるんじゃないかと心配になり、意味もなく口元に手が行く。そのまま猫背になって急ぐ。
女の子にしては背の高い鈴村を見つけるのは容易いはずだった。なのに、たぶんその辺だろうと思った小さな花屋のそばに彼女が見あたらない。ひょっとして「大塚」といってもいつものJRの駅じゃなく都電の方だろうかと疑いながら通りを越えると、イチョウの木陰、低い位置でひらひらと振られている白い手を見つけた。
鈴村は椅子に座ってぼくを待っていた。
歩道の隅に置いた椅子に座った彼女の姿は、覆いを外されたばかりの真新しいオブジェみたいに居心地の悪い眺めだ。
「この高さから見てると、いつもの駅前もいろいろ新鮮だよ」
ぼくが近づいてもすぐには立ち上がらず、長めのスカートの中の膝をきちんとそろえて鈴村は座っている。回りから見れば彼女の姿の方がよほど新鮮だろう。
「その椅子、鈴村の? 電車で運んで来たのか?」
「そう。重いし、ちょっと恥ずかしかったよ……」
だから「迎えに来てくれ」だったのかと、ぼくは彼女を立たせてその椅子を片手で少し持ち上げてみた。見た目よりもずっしりと重く、背もたれの後ろ側にはポケットのような細工がある椅子だった。そのせいでひどく持ちにくい。
「変わった椅子だね」
「うん、香坂くんとこに置いてほしいんだ。いいでしょ?」
「いいけど……。配送とか頼めなかったの?」
「買ったんじゃないから……」
「盗んだとか?」
「失礼ねえ」
椅子を持って歩いているぼくらは、変に人の目を引くようだった。ましてや電車の中ではどんなに目立っただろう。いったいひとりでどこから運んできたんだろう。改札はどうやって通したんだ? そうまでして運んできたこの椅子は、そもそも鈴村のものなのか、それともぼくへの贈り物なのか。聞きたいことは山ほどあるけれど、ひとつもうまく口から出てこない。
鈴村はぼくの少し前を、手を後ろで組んで一歩一歩、脚を前に放り出すようにしながらゆるゆると歩いている。髪が伸びたなと、ぼくは思う。
さっきとは違う音で都電が行き過ぎた。
「さて、どこに置こうか」
1DKの小さな部屋には、ぼくなりのこだわりできちんと家具が配置されている。その中にこの新入りの椅子をどう置いたら落ち着くのかと、ぼくはだるくなった腕をもみほぐしながら狭い部屋の中をうろうろした。
「壁に押しつけるのはだめよ。聖書入れが活きないから」
部屋の入り口に立って見ていた鈴村がそう言った。
「聖書入れ?」
そうか、このポケットは聖書を入れるためのものなのか。
じゃあこの椅子は教会から盗んで来たのか? と、ぼくはまた軽口をたたこうとしてやめた。いつだって肝心なことは訊けないくせに、そういうくだらないことばかりを口にしてしまう。
椅子が落ち着いたのは窓際の、ベッドの脇だった。それも、ベッドの方に向くように置いたから、「まるで病院にお見舞いに来た人のための椅子みたい」と、鈴村は満足とも不満足とも言えない顔だった。
それにしても、こんな風にふたりが会うのは久しぶりだ。
「今度さ、この椅子のポケットに香坂君への手紙を入れておくね。わたしたち、なかなか会えないし」
置かれたばかりの椅子の背もたれに触れながら、鈴村はそう言った。
「手紙より弁当の方がいいかな」と、ちょうど腹の空いていたぼくが言うと、下を向いたまま小さく笑う。
髪が匂った。
シャンプーでもリンスでもない、鈴村の匂い。
ぼくはやっとするべきことを思い出したような気がして、鈴村の肩を抱き寄せた。一瞬驚いたようにした鈴村も、ぼくの背中に腕を回す。ぼくは目を閉じて唇で唇を探り当ててキスをした。鈴村も応えた。
鈴村とキスをするのはいつ以来だろう……。そっと舌を絡めながらぼくが感じていたのは、官能よりもむしろ安堵のようなものに近かった。
つづく
「大塚まで迎えに来てくれない?」と鈴村から電話があった時にはまだ、ベッドの中だった。
どうして駅まで迎えに? ……と、理由を求めかけて口をつぐみ、15分だけ待つように言ってあわてて身支度をして来た。都電の車内から女学生がこっちを見て笑っているような気がする。どこか、ぼくの身なりにおかしいところがあるんじゃないかと心配になり、意味もなく口元に手が行く。そのまま猫背になって急ぐ。
女の子にしては背の高い鈴村を見つけるのは容易いはずだった。なのに、たぶんその辺だろうと思った小さな花屋のそばに彼女が見あたらない。ひょっとして「大塚」といってもいつものJRの駅じゃなく都電の方だろうかと疑いながら通りを越えると、イチョウの木陰、低い位置でひらひらと振られている白い手を見つけた。
鈴村は椅子に座ってぼくを待っていた。
歩道の隅に置いた椅子に座った彼女の姿は、覆いを外されたばかりの真新しいオブジェみたいに居心地の悪い眺めだ。
「この高さから見てると、いつもの駅前もいろいろ新鮮だよ」
ぼくが近づいてもすぐには立ち上がらず、長めのスカートの中の膝をきちんとそろえて鈴村は座っている。回りから見れば彼女の姿の方がよほど新鮮だろう。
「その椅子、鈴村の? 電車で運んで来たのか?」
「そう。重いし、ちょっと恥ずかしかったよ……」
だから「迎えに来てくれ」だったのかと、ぼくは彼女を立たせてその椅子を片手で少し持ち上げてみた。見た目よりもずっしりと重く、背もたれの後ろ側にはポケットのような細工がある椅子だった。そのせいでひどく持ちにくい。
「変わった椅子だね」
「うん、香坂くんとこに置いてほしいんだ。いいでしょ?」
「いいけど……。配送とか頼めなかったの?」
「買ったんじゃないから……」
「盗んだとか?」
「失礼ねえ」
椅子を持って歩いているぼくらは、変に人の目を引くようだった。ましてや電車の中ではどんなに目立っただろう。いったいひとりでどこから運んできたんだろう。改札はどうやって通したんだ? そうまでして運んできたこの椅子は、そもそも鈴村のものなのか、それともぼくへの贈り物なのか。聞きたいことは山ほどあるけれど、ひとつもうまく口から出てこない。
鈴村はぼくの少し前を、手を後ろで組んで一歩一歩、脚を前に放り出すようにしながらゆるゆると歩いている。髪が伸びたなと、ぼくは思う。
さっきとは違う音で都電が行き過ぎた。
「さて、どこに置こうか」
1DKの小さな部屋には、ぼくなりのこだわりできちんと家具が配置されている。その中にこの新入りの椅子をどう置いたら落ち着くのかと、ぼくはだるくなった腕をもみほぐしながら狭い部屋の中をうろうろした。
「壁に押しつけるのはだめよ。聖書入れが活きないから」
部屋の入り口に立って見ていた鈴村がそう言った。
「聖書入れ?」
そうか、このポケットは聖書を入れるためのものなのか。
じゃあこの椅子は教会から盗んで来たのか? と、ぼくはまた軽口をたたこうとしてやめた。いつだって肝心なことは訊けないくせに、そういうくだらないことばかりを口にしてしまう。
椅子が落ち着いたのは窓際の、ベッドの脇だった。それも、ベッドの方に向くように置いたから、「まるで病院にお見舞いに来た人のための椅子みたい」と、鈴村は満足とも不満足とも言えない顔だった。
それにしても、こんな風にふたりが会うのは久しぶりだ。
「今度さ、この椅子のポケットに香坂君への手紙を入れておくね。わたしたち、なかなか会えないし」
置かれたばかりの椅子の背もたれに触れながら、鈴村はそう言った。
「手紙より弁当の方がいいかな」と、ちょうど腹の空いていたぼくが言うと、下を向いたまま小さく笑う。
髪が匂った。
シャンプーでもリンスでもない、鈴村の匂い。
ぼくはやっとするべきことを思い出したような気がして、鈴村の肩を抱き寄せた。一瞬驚いたようにした鈴村も、ぼくの背中に腕を回す。ぼくは目を閉じて唇で唇を探り当ててキスをした。鈴村も応えた。
鈴村とキスをするのはいつ以来だろう……。そっと舌を絡めながらぼくが感じていたのは、官能よりもむしろ安堵のようなものに近かった。
つづく
Copyright(c) sakurai All rights reserved.