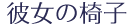





(5)
ゴールデンウィークが明けたばかりの晴れた日だ。久しぶりに歩く昼の街はまぶしく、もう半袖の服を着ている人も多い。姐さんからの電話で呼ばれた店に着く頃には、うっすらと汗をかくほどの陽気だった。
見慣れたメッツォの扉を押すと、カウンターから姐さんがぼくに手招きをした。その動作に気づいたのか、すぐそばでナポリタンを食べていた学生風の若い男が、慌てて紙ナプキンで口元をぬぐって立ち上がる。
「こちら牧野さん。家具を手作りしている将来有望な職人さんよ」
姐さんが少し気取って男を紹介した。
「香坂さんですね。牧野です。はじめまして」
ペコンという感じで頭を下げた牧野という男の口元には、まだ少しケチャップの色がにじんでいる。ぼくは「どうも」と言ってその赤から目をそらし、姐さんを伺った。どういうことだろう。
「ここじゃあれだから、向こうのテーブルで……」
姐さんが空いたテーブルにぼくを促すと、牧野は「あ、ちょっと待ってて下さいね」と、急いで食事の続きをはじめた。
真夏のように、白いTシャツ一枚に履き古したジーンズ。健康的に動く背中は堅く、脂気のない髪は赤茶けていている。
牧野は日向の男だ。
ぼくは急に居心地が悪くなって、自分の長いシャツの袖を丁寧に捲りあげた。
「すみません、お待たせして」
今度は綺麗に口元もぬぐって牧野はぼくの前に座った。その手には、ぼくが撮って姐さんに預けてあったポケットアルバムの束を持っていた。
「香坂さんの写真、見せていただいたんです。それでですね……」
テーブルに乗り出すようにした牧野の話し方はとても早くて、ぼくには口を挟む暇もなかった。途中で姐さんがコーヒーをもってきて、ぼくにウインクをする。
つまりこうだった。
牧野は長野で家具を作っている。特に椅子を。今まではネットを介して販売していたけれど、ある人に認められて、姐さんの持っているビルにあるスタジオで展示会をすることになった。
その椅子を、ぼくにレイアウトさせたらどうだろうというのが姐さんの最初の思いつきだったらしい。そうして、話のついでにぼくの撮った写真を見せたら、牧野は是非写真も撮って貰いたいと、そう考えたというのだ。
「香坂さんの写真の椅子たちは、とても饒舌だと思いました。
整然として饒舌。
ぼくの椅子もそんな写真に撮ってもらいたいんです。どうでしょう」
一息に話し終えた牧野の前で、ぼくは呆けた顔をしていたと思う。なんと答えていいか分らないというのが正直なところだった。そんな「いい話」をにわかには信じられない。
「でも、ぼくのは全くのシロート写真ですよ」
「でも写真、好きでしょう? ぼくもそうです。ただ好きで椅子を作ってるんです。だからこそ、一緒にいいものができそうな気がしませんか?」
なんなんだろう、こいつの自信は。
「とりあえず、彼の椅子を見てご覧よ」と姐さんに促されて、ぼくは店の裏からまだシャッターを閉めたままのスタジオに入った。既に椅子は搬入されていて、いくつかは梱包も解かれていた。どれも、素朴な木の椅子だった。
「実家が蕎麦屋をやってましてね、その店の椅子を直したのが最初でしたよ。
椅子っていうのはこう、人を包み込むように手を広げているような温かさがあると思いませんか」
牧野がひとりでしゃべるのを聞きながら、ぼくは牧野の椅子を見て回った。
どれも、人を待つ椅子だと感じた。誰も座っていない椅子がぼくは好きなのだけど、牧野の椅子は人を呼んでいる。
牧野はいとおしむように椅子の背を撫でながら部屋の奥へと歩いていく。
整然と並べることならぼくは得意だけれど、展示会のための「レイアウト」となると話はまた違う。そう思いながら牧野の手の行く先を見ていたぼくは、見覚えのある椅子をみつけた。
本当は、部屋に入ったときから、そこにそれがあることは予感していたのかもしれない。
「それ……」
「え?」
「教会の椅子……ですよね」
「あ、香坂さんよくご存知ですね。
イギリスの古い教会の椅子を真似てみたんですけど、
ほら、ここのくりぬきの所、本来は十字架の形だったのをこうして……」
牧野が指し示す背もたれには、木の形のくりぬきがあるのだ。触らなくてもぼくにはその手触りがわかる。それは、ぼくの部屋にある鈴村の椅子と全く同じだったのだから。
「どうして大塚に?」とぼくは聞いてみた。牧野は頭をかいて、「東京ならどこでもよかったんですけど、これも縁ですね」と笑った。昔からずっと自分をサポートしてくれている人がこの土地にいること。その人の提案でアンティークの模倣を始めたこと。それが世間に認められたこと。その人から展示会をする場所も提供されたけれど、そこでは手狭なのが分かってここを探し出したこと。
「ぼくが今日あるのはその人のおかげなんです。その教会の椅子も、その人のアイデアだったんですよ」
そう言って微笑む牧野の顔は眩しかった。悔しいくらいに。
返事は改めてということにして家に帰ったぼくは、自分の部屋のベッドの横に置かれた、鈴村のあの椅子をひっくりかえしてみた。座面の裏には、予想したとおり「Mitsu」というサインがあった。
椅子を元に戻し、ついさっき牧野からもらった名刺を聖書入れのポケットに入れる。
『工房HANA まきの充』と書かれた名刺だ。
「どうして?」と、鈴村に聞きたいことが山ほどある。
どうして彼の椅子がここにある?
どうして彼はぼくの前に現れた?
どうして彼のことを黙っていた?
彼は、かつて鈴村が話してくれた、長野の彼に違いない。記憶の中ではいつでも年下の小学生のガキだったライバルが、いきなりでかくなって目の前に現れたのだ。
そして、牧野が自分の工房に付けているのは鈴村の名前だ。鈴村華子の「HANA」に違いない。だとすれば、牧野にとって鈴村は今でも特別な女性なのではないのか。
ぼくだけがずっと鈴村のそばにいたつもりだった。でも本当は、牧野もずっと彼女のそばにいたということだ。
ぼくはずっと鈴村に支えられてきた。でも、牧野もきっとそうなのだ。
突き上げてくるのは今までに感じたことのない強い嫉妬心だった。
つづく
見慣れたメッツォの扉を押すと、カウンターから姐さんがぼくに手招きをした。その動作に気づいたのか、すぐそばでナポリタンを食べていた学生風の若い男が、慌てて紙ナプキンで口元をぬぐって立ち上がる。
「こちら牧野さん。家具を手作りしている将来有望な職人さんよ」
姐さんが少し気取って男を紹介した。
「香坂さんですね。牧野です。はじめまして」
ペコンという感じで頭を下げた牧野という男の口元には、まだ少しケチャップの色がにじんでいる。ぼくは「どうも」と言ってその赤から目をそらし、姐さんを伺った。どういうことだろう。
「ここじゃあれだから、向こうのテーブルで……」
姐さんが空いたテーブルにぼくを促すと、牧野は「あ、ちょっと待ってて下さいね」と、急いで食事の続きをはじめた。
真夏のように、白いTシャツ一枚に履き古したジーンズ。健康的に動く背中は堅く、脂気のない髪は赤茶けていている。
牧野は日向の男だ。
ぼくは急に居心地が悪くなって、自分の長いシャツの袖を丁寧に捲りあげた。
「すみません、お待たせして」
今度は綺麗に口元もぬぐって牧野はぼくの前に座った。その手には、ぼくが撮って姐さんに預けてあったポケットアルバムの束を持っていた。
「香坂さんの写真、見せていただいたんです。それでですね……」
テーブルに乗り出すようにした牧野の話し方はとても早くて、ぼくには口を挟む暇もなかった。途中で姐さんがコーヒーをもってきて、ぼくにウインクをする。
つまりこうだった。
牧野は長野で家具を作っている。特に椅子を。今まではネットを介して販売していたけれど、ある人に認められて、姐さんの持っているビルにあるスタジオで展示会をすることになった。
その椅子を、ぼくにレイアウトさせたらどうだろうというのが姐さんの最初の思いつきだったらしい。そうして、話のついでにぼくの撮った写真を見せたら、牧野は是非写真も撮って貰いたいと、そう考えたというのだ。
「香坂さんの写真の椅子たちは、とても饒舌だと思いました。
整然として饒舌。
ぼくの椅子もそんな写真に撮ってもらいたいんです。どうでしょう」
一息に話し終えた牧野の前で、ぼくは呆けた顔をしていたと思う。なんと答えていいか分らないというのが正直なところだった。そんな「いい話」をにわかには信じられない。
「でも、ぼくのは全くのシロート写真ですよ」
「でも写真、好きでしょう? ぼくもそうです。ただ好きで椅子を作ってるんです。だからこそ、一緒にいいものができそうな気がしませんか?」
なんなんだろう、こいつの自信は。
「とりあえず、彼の椅子を見てご覧よ」と姐さんに促されて、ぼくは店の裏からまだシャッターを閉めたままのスタジオに入った。既に椅子は搬入されていて、いくつかは梱包も解かれていた。どれも、素朴な木の椅子だった。
「実家が蕎麦屋をやってましてね、その店の椅子を直したのが最初でしたよ。
椅子っていうのはこう、人を包み込むように手を広げているような温かさがあると思いませんか」
牧野がひとりでしゃべるのを聞きながら、ぼくは牧野の椅子を見て回った。
どれも、人を待つ椅子だと感じた。誰も座っていない椅子がぼくは好きなのだけど、牧野の椅子は人を呼んでいる。
牧野はいとおしむように椅子の背を撫でながら部屋の奥へと歩いていく。
整然と並べることならぼくは得意だけれど、展示会のための「レイアウト」となると話はまた違う。そう思いながら牧野の手の行く先を見ていたぼくは、見覚えのある椅子をみつけた。
本当は、部屋に入ったときから、そこにそれがあることは予感していたのかもしれない。
「それ……」
「え?」
「教会の椅子……ですよね」
「あ、香坂さんよくご存知ですね。
イギリスの古い教会の椅子を真似てみたんですけど、
ほら、ここのくりぬきの所、本来は十字架の形だったのをこうして……」
牧野が指し示す背もたれには、木の形のくりぬきがあるのだ。触らなくてもぼくにはその手触りがわかる。それは、ぼくの部屋にある鈴村の椅子と全く同じだったのだから。
「どうして大塚に?」とぼくは聞いてみた。牧野は頭をかいて、「東京ならどこでもよかったんですけど、これも縁ですね」と笑った。昔からずっと自分をサポートしてくれている人がこの土地にいること。その人の提案でアンティークの模倣を始めたこと。それが世間に認められたこと。その人から展示会をする場所も提供されたけれど、そこでは手狭なのが分かってここを探し出したこと。
「ぼくが今日あるのはその人のおかげなんです。その教会の椅子も、その人のアイデアだったんですよ」
そう言って微笑む牧野の顔は眩しかった。悔しいくらいに。
返事は改めてということにして家に帰ったぼくは、自分の部屋のベッドの横に置かれた、鈴村のあの椅子をひっくりかえしてみた。座面の裏には、予想したとおり「Mitsu」というサインがあった。
椅子を元に戻し、ついさっき牧野からもらった名刺を聖書入れのポケットに入れる。
『工房HANA まきの充』と書かれた名刺だ。
「どうして?」と、鈴村に聞きたいことが山ほどある。
どうして彼の椅子がここにある?
どうして彼はぼくの前に現れた?
どうして彼のことを黙っていた?
彼は、かつて鈴村が話してくれた、長野の彼に違いない。記憶の中ではいつでも年下の小学生のガキだったライバルが、いきなりでかくなって目の前に現れたのだ。
そして、牧野が自分の工房に付けているのは鈴村の名前だ。鈴村華子の「HANA」に違いない。だとすれば、牧野にとって鈴村は今でも特別な女性なのではないのか。
ぼくだけがずっと鈴村のそばにいたつもりだった。でも本当は、牧野もずっと彼女のそばにいたということだ。
ぼくはずっと鈴村に支えられてきた。でも、牧野もきっとそうなのだ。
突き上げてくるのは今までに感じたことのない強い嫉妬心だった。
つづく
Copyright(c) since2004 sakurai All rights reserved.