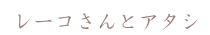
(20)終わり花火
今のところ、アタシの「嫌いな人間リスト」の栄えあるワースト一位に輝いているのはアサコさんだ。アサコさんてのは、ハラッポの引っ越し先に遊びに行って彼女の写真を撮って来たとレーコさんを驚かせたイヤな友だちだ。そのアサコさんが、このくそ暑い夏の、やっと少し涼しくなりかけた夕暮れの静かな時間に、なんとあの、ハラッポを連れて来た。キライ度が上がった。
なんで急にアサコさんが、どうしてハラッポと一緒になわけ? わけわかんなくてアタシは機嫌悪いよ、ごめんなすってよ。
「あんなところで会うなんて夢にも思わないもん。びっくりよ、ねぇ? 原くん」
アサコさんは、はしゃいでいる。「あんなとこ」ってどこだよまったく。どうしてそういうところ、レーコさんは突っ込んで訊かないんだろう。
「お盆だし、さ……」と、ハラッポはまだ脚が半分外に残っているような感じで、部屋に上がってもいいんだろうかと相変わらずはっきりしない。
なにがお盆だからなんだかアタシにはわかんないけど、「そうよね……」と言うレーコさんの脇をすり抜けて、アサコさんはずんずん部屋の奥へやってくる。
「レーコのことびっくりさせようと思ってさ、無理やり原くんを引っ張って来ちゃった。どう? びっくりした?」
「うん、びっくりした」
びっくりしたっていうか、レーコさん、蒼くなってるような気がするけど?
「でも原くんの実家ってあっちでしょ? なんでお墓参りがこっちなの?」
あっちとかこっちとかアサコさんが言うから、アタシにはぴーんと来た。ハラッポ、ひとりでこっちに来たんじゃないんだね。こっちの人のお墓参りに同行したんだね。みぃちゃんだね。
ハラッポはなんと答えようか迷ってる。アサコさんはハラッポの答えなど待たずに続ける。
「ほんとに久しぶりだよね。ほら、わたしとキダくんのふたりで、いきなり原くんのとこお邪魔したのはいつだっけ。
ねぇ、レーコは原くんと会うの、いつ以来?」
「え?」
ふたりは顔を見合わせて考えるのかと思ったら、互いにあらぬ方向を見た。ばればれじゃん。
それを見てアサコさんは、「やっぱりなにかあるのねぇ」という顔。いやだねぇ。
ちょうどその時チャイムが鳴った。勝手にドアを開けてにぎやかな声が聞こえてくる。千客万来? 今日はまったく、どうしたっていうんだろう。
「おねえちゃーん、可愛い妹が来てやったよー。びっくりする人も連れてきたよ」
ほらまた「びっくり」だ。しかも、
「よ、レーコ」って、重そうなコンビニの袋を下げて入ってきたのは、あのオトコじゃないか。アタシが祭礼でレーコさんにすくって貰ったときに、レーコさんと一緒だったあのオトコだ。その後ろには妹の温子さんとその彼氏がいる。アサコさんは、「紹介してよ」とレーコさんの肘をつつく。
「えっと、わたしの妹の温子と、温子の彼氏とその先輩、バンドやってるのよ。こっちは原くんと……」
「アサコです!」
うわ。アサコさんの目線はしっかりあのオトコを押さえてる。
「ども……八木です」
おおー、八木っていうんだ。初めて知った。知らなくてもよかったけど。
「どうしたのよアッコ、急に来るなんて」
「今日ね、シリウスってライブハウスのオーディションがあったのよ。そのあと、花火大会に行く予定だったんだけど、その花火ならおねえちゃんとこからよく見えるって、八木さんが言うからさぁ……」
「花火、今日だったんだ……知らなかった」
「そんなにここからよく見えるんですか?」
どうして知ってるんですか? と言わんばかりにアサコさんが八木を見上げて訊く。
「いやぁ、よく見えるのなんのって。まぁ、もう少ししたら分かるから期待しててよ」と、ヤギもなれなれしい。それからアタシを見つけて、「あ、おまえ、まだ生きてんのか? しぶといなぁ!」って、テンション高すぎるし。
そんな中、ハラッポは背中から玄関の方へ後ずさりながらレーコさんを手招きしていた。
「急に来てごめん……。俺、もう行くから……」
「うん……」
「花火が見えるなんて、知らなかったな」
「ああ、うん、そうだったね……」
「なぁなぁ、レーコ、あれどうした? ほら、折り畳みのなんかこう、テーブルみたいのあったじゃないか」
ヤギヤギが長い髪を手拭いでまとめながら、レーコさんとハラッポのところに首をつっこんだ。大掃除でもするみたいに張り切っている。
「あれー? 帰っちゃうんですかぁ?」と、温子さんの彼氏も顔を出し、「いいじゃないですか、一緒に花火見て、呑みましょうよ。ほらほら、お姉さんと一緒にほら」と、靴を履きかけていたハラッポの肩の辺りを掴んで引っぱる。
「ちょ……ちょっと! なんなんですか」と、さすがのハラッポも声を上げたね。その声に温子さんが飛んできて、「ごめんなさい。今日の演奏があんまりうまくいったから嬉しくて、それで、先輩もケータも飲んじゃってるし調子のっちゃってて……」 すると今度はけたたましくヤギの携帯が鳴り出した。ヤギヤギは着信画面を見て手ぬぐいをむしるように外しながら、「え? これからですか? いや、大丈夫です。ありがとうございます。行きます。すぐ行きます」と、大声でしゃべり終わるや馬鹿に勢いよく携帯を閉じちゃって、「おい、ケータ、マネージャーが打ち合わせしたいってさ、俺ら、オーディションに通ったぞ。これからシリウスに戻るぞ!」「本当っすか?」と、高い声。「やったね、けーちゃん。じゃあね、おねえちゃん、また来るからっ!」
う、る、せぇー。
大騒ぎで三人が脱いだばかりの靴を競うようにつっかけて出ていこうとすると、アサコさんまで「待って! わたしもその店を知りたいから連れていって」と慌て出し、レーコさんには「あとはよろしく」と意味深に笑いおいて、みんなを追いかけるようにして出ていってしまった。
あーあー、アタシは目が回りそうだよ。
そうして結局、廊下の壁に貼り付くようにして立っていたハラッポとレーコさん、残された。
まるで嵐が通り過ぎていった後みたいだ。
「なんだったの? って感じだな」
「ごめんね、お騒がせで」
「いや、おかげで俺のお騒がせ度が薄まった。……ような気がする」
部屋のテーブルの上にはコンビニの袋がどんと乗って崩れていて、缶ビールが一つ二つ、転がり出ている。
「八木って人、レーコさんの、前の……?」
「昔のね。今でもたまには会うけど、もう全然そういうんじゃないよ……って、別に言い訳する必要もないか」
「あの人、俺の知らないレーコさんをたくさん知っている気がした」
気がするばっかりだね、ハラッポ。
「そういうふうに見せたがる人なのよ、あの人は」
「そっか……。あ、始まったな、花火」
「見ていく?」
「いいの?」
「うん」
もうアタシには花火の音しか聞こえない。
テーブルの飲み物や食べ物には目もくれないで、ふたりはベランダの手すりにもたれるようにして花火を見ていた。「わぁー」でもなければもちろん「たまやー」でもなく、ただ、淡々と見ていた。
アタシには見えないけど、花火の音ってもの悲しい。なにかがどんどん、終わっていく感じがする。
終わったと思うと、思わせぶりな間隔をおいてまた鳴る。がっかりしたり、ほっとしたり。いつかは「最後の一発」になるのが分かっているから、次か、次かとどきどきする。でも、そのうちに少しずつ慣れてきて、もうこれで最後でもいいやって、思えてくるんだ。次から次を待つのも疲れるし。
どうせいつかは終わるんだ。いつまでも夜じゃない。朝が来れば忘れてしまうこと……。
「ね、今ので終わりだと思う?」
「時間的にも、そうじゃないかな……」
「お、わ、りって、出たらいいのにね」
「ENDとか、 FINとか?」
「そうしたらわかりやすい」
先に部屋に戻ろうとしたのはレーコさんだった。ハラッポはもう一度夜空を見て、それから、少し視線を下げた。
「ほら、まだやってるよ。下の方で」
「見えないでしょ、ここからじゃ」
仕掛け花火じゃ音も聞こえない。
「でも明るい……。ねぇ、レーコさん」
「なに?」
「俺、今でも好きだよ」
レーコさんは部屋の入り口で立ち止まっている。サンダル片方脱いだまま。
「だからなに? とか言わないで欲しいんだけど、俺は……」
「だからなに?」
「やっぱりかよ」
定石だね。
「でもそれなら、わたしだって同じだよ……」
その時、
嘘みたいにまた、たくさんの花火が上がった。
びっくりして空を見上げるふたりの距離は、さっきよりもちょっとだけ近く見える。
そう言えば祭礼のある日や運動会の朝も、花火の音がするんだよなってアタシは思い出した。あれはいつも、これから楽しいことが始まることを約束する花火なんだ。
「終わり」を知らせる花火なんかいらないよ。
なんで急にアサコさんが、どうしてハラッポと一緒になわけ? わけわかんなくてアタシは機嫌悪いよ、ごめんなすってよ。
「あんなところで会うなんて夢にも思わないもん。びっくりよ、ねぇ? 原くん」
アサコさんは、はしゃいでいる。「あんなとこ」ってどこだよまったく。どうしてそういうところ、レーコさんは突っ込んで訊かないんだろう。
「お盆だし、さ……」と、ハラッポはまだ脚が半分外に残っているような感じで、部屋に上がってもいいんだろうかと相変わらずはっきりしない。
なにがお盆だからなんだかアタシにはわかんないけど、「そうよね……」と言うレーコさんの脇をすり抜けて、アサコさんはずんずん部屋の奥へやってくる。
「レーコのことびっくりさせようと思ってさ、無理やり原くんを引っ張って来ちゃった。どう? びっくりした?」
「うん、びっくりした」
びっくりしたっていうか、レーコさん、蒼くなってるような気がするけど?
「でも原くんの実家ってあっちでしょ? なんでお墓参りがこっちなの?」
あっちとかこっちとかアサコさんが言うから、アタシにはぴーんと来た。ハラッポ、ひとりでこっちに来たんじゃないんだね。こっちの人のお墓参りに同行したんだね。みぃちゃんだね。
ハラッポはなんと答えようか迷ってる。アサコさんはハラッポの答えなど待たずに続ける。
「ほんとに久しぶりだよね。ほら、わたしとキダくんのふたりで、いきなり原くんのとこお邪魔したのはいつだっけ。
ねぇ、レーコは原くんと会うの、いつ以来?」
「え?」
ふたりは顔を見合わせて考えるのかと思ったら、互いにあらぬ方向を見た。ばればれじゃん。
それを見てアサコさんは、「やっぱりなにかあるのねぇ」という顔。いやだねぇ。
ちょうどその時チャイムが鳴った。勝手にドアを開けてにぎやかな声が聞こえてくる。千客万来? 今日はまったく、どうしたっていうんだろう。
「おねえちゃーん、可愛い妹が来てやったよー。びっくりする人も連れてきたよ」
ほらまた「びっくり」だ。しかも、
「よ、レーコ」って、重そうなコンビニの袋を下げて入ってきたのは、あのオトコじゃないか。アタシが祭礼でレーコさんにすくって貰ったときに、レーコさんと一緒だったあのオトコだ。その後ろには妹の温子さんとその彼氏がいる。アサコさんは、「紹介してよ」とレーコさんの肘をつつく。
「えっと、わたしの妹の温子と、温子の彼氏とその先輩、バンドやってるのよ。こっちは原くんと……」
「アサコです!」
うわ。アサコさんの目線はしっかりあのオトコを押さえてる。
「ども……八木です」
おおー、八木っていうんだ。初めて知った。知らなくてもよかったけど。
「どうしたのよアッコ、急に来るなんて」
「今日ね、シリウスってライブハウスのオーディションがあったのよ。そのあと、花火大会に行く予定だったんだけど、その花火ならおねえちゃんとこからよく見えるって、八木さんが言うからさぁ……」
「花火、今日だったんだ……知らなかった」
「そんなにここからよく見えるんですか?」
どうして知ってるんですか? と言わんばかりにアサコさんが八木を見上げて訊く。
「いやぁ、よく見えるのなんのって。まぁ、もう少ししたら分かるから期待しててよ」と、ヤギもなれなれしい。それからアタシを見つけて、「あ、おまえ、まだ生きてんのか? しぶといなぁ!」って、テンション高すぎるし。
そんな中、ハラッポは背中から玄関の方へ後ずさりながらレーコさんを手招きしていた。
「急に来てごめん……。俺、もう行くから……」
「うん……」
「花火が見えるなんて、知らなかったな」
「ああ、うん、そうだったね……」
「なぁなぁ、レーコ、あれどうした? ほら、折り畳みのなんかこう、テーブルみたいのあったじゃないか」
ヤギヤギが長い髪を手拭いでまとめながら、レーコさんとハラッポのところに首をつっこんだ。大掃除でもするみたいに張り切っている。
「あれー? 帰っちゃうんですかぁ?」と、温子さんの彼氏も顔を出し、「いいじゃないですか、一緒に花火見て、呑みましょうよ。ほらほら、お姉さんと一緒にほら」と、靴を履きかけていたハラッポの肩の辺りを掴んで引っぱる。
「ちょ……ちょっと! なんなんですか」と、さすがのハラッポも声を上げたね。その声に温子さんが飛んできて、「ごめんなさい。今日の演奏があんまりうまくいったから嬉しくて、それで、先輩もケータも飲んじゃってるし調子のっちゃってて……」 すると今度はけたたましくヤギの携帯が鳴り出した。ヤギヤギは着信画面を見て手ぬぐいをむしるように外しながら、「え? これからですか? いや、大丈夫です。ありがとうございます。行きます。すぐ行きます」と、大声でしゃべり終わるや馬鹿に勢いよく携帯を閉じちゃって、「おい、ケータ、マネージャーが打ち合わせしたいってさ、俺ら、オーディションに通ったぞ。これからシリウスに戻るぞ!」「本当っすか?」と、高い声。「やったね、けーちゃん。じゃあね、おねえちゃん、また来るからっ!」
う、る、せぇー。
大騒ぎで三人が脱いだばかりの靴を競うようにつっかけて出ていこうとすると、アサコさんまで「待って! わたしもその店を知りたいから連れていって」と慌て出し、レーコさんには「あとはよろしく」と意味深に笑いおいて、みんなを追いかけるようにして出ていってしまった。
あーあー、アタシは目が回りそうだよ。
そうして結局、廊下の壁に貼り付くようにして立っていたハラッポとレーコさん、残された。
まるで嵐が通り過ぎていった後みたいだ。
「なんだったの? って感じだな」
「ごめんね、お騒がせで」
「いや、おかげで俺のお騒がせ度が薄まった。……ような気がする」
部屋のテーブルの上にはコンビニの袋がどんと乗って崩れていて、缶ビールが一つ二つ、転がり出ている。
「八木って人、レーコさんの、前の……?」
「昔のね。今でもたまには会うけど、もう全然そういうんじゃないよ……って、別に言い訳する必要もないか」
「あの人、俺の知らないレーコさんをたくさん知っている気がした」
気がするばっかりだね、ハラッポ。
「そういうふうに見せたがる人なのよ、あの人は」
「そっか……。あ、始まったな、花火」
「見ていく?」
「いいの?」
「うん」
もうアタシには花火の音しか聞こえない。
テーブルの飲み物や食べ物には目もくれないで、ふたりはベランダの手すりにもたれるようにして花火を見ていた。「わぁー」でもなければもちろん「たまやー」でもなく、ただ、淡々と見ていた。
アタシには見えないけど、花火の音ってもの悲しい。なにかがどんどん、終わっていく感じがする。
終わったと思うと、思わせぶりな間隔をおいてまた鳴る。がっかりしたり、ほっとしたり。いつかは「最後の一発」になるのが分かっているから、次か、次かとどきどきする。でも、そのうちに少しずつ慣れてきて、もうこれで最後でもいいやって、思えてくるんだ。次から次を待つのも疲れるし。
どうせいつかは終わるんだ。いつまでも夜じゃない。朝が来れば忘れてしまうこと……。
「ね、今ので終わりだと思う?」
「時間的にも、そうじゃないかな……」
「お、わ、りって、出たらいいのにね」
「ENDとか、 FINとか?」
「そうしたらわかりやすい」
先に部屋に戻ろうとしたのはレーコさんだった。ハラッポはもう一度夜空を見て、それから、少し視線を下げた。
「ほら、まだやってるよ。下の方で」
「見えないでしょ、ここからじゃ」
仕掛け花火じゃ音も聞こえない。
「でも明るい……。ねぇ、レーコさん」
「なに?」
「俺、今でも好きだよ」
レーコさんは部屋の入り口で立ち止まっている。サンダル片方脱いだまま。
「だからなに? とか言わないで欲しいんだけど、俺は……」
「だからなに?」
「やっぱりかよ」
定石だね。
「でもそれなら、わたしだって同じだよ……」
その時、
嘘みたいにまた、たくさんの花火が上がった。
びっくりして空を見上げるふたりの距離は、さっきよりもちょっとだけ近く見える。
そう言えば祭礼のある日や運動会の朝も、花火の音がするんだよなってアタシは思い出した。あれはいつも、これから楽しいことが始まることを約束する花火なんだ。
「終わり」を知らせる花火なんかいらないよ。
Copyright(c) 2004 sakurai All rights reserved.

