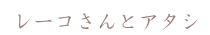
(26)最後の一片
「お姉ちゃん、こういうの得意でしょ?」
レーコさんの妹の温子さん(あっちゃん)が、来るなりジグソーパズルの箱を傾け、ざさっとテーブルの上にピースを広げた。
「どうしたの? これ」
「ケータにもらったんだ」
そう言いながら、麻雀パイみたいにピースをかきまわすから、小さなテーブルから今にもこぼれ落ちそうだ。
「ちょっと、そんなに全部広げちゃってどうするのよ」
「ケータが遠征から帰ってくるまでに仕上げておくって約束したんだもん」
ケータたちは、遠くまでバンドの出稼ぎ演奏に行っているらしい。
「あっちゃんがこういうの苦手なこと、彼は知らないの?」
「知ってるよ。ケータも苦手だし」
えー? それならどうしてジグソーパズルなんか……。
「でもこれ、ケータの大好きな景色なんだ。だからお姉ちゃん、よろしくね」
いつものように、あっちゃんは調子がいい。
箱には夕暮れの厳島神社の写真がある。パチンコの景品かなんかで取ったのかもしれないけど、もしかしたらケータの実家は広島の方なんだね。
「なんでわたしが……」
そう言いながら、レーコさんはあっちゃんが広げたピースを箱に戻している。ただ戻すんじゃなく、箱と蓋の方、ふたつに分けている。
「たまにはこういうのもいいでしょ? お姉ちゃんデートもなくて暇そうだし」
「うるさいわね。それよりほら、こっちの箱から、平らな辺のあるピースを見つけて。それが回りのピースだから」
「えー、めんどくさいよ」
「そんなこと言うなら、やらないよ?」
「もぅー。そうやってカレシのことも脅迫するんでしょ。そんなこと言うなら別れるよ、とか」
あっちゃんはそう言って箱の中を指先でかき回すけど、ちっとも探しているようには見えない。
レーコさんも期待はしていないみたいだ。自分で探し出したピースを並べて、少しずつ枠になる部分を作っている。
「ねぇ、お姉ちゃんの今のカレシって、こないだの人?」
「こないだって?」
こないだって?
「ほら、お店にケータたちの演奏を観に来てくれたじゃない? あのとき、隣に座ってた背の高い人」
「ああ、藤野くんなら、高校の時の同級生よ」
「そっかぁ! わたし、どこかで見たことある顔だなぁって思ったんだ。お姉ちゃんとこの学園祭だったのかも…」
「そんな昔のこと、よく覚えてるわねぇ」
「かっこよくて目立ってたもん。今はちょっと時代遅れな感じだけどさ」
「時代遅れねぇ…」
レーコさん、思わず吹き出した。
ひどーい、藤野のどこが時代遅れってなんだよー。
「なんだ、やっぱりただの友だちなんだ。八木さんの言う通りだったんだな」
え? ヤギヤギが何を知ってるのさ。
「あの人がなにを言ってたの?」
「あれは恋人じゃないでしょって。お姉ちゃんの顔、見てたら分かるんだってさ」
ヤギヤギのそういう知ったかぶりなところがアタシは気に入らないね。たぶんレーコさんも「ふん」と思ったんじゃないかな。
「じゃあ、本命は花火の時の人?」
ハラッポのことだ。
「あの人は、もっと関係ないよ」
「どうして?」
「どうしても」
------
どうしても? で、アタシは思い出した。こないだのこと……
「どうしても?」
「いや、どうしてもってわけじゃないけど、できれば」
ハラッポがそう言って箸を置いたとき、アタシはなにかの音を聞いた。箸を置く音よりもずっとかすかな、むしろ、なんの音よりも音のない音…。
「うん、わかった。なんかわたし、勘違いしていたかも」
レーコさんの顔色がすーっと白くなっていくのがアタシにもわかった。そんなレーコさんを見たらハラッポ、「ごめん」とか言うだろうと思った。アタシが思ったんだからレーコさんだってそう思っていただろう。でも、その日のハラッポはそれ以上何も言わないで立ち上がると、「じゃ、また今度…」ってあっさりと帰って行ったんだ。
引っ越して一度は遠のいたのに、その頃はまた、ハラッポがここに顔を出すようになっていた。おかげでアタシは藤野に会う機会もなかったくらいだ。
「みぃのお母さんのお見舞いのついで」らしかった。
みぃのお母さんがぎっくり腰で倒れて美容院の仕事ができなくて、それで「みぃがずっとこっちで手伝っている」「もしかしたらみぃだけまた、東京に戻るかも」と、ハラッポは話していた。
レーコさんは「大変だね」と答え、アタシは「ふーん」と思っていた。「あっちでひとりになっちゃうなら、わたしが行ってあげようか」とレーコさんが言えば、「来てくれないくせに」とハラッポがむくれて、それでふたりで笑っていた。
ハラッポとみぃ、ハラッポとレーコさん、どういう関係なのかアタシには全然わかんない。
金曜日の夜にレーコさんのとこに来て、土曜日に「お見舞い」に行って、日曜の夜にもう一度レーコさんのところに寄って帰るというパターンが何回くらい続いいただろう。気がつくとそれが、日曜の夜、帰る前にちょっと寄るだけになっていた。その代わり、レーコさんは夕飯の用意をして待っていた。
「レーコさんの手料理を食べないと帰れないよ」と、ハラッポは言っていた。「夕飯は食べてきたけど、レーコさんのは別腹」と言うこともあった。日曜の遅くにやってきて、慌ただしくご飯を食べて帰ったりする日もあった。明日の朝食べるからと、残りをタッパーに詰めて貰ったりもしていた。
ほんのついこの間までそんなふうだった。
でもあの日、突然(とアタシは思った)、ハラッポは言ったんだ。
「夕飯は向こう(みぃの実家だね)で食べてくるから、ぼくの分は用意しないで欲しい」って。それでレーコさん「うん、わかった」って青白くなった。
だって、そんなこと最初から分かっていたよ? なんで今更それが理由になるんだろう。
釈然としないまま日は過ぎて、日曜日の夜になるとレーコさんはハラッポに電話する。「今日、来る?」って。
以前ならそれは、「来てもいいよ」というレーコさんからの合図だったのに、いつの間にか、「来られますかどうですか?」という、お伺いのようになっている。もちろん言われた通り、夕飯の支度なんかしない。ひとりだけの夕食をそそくさとお腹に収めてハラッポを待つ日曜日だ。
ちがう。
レーコさんは金曜日から待ってるんだ。最初の頃のように。
外にバイクの音がするたび、はっとするんだ。
そんなレーコさんをアタシは正直言って好きになれなくて、なんだかいらいらして、週末が来るたびにアタシのちっちゃな胃袋が痛くなる。なんであんな勝手なヤツに振り回されるんだよ。ああ、こんな時には藤野が来てくれればいいのになぁと思う。
でもでも、今日はあっちゃんがいる! 誰もいないよりましだ。
「ねぇ、お姉ちゃん、これさ、最後の一個はわたしに入れさせてね」
「いいよ」
「え? いいの? 最後の最後の一つだよ? そのピースを入れて、おわったぁー! っていう達成感はいらないの?」
「なによ、自分で言い出しておいて…」
レーコさんは適当な一片をあっちゃんに渡して、「それ、持っていていいよ」と言った。「あっちゃんのなんだし」と。
あっちゃんはその一片をしげしげと眺めてから、無造作にジーンズのポケットに入れた。それがなければ完成しない、大切な一片を……。
「そのかわり、来週も来て手伝ってね。今日中になんかできないから」
「えー? 来週はケータも帰って来るしぃ…」
「一緒に来ればいいじゃない?」
「ほんと? 八木さんも一緒でもいい?」
う、なんでヤギヤギも一緒なんだ?!
「あの人連れてきて、何か企んでるんじゃないでしょうね」
「企んでるわけじゃないけど、八木さんならお姉ちゃんに太刀打ちできるじゃない。太刀打ちできるっていうか、打たれ強いっていうか、図太いっていうか…」
「がさつというか、鈍感というか?」
ひどい言われ方だね、ヤギヤギ。間違ってないけど。
「お姉ちゃんには八木さんみたいな人が合ってると思うよ、結局」
やだやだやだー。
「お姉ちゃんはね、繊細な人とつきあうのは止めた方がいいんだよ。傷つけるし、疲れさせるし、お互いにそうなったら続かないんだから、きっと」
「なんか…」
レーコさん、手を止めてあっちゃんの顔をまじまじと見て言った。
「なんかちょっと、腹がたってきたな」
「本当のことだからでしょ?」
おおー、結構するどかったんだな、あっちゃん。
「やっぱり八木さんの言う通りだ。 お姉ちゃんて案外、分かりやすいね」
レーコさんは怒って作りかけのパズルをひっくり返すふりをした。もちろん、ふりだけだった。ほんの途中まででも作り上げて来たものを自分からぶち壊すなんてたぶん出来ない。
それからは無駄話もせず、途中であっちゃんが中華まんを買いに行ったり、コーヒーを淹れたり、テレビを観たり、雑誌をめくったり、時々気まぐれにピースを探してみたりとひとりで勝手に過ごす横で、レーコさんは厳島神社の赤い鳥居を形作っていった。
アタシの赤に似た赤だ。その立派な鳥居の下を泳ぐことを気持よく想像していたら、「知ってる? 干潮の時はその鳥居の下、水が無くなって歩いて通れるんだよ」なんてあっちゃんが言うからぞっとした。
レーコさんはともかく、ヤギヤギとハラッポと藤野、アタシを一番大事にしてくれるのは誰だろうな。
アタシが好きなのは藤野なんだけど、でも、レーコさんの次だ。
だって、 生きていくのに必要なのは水と、毎日ちゃんと食べ物をくれる人なんだよ。
藤野がアタシをお腹いっぱいにしてくれたことはまだ一回もない。あまり話しかけてもくれない。それを考えると淋しくなるな。
その夜、バイクの音はしなかった。 誰からの電話も鳴らない週末だった。
レーコさんの妹の温子さん(あっちゃん)が、来るなりジグソーパズルの箱を傾け、ざさっとテーブルの上にピースを広げた。
「どうしたの? これ」
「ケータにもらったんだ」
そう言いながら、麻雀パイみたいにピースをかきまわすから、小さなテーブルから今にもこぼれ落ちそうだ。
「ちょっと、そんなに全部広げちゃってどうするのよ」
「ケータが遠征から帰ってくるまでに仕上げておくって約束したんだもん」
ケータたちは、遠くまでバンドの出稼ぎ演奏に行っているらしい。
「あっちゃんがこういうの苦手なこと、彼は知らないの?」
「知ってるよ。ケータも苦手だし」
えー? それならどうしてジグソーパズルなんか……。
「でもこれ、ケータの大好きな景色なんだ。だからお姉ちゃん、よろしくね」
いつものように、あっちゃんは調子がいい。
箱には夕暮れの厳島神社の写真がある。パチンコの景品かなんかで取ったのかもしれないけど、もしかしたらケータの実家は広島の方なんだね。
「なんでわたしが……」
そう言いながら、レーコさんはあっちゃんが広げたピースを箱に戻している。ただ戻すんじゃなく、箱と蓋の方、ふたつに分けている。
「たまにはこういうのもいいでしょ? お姉ちゃんデートもなくて暇そうだし」
「うるさいわね。それよりほら、こっちの箱から、平らな辺のあるピースを見つけて。それが回りのピースだから」
「えー、めんどくさいよ」
「そんなこと言うなら、やらないよ?」
「もぅー。そうやってカレシのことも脅迫するんでしょ。そんなこと言うなら別れるよ、とか」
あっちゃんはそう言って箱の中を指先でかき回すけど、ちっとも探しているようには見えない。
レーコさんも期待はしていないみたいだ。自分で探し出したピースを並べて、少しずつ枠になる部分を作っている。
「ねぇ、お姉ちゃんの今のカレシって、こないだの人?」
「こないだって?」
こないだって?
「ほら、お店にケータたちの演奏を観に来てくれたじゃない? あのとき、隣に座ってた背の高い人」
「ああ、藤野くんなら、高校の時の同級生よ」
「そっかぁ! わたし、どこかで見たことある顔だなぁって思ったんだ。お姉ちゃんとこの学園祭だったのかも…」
「そんな昔のこと、よく覚えてるわねぇ」
「かっこよくて目立ってたもん。今はちょっと時代遅れな感じだけどさ」
「時代遅れねぇ…」
レーコさん、思わず吹き出した。
ひどーい、藤野のどこが時代遅れってなんだよー。
「なんだ、やっぱりただの友だちなんだ。八木さんの言う通りだったんだな」
え? ヤギヤギが何を知ってるのさ。
「あの人がなにを言ってたの?」
「あれは恋人じゃないでしょって。お姉ちゃんの顔、見てたら分かるんだってさ」
ヤギヤギのそういう知ったかぶりなところがアタシは気に入らないね。たぶんレーコさんも「ふん」と思ったんじゃないかな。
「じゃあ、本命は花火の時の人?」
ハラッポのことだ。
「あの人は、もっと関係ないよ」
「どうして?」
「どうしても」
------
どうしても? で、アタシは思い出した。こないだのこと……
「どうしても?」
「いや、どうしてもってわけじゃないけど、できれば」
ハラッポがそう言って箸を置いたとき、アタシはなにかの音を聞いた。箸を置く音よりもずっとかすかな、むしろ、なんの音よりも音のない音…。
「うん、わかった。なんかわたし、勘違いしていたかも」
レーコさんの顔色がすーっと白くなっていくのがアタシにもわかった。そんなレーコさんを見たらハラッポ、「ごめん」とか言うだろうと思った。アタシが思ったんだからレーコさんだってそう思っていただろう。でも、その日のハラッポはそれ以上何も言わないで立ち上がると、「じゃ、また今度…」ってあっさりと帰って行ったんだ。
引っ越して一度は遠のいたのに、その頃はまた、ハラッポがここに顔を出すようになっていた。おかげでアタシは藤野に会う機会もなかったくらいだ。
「みぃのお母さんのお見舞いのついで」らしかった。
みぃのお母さんがぎっくり腰で倒れて美容院の仕事ができなくて、それで「みぃがずっとこっちで手伝っている」「もしかしたらみぃだけまた、東京に戻るかも」と、ハラッポは話していた。
レーコさんは「大変だね」と答え、アタシは「ふーん」と思っていた。「あっちでひとりになっちゃうなら、わたしが行ってあげようか」とレーコさんが言えば、「来てくれないくせに」とハラッポがむくれて、それでふたりで笑っていた。
ハラッポとみぃ、ハラッポとレーコさん、どういう関係なのかアタシには全然わかんない。
金曜日の夜にレーコさんのとこに来て、土曜日に「お見舞い」に行って、日曜の夜にもう一度レーコさんのところに寄って帰るというパターンが何回くらい続いいただろう。気がつくとそれが、日曜の夜、帰る前にちょっと寄るだけになっていた。その代わり、レーコさんは夕飯の用意をして待っていた。
「レーコさんの手料理を食べないと帰れないよ」と、ハラッポは言っていた。「夕飯は食べてきたけど、レーコさんのは別腹」と言うこともあった。日曜の遅くにやってきて、慌ただしくご飯を食べて帰ったりする日もあった。明日の朝食べるからと、残りをタッパーに詰めて貰ったりもしていた。
ほんのついこの間までそんなふうだった。
でもあの日、突然(とアタシは思った)、ハラッポは言ったんだ。
「夕飯は向こう(みぃの実家だね)で食べてくるから、ぼくの分は用意しないで欲しい」って。それでレーコさん「うん、わかった」って青白くなった。
だって、そんなこと最初から分かっていたよ? なんで今更それが理由になるんだろう。
釈然としないまま日は過ぎて、日曜日の夜になるとレーコさんはハラッポに電話する。「今日、来る?」って。
以前ならそれは、「来てもいいよ」というレーコさんからの合図だったのに、いつの間にか、「来られますかどうですか?」という、お伺いのようになっている。もちろん言われた通り、夕飯の支度なんかしない。ひとりだけの夕食をそそくさとお腹に収めてハラッポを待つ日曜日だ。
ちがう。
レーコさんは金曜日から待ってるんだ。最初の頃のように。
外にバイクの音がするたび、はっとするんだ。
そんなレーコさんをアタシは正直言って好きになれなくて、なんだかいらいらして、週末が来るたびにアタシのちっちゃな胃袋が痛くなる。なんであんな勝手なヤツに振り回されるんだよ。ああ、こんな時には藤野が来てくれればいいのになぁと思う。
でもでも、今日はあっちゃんがいる! 誰もいないよりましだ。
「ねぇ、お姉ちゃん、これさ、最後の一個はわたしに入れさせてね」
「いいよ」
「え? いいの? 最後の最後の一つだよ? そのピースを入れて、おわったぁー! っていう達成感はいらないの?」
「なによ、自分で言い出しておいて…」
レーコさんは適当な一片をあっちゃんに渡して、「それ、持っていていいよ」と言った。「あっちゃんのなんだし」と。
あっちゃんはその一片をしげしげと眺めてから、無造作にジーンズのポケットに入れた。それがなければ完成しない、大切な一片を……。
「そのかわり、来週も来て手伝ってね。今日中になんかできないから」
「えー? 来週はケータも帰って来るしぃ…」
「一緒に来ればいいじゃない?」
「ほんと? 八木さんも一緒でもいい?」
う、なんでヤギヤギも一緒なんだ?!
「あの人連れてきて、何か企んでるんじゃないでしょうね」
「企んでるわけじゃないけど、八木さんならお姉ちゃんに太刀打ちできるじゃない。太刀打ちできるっていうか、打たれ強いっていうか、図太いっていうか…」
「がさつというか、鈍感というか?」
ひどい言われ方だね、ヤギヤギ。間違ってないけど。
「お姉ちゃんには八木さんみたいな人が合ってると思うよ、結局」
やだやだやだー。
「お姉ちゃんはね、繊細な人とつきあうのは止めた方がいいんだよ。傷つけるし、疲れさせるし、お互いにそうなったら続かないんだから、きっと」
「なんか…」
レーコさん、手を止めてあっちゃんの顔をまじまじと見て言った。
「なんかちょっと、腹がたってきたな」
「本当のことだからでしょ?」
おおー、結構するどかったんだな、あっちゃん。
「やっぱり八木さんの言う通りだ。 お姉ちゃんて案外、分かりやすいね」
レーコさんは怒って作りかけのパズルをひっくり返すふりをした。もちろん、ふりだけだった。ほんの途中まででも作り上げて来たものを自分からぶち壊すなんてたぶん出来ない。
それからは無駄話もせず、途中であっちゃんが中華まんを買いに行ったり、コーヒーを淹れたり、テレビを観たり、雑誌をめくったり、時々気まぐれにピースを探してみたりとひとりで勝手に過ごす横で、レーコさんは厳島神社の赤い鳥居を形作っていった。
アタシの赤に似た赤だ。その立派な鳥居の下を泳ぐことを気持よく想像していたら、「知ってる? 干潮の時はその鳥居の下、水が無くなって歩いて通れるんだよ」なんてあっちゃんが言うからぞっとした。
レーコさんはともかく、ヤギヤギとハラッポと藤野、アタシを一番大事にしてくれるのは誰だろうな。
アタシが好きなのは藤野なんだけど、でも、レーコさんの次だ。
だって、 生きていくのに必要なのは水と、毎日ちゃんと食べ物をくれる人なんだよ。
藤野がアタシをお腹いっぱいにしてくれたことはまだ一回もない。あまり話しかけてもくれない。それを考えると淋しくなるな。
その夜、バイクの音はしなかった。 誰からの電話も鳴らない週末だった。
Copyright(c) sakurai All rights reserved.

