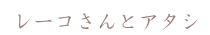
(33)そこにあったカギのこと
いつものように夜が来て、玄関のカギを回す音がする。レーコさんが仕事から帰って来た。
その音が普段よりも乱暴で、靴の脱ぎ方も足音も慌ただしい。どうしたんだろうと思っていたら、壁を叩くような勢いで灯りをつけ、電気ストーブと、滅多に使わないエアコンのスイッチまで入れて、また急いで玄関に戻って行った。
「ほらほら、入って入って。寒かったでしょ?」
レーコさんに背中を押されるようにして来たのは、制服姿の美月だった。
美月はレーコさんの従姉妹の子どもだったよね。
「いつから待ってたの? 電話してくれたらよかったのに」
「でも、携帯の番号、知らなくて、お母さんに訊いても知らないって言われて……。そしたら、おじさんがすぐに来てくれるって言うから、待ってました」
え? おじさんて、誰?
「おじさんて、こないだここで会った人?」
美月がうんうんと頷く。そうか、ヤギヤギのことか。
「あの人に電話したの?」
「メールです」
「メール?」
「このまえ、ここで、おじさんが勝手に登録してくれて、それでときどき……」
「メールのやり取りをしてるんだ」
「はい」
「へぇーぇ」
レーコさんはコートを脱ぎながら、ふっと笑った。中学生とメル友のヤギヤギ、おかしいよね。
「あ、じゃあどうしてあの人、わたしに連絡して来ないんだろ。美月ちゃんが待ってるって分かっていたらもっと急いで帰って来たのに」
「電話、繋がらないって言ってました。番号が変わったんじゃないかって」
「そうか……新しいの、教えてなかったんだ……」
そういえば携帯電話、ダメにしたんだよね。あのとき、番号も変えちゃったんだね。
「そうだ、お夕飯どうする? お腹すいてるでしょ?」
「あ、それなら、お弁当を買って来るから待っとけって、おじさんが」
「ふーん。早苗さんのとこのお弁当かな……」
そのおじさんが来たのはそれからすぐで、背中にギターを背負って、両手に袋を下げて前のめりにやって来た。
「寒いと思ったら雪、降って来たぞ」
「ほんと?」
美月は窓に駆け寄った。
「ねぇ、わたしがまだ帰ってなかったら、外でどうするつもりだったの?」
「部屋で待ったよ。カギ、あるもん」
「え?!」
「おれ、スペアを持ってるじゃん」
「なんで?!」
「なんでってさぁ……」
ヤギヤギはギターを下ろすと広げた指でいつものように頭をぐしゃぐしゃっとしてから、ジーンズの後ろのポケットにあったカギを出してテーブルにコトンと乗せた。なんの飾りも付けていない、ただの銀色のカギそのものだ。
「どうして、あなたが……」
「なんだよ、そんなに青くなることないだろ」
「だって……」
「おまえ、あそこの押し入れん中の小さい引き出しに、体温計なんかと一緒にしまってただろ? それを俺が見つけて、これ持ってていいかって訊いたら、そうしてって、レーコが」
「うそ……」
うそだぁー。そんな無防備なレーコさんあり得なーい。
「覚えてないのかよ。レーコはそんときインフルかなんかで、すごい熱出して寝込んでてさ、たぶん心細いんだろうなって……」
本当にレーコさんは青くなっている。うまく思い出せないみたいだった。
「それで、どうしてそのカギを持ったままなの? 普通、返すでしょ」
別れたんだから、と、レーコさんは美月ちゃんを気にして小さい声で付け足した。
「レーコだって、忘れてたんだろ」
「忘れてたわけじゃ……。ねぇ、それよりそのカギ、使ったことあるの?」
「いや」
「本当?」
「本当だよ。っていうか俺、持ってたことさえ忘れてたんだぜ。このギターケースを整理して、ここんとこのポケットに入ってたのをつい最近、見つけたんだ」
「本当に?」
「嘘じゃねぇよ」
そう言うとヤギヤギは、窓際の美月の隣りに行って「おー、本格的に降って来たじゃん」と窓に貼り付くようにして空を見た。
交代に美月が振り向いて、
「あの……。今日、初めてカギが役にたつって、おじさん言ってたから。だから、使ってたことないの、嘘じゃないと思います」
って、気を遣っちゃってる。
「ごめんごめん、そうじゃないの。ただ、この人が持ってるって思ってなかったから、ちょっと驚いちゃって……。あぁ、ほんとだ、雪、結構降ってるねぇ」
と、とってつけたように言うレーコさんを、ヤギヤギは横目でちらと見る。二人の間に立っていた美月は先に窓を離れて、テーブルの上のお弁当の袋を覗き込んだ。
「美味しそうですね」
「だろ? 一番高いのをふたつ、奮発したからな。お祝いだし」
「お祝い?」
きょとんとするレーコさんに、「高校、決まったんです」と、美月が言った。
「わぁ、そうだったんだ。おめでとう!」
「あんまりアタマいい学校じゃないからお母さんはがっかりしてるんだけど、でも、わたしは行きたかった学校だから……。ありがとうございます」
「行きたいとこに行くのが一番だよな。高校なんかどこだってさ、好きなことを見つけて、それをずっと続ける事ができたら、人生それが一番」
「でも、それがなかなか難しいんだよね……」
「そうか? 俺に出来るんだから、レーコにだって美月にだってできるさ。ってわけで、バンドの練習があるからもう行くよ。またな、美月」
「え? もう行っちゃうんですか?」
と、残念そうに言ったのはもちろん美月。
「またメールする。あ、そうだ、このおばちゃんの番号とアドレスも聞いといて、あとで教えてくれよな。そんじゃまたな、レーコ。カギ、ちゃんとしまっとけよ」
あーあー雪かよ、バイクで来るんじゃなかったなぁ……と、そんな声と一緒にバタンとドアがしまった。
なんだかさ、このごろヤギヤギも藤野も、さっさと帰っちゃうのね。
(この話は、珍しく次に続く)
その音が普段よりも乱暴で、靴の脱ぎ方も足音も慌ただしい。どうしたんだろうと思っていたら、壁を叩くような勢いで灯りをつけ、電気ストーブと、滅多に使わないエアコンのスイッチまで入れて、また急いで玄関に戻って行った。
「ほらほら、入って入って。寒かったでしょ?」
レーコさんに背中を押されるようにして来たのは、制服姿の美月だった。
美月はレーコさんの従姉妹の子どもだったよね。
「いつから待ってたの? 電話してくれたらよかったのに」
「でも、携帯の番号、知らなくて、お母さんに訊いても知らないって言われて……。そしたら、おじさんがすぐに来てくれるって言うから、待ってました」
え? おじさんて、誰?
「おじさんて、こないだここで会った人?」
美月がうんうんと頷く。そうか、ヤギヤギのことか。
「あの人に電話したの?」
「メールです」
「メール?」
「このまえ、ここで、おじさんが勝手に登録してくれて、それでときどき……」
「メールのやり取りをしてるんだ」
「はい」
「へぇーぇ」
レーコさんはコートを脱ぎながら、ふっと笑った。中学生とメル友のヤギヤギ、おかしいよね。
「あ、じゃあどうしてあの人、わたしに連絡して来ないんだろ。美月ちゃんが待ってるって分かっていたらもっと急いで帰って来たのに」
「電話、繋がらないって言ってました。番号が変わったんじゃないかって」
「そうか……新しいの、教えてなかったんだ……」
そういえば携帯電話、ダメにしたんだよね。あのとき、番号も変えちゃったんだね。
「そうだ、お夕飯どうする? お腹すいてるでしょ?」
「あ、それなら、お弁当を買って来るから待っとけって、おじさんが」
「ふーん。早苗さんのとこのお弁当かな……」
そのおじさんが来たのはそれからすぐで、背中にギターを背負って、両手に袋を下げて前のめりにやって来た。
「寒いと思ったら雪、降って来たぞ」
「ほんと?」
美月は窓に駆け寄った。
「ねぇ、わたしがまだ帰ってなかったら、外でどうするつもりだったの?」
「部屋で待ったよ。カギ、あるもん」
「え?!」
「おれ、スペアを持ってるじゃん」
「なんで?!」
「なんでってさぁ……」
ヤギヤギはギターを下ろすと広げた指でいつものように頭をぐしゃぐしゃっとしてから、ジーンズの後ろのポケットにあったカギを出してテーブルにコトンと乗せた。なんの飾りも付けていない、ただの銀色のカギそのものだ。
「どうして、あなたが……」
「なんだよ、そんなに青くなることないだろ」
「だって……」
「おまえ、あそこの押し入れん中の小さい引き出しに、体温計なんかと一緒にしまってただろ? それを俺が見つけて、これ持ってていいかって訊いたら、そうしてって、レーコが」
「うそ……」
うそだぁー。そんな無防備なレーコさんあり得なーい。
「覚えてないのかよ。レーコはそんときインフルかなんかで、すごい熱出して寝込んでてさ、たぶん心細いんだろうなって……」
本当にレーコさんは青くなっている。うまく思い出せないみたいだった。
「それで、どうしてそのカギを持ったままなの? 普通、返すでしょ」
別れたんだから、と、レーコさんは美月ちゃんを気にして小さい声で付け足した。
「レーコだって、忘れてたんだろ」
「忘れてたわけじゃ……。ねぇ、それよりそのカギ、使ったことあるの?」
「いや」
「本当?」
「本当だよ。っていうか俺、持ってたことさえ忘れてたんだぜ。このギターケースを整理して、ここんとこのポケットに入ってたのをつい最近、見つけたんだ」
「本当に?」
「嘘じゃねぇよ」
そう言うとヤギヤギは、窓際の美月の隣りに行って「おー、本格的に降って来たじゃん」と窓に貼り付くようにして空を見た。
交代に美月が振り向いて、
「あの……。今日、初めてカギが役にたつって、おじさん言ってたから。だから、使ってたことないの、嘘じゃないと思います」
って、気を遣っちゃってる。
「ごめんごめん、そうじゃないの。ただ、この人が持ってるって思ってなかったから、ちょっと驚いちゃって……。あぁ、ほんとだ、雪、結構降ってるねぇ」
と、とってつけたように言うレーコさんを、ヤギヤギは横目でちらと見る。二人の間に立っていた美月は先に窓を離れて、テーブルの上のお弁当の袋を覗き込んだ。
「美味しそうですね」
「だろ? 一番高いのをふたつ、奮発したからな。お祝いだし」
「お祝い?」
きょとんとするレーコさんに、「高校、決まったんです」と、美月が言った。
「わぁ、そうだったんだ。おめでとう!」
「あんまりアタマいい学校じゃないからお母さんはがっかりしてるんだけど、でも、わたしは行きたかった学校だから……。ありがとうございます」
「行きたいとこに行くのが一番だよな。高校なんかどこだってさ、好きなことを見つけて、それをずっと続ける事ができたら、人生それが一番」
「でも、それがなかなか難しいんだよね……」
「そうか? 俺に出来るんだから、レーコにだって美月にだってできるさ。ってわけで、バンドの練習があるからもう行くよ。またな、美月」
「え? もう行っちゃうんですか?」
と、残念そうに言ったのはもちろん美月。
「またメールする。あ、そうだ、このおばちゃんの番号とアドレスも聞いといて、あとで教えてくれよな。そんじゃまたな、レーコ。カギ、ちゃんとしまっとけよ」
あーあー雪かよ、バイクで来るんじゃなかったなぁ……と、そんな声と一緒にバタンとドアがしまった。
なんだかさ、このごろヤギヤギも藤野も、さっさと帰っちゃうのね。
(この話は、珍しく次に続く)
Copyright(c) sakurai All rights reserved.

