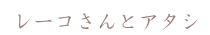
番外編4 不機嫌な姉とアンディの引っ越し(温子さん語る)
久しぶりに車を運転する姉は、大きな交差点の右折待ち車線で緊張しているらしい。今話しかけたらただじゃおかないわよ、というオーラが漂っている。
信号が青から黄色になるころになってやっと対向車がいなくなり、前方の車から右折が始まった。行け行け、前に続いてスイッと右折してしまえ! 助手席からそう念じたけれど、停止線ギリギリで赤に気づいた姉は、アクセルペダルから足を離してブレーキを踏んだ。そうして再び信号待ちになって三割り増しになった不機嫌を、姉は隠そうともしない。
「もう、どうして私が車を運転しなきゃいけないのよ。ケータがダメなら八木さんに頼めばよかったじゃない。二人とも運送会社で働いてるんだから、車くらいどうにでもなったんじゃないの?」
いや、運送会社に勤めてたって車が自由になるとは限らないでしょう……と思うけれど反論はしないでおく。確かに八木さんなら「なんとか」してしまいそうな気もするし。
「いい? 本当に今日だけだからね。二度と私に運転を期待しないでね」
「はいはい」
「まったく……あっちゃんも免許くらい取っておけばいいのに」
「はいはい」
あと3回は同じ事を言われるだろうな……。車は運転するもんじゃなくて、乗せてもらうもんだと思うけど。お姉ちゃんこそ、運転が嫌いなら免許なんか取らなければよかったんだ。
「だいたいね、タクシーじゃ恥ずかしいからとか、私の知った事じゃないんだからね」
「はいはい」
もうさ、既にこうして運転してくれちゃってるんだから、今更くどくど言わなくたっていいじゃん。本当に諦めが悪いっていうか、お姉ちゃんて根に持つタイプだよね。って言いたいけどぐっと我慢。姉はなにより、車を借りる為に実家に顔を出さなければならなかったことが腹立たしいのかもしれない。
「第一、ケータが前より広い部屋に引越したからって、ベェスケを連れて行くのはどうして?」
姉はちらっとバックミラーを見る。後部座席右側に、ベェスケは座っている。
違う違う、
「ベェスケじゃないよ、アンディだよ」
身長120センチのクマのぬいぐるみを19歳の誕生日にくれたのは、その頃つきあっていた米田康介くんだ。それで米田の「米」と康介の「介」で「ベェスケ」という名前を姉が勝手に付けたのだけれど、康介と別れてから改めて「アンディ」と名付けたんだから、アンディと呼んで欲しい。
「名前がなんだって、昔の彼氏にもらったクマであることには変りないでしょ」
「あのね、そのことはケータには内緒だからね!」
まぁ、お姉ちゃんはよけいな事言わないと思うんだけど。
子供っぽいと言われようと、私にとってアンディは大事な精神安定剤だ。19の頃からの5年間、両親が離婚するとかしないとかで揉めたり、姉がパパのコネで入った銀行を勝手に辞めちゃったり家を出たり、おばあちゃんがボケかけたり、家の中がごたごた落ち着かなくていらつくとき、誰より癒してくれた分身のようなアンディ。そのアンディをまず、ケータのところに住ませるのだ。それから私自身がこっそりといつの間にか、ケータのところに住み着いてやる計画。
関係の継続に必要なのは生活だよ、うん。
改めて前方の信号が青になり黄色になり、対向車が途切れて右折を果たした姉は、ちょっとほっとしたように見える。そんなに右折が怖かったのか。
「そうそう、新しいケータのアパートのそばにね、感じのいい美容室を見つけたんだよ」
話を変えたくて私は言った。
「そんなこと言って、すぐ美容師と喧嘩して行かなくなるくせに」
「それはね、今までの美容師がみんなヘタクソだったり、くだらない話題をふったりしたからだよ。でも今度は大丈夫。カットも上手だったし、なんかね、こんな人がお姉ちゃんだったら癒されるだろうなぁって感じの人なんだよ、塚原さんは」
「悪かったわね、癒しにならないお姉ちゃんで」
それは、どこか懐かしい、古い喫茶店のような外見の店だった。入り口の前には小さな階段があって、赤いペンキで塗られた手すりがかわいくて、よく手入れされた草花に覆われていて、頑丈そうなドアには控えめにステンドグラスがはめられていた。
単純に、中はどんなだろうという好奇心で近づいたらカラリとドアが開いて、ほわんと女の人が出て来て、ものすごく優しい目でまっすぐに私を見て「いらっしゃいませ」って会釈されて……
「それで、気づいたら鏡の前に座ってたとか?」
「そうそう。
私さ、お財布さえ持ってなかったことに途中で気づいたんだけど、後でいいですよって言うんだよね。その感じがすごくよかったっていうか、私、他人に信用されたのって久しぶりな気がしたんだ」
姉はあきれたっていう顔をしながらアクセルを踏んでいる。前方を見ていなきゃならないのは分かるけど、なんだかにくたらしくなる。冷淡なレーコさん。
「お姉ちゃんもさ、そろそろカットくらいした方がいいよ。ずっと伸ばしっぱなしでしょ。ちょっと見にはきれいだけど、こうやって日差しがあたってるの見ると切れ毛が目立つし、なんか貧乏くさ……」
「ねぇ、その人、ひとりでお店をやってるの?」
「え? ああ、ううん、母親のお店みたい。私が行ったときはそのおばさん、杖をついてて、立ち仕事は長くできないみたいで、もっぱら口を動かしてたけどね」
「ふーん……」
私は無性にその店の佇まいを姉に見せたくなってきた。
「もうちょっと走ったら、右の方にドラッグストアが見えてきて、ほら、あれ、あの先の信号を左に曲がって……」
本当はもう、ケータのアパートの前を通り過ぎていたけれど、姉に道が分からないのをいいことに、私は塚原美容室のある通りの方へと誘導していく。
「ここここ、ほら、さっき話した美容室。なんか、いい感じでしょ?」
いい感じでしょ? と自分で言いながら、あれ、そうでもないや、普通の美容室じゃんという気がしてくるのは、走る車の窓越しに見ているせいなんだろうか、空が曇っているせいかな。
歩行者用の信号が押されて赤になり、姉が車を止めたから、改めて私はアンディの頭の向こうに見える美容室を振り返った。ちょうど美容室の脇の道から何か白いものを抱いた若い男の人が出て来て、入り口前のステップに立ったところだった。
その人は、ほんの少し美容室のドアを開けて足の先で押さえて、手振りで中に何かを伝えている。そのグレーのセーターの肩先から、抱かれていた白いものがぬぬっと顔を出す。
あ、猫だ。抱いていたのは白い猫だったんだ。あれが塚原さんちのみいちゃん?
だとしたら、あの男の人が塚原さんの恋人なのかな。
塚原さんが聞き上手だから、私はケータの浮気を心配してることなんかつらつら話してしまって……そしたら塚原さん、「関係の継続に必要なのは生活かもしれない」って、小さな声で言ってたっけ。あの人がその相手かもしれない。
生活かぁー。愛だ恋だよりもやっぱり生活かぁー。
これはもう、一日も早くケータのところに転がり込んでやらなきゃなって思ったから、こうして大きな荷物から運び始めたんだけど……姉には話しても分かってもらえないと思う。姉は、生活でつながっているだけの夫婦を見てるのは嫌だとか言って、家を出ちゃった人だから。
だいたいお姉ちゃんは勝手なんだよね、自分だけさっさと家を出て行って、私にだけいい娘でいること押し付けてさ。
あれ? まだ赤信号? 長いね。
横を見ると、姉はサイドミラーの方を見たまま固まっていた。どうしたんだろ、後ろに幽霊でも見たのかな。
なにボォーっとしてるの? ほら、もう青になってるよ! って、笑おうと思ったけど、なんだかただならぬ気配。
これ以上姉の機嫌を悪くしてもいけないから、できるだけさりげなく、「お姉ちゃん、信号、青になってますよ」と私は言う。
信号が青から黄色になるころになってやっと対向車がいなくなり、前方の車から右折が始まった。行け行け、前に続いてスイッと右折してしまえ! 助手席からそう念じたけれど、停止線ギリギリで赤に気づいた姉は、アクセルペダルから足を離してブレーキを踏んだ。そうして再び信号待ちになって三割り増しになった不機嫌を、姉は隠そうともしない。
「もう、どうして私が車を運転しなきゃいけないのよ。ケータがダメなら八木さんに頼めばよかったじゃない。二人とも運送会社で働いてるんだから、車くらいどうにでもなったんじゃないの?」
いや、運送会社に勤めてたって車が自由になるとは限らないでしょう……と思うけれど反論はしないでおく。確かに八木さんなら「なんとか」してしまいそうな気もするし。
「いい? 本当に今日だけだからね。二度と私に運転を期待しないでね」
「はいはい」
「まったく……あっちゃんも免許くらい取っておけばいいのに」
「はいはい」
あと3回は同じ事を言われるだろうな……。車は運転するもんじゃなくて、乗せてもらうもんだと思うけど。お姉ちゃんこそ、運転が嫌いなら免許なんか取らなければよかったんだ。
「だいたいね、タクシーじゃ恥ずかしいからとか、私の知った事じゃないんだからね」
「はいはい」
もうさ、既にこうして運転してくれちゃってるんだから、今更くどくど言わなくたっていいじゃん。本当に諦めが悪いっていうか、お姉ちゃんて根に持つタイプだよね。って言いたいけどぐっと我慢。姉はなにより、車を借りる為に実家に顔を出さなければならなかったことが腹立たしいのかもしれない。
「第一、ケータが前より広い部屋に引越したからって、ベェスケを連れて行くのはどうして?」
姉はちらっとバックミラーを見る。後部座席右側に、ベェスケは座っている。
違う違う、
「ベェスケじゃないよ、アンディだよ」
身長120センチのクマのぬいぐるみを19歳の誕生日にくれたのは、その頃つきあっていた米田康介くんだ。それで米田の「米」と康介の「介」で「ベェスケ」という名前を姉が勝手に付けたのだけれど、康介と別れてから改めて「アンディ」と名付けたんだから、アンディと呼んで欲しい。
「名前がなんだって、昔の彼氏にもらったクマであることには変りないでしょ」
「あのね、そのことはケータには内緒だからね!」
まぁ、お姉ちゃんはよけいな事言わないと思うんだけど。
子供っぽいと言われようと、私にとってアンディは大事な精神安定剤だ。19の頃からの5年間、両親が離婚するとかしないとかで揉めたり、姉がパパのコネで入った銀行を勝手に辞めちゃったり家を出たり、おばあちゃんがボケかけたり、家の中がごたごた落ち着かなくていらつくとき、誰より癒してくれた分身のようなアンディ。そのアンディをまず、ケータのところに住ませるのだ。それから私自身がこっそりといつの間にか、ケータのところに住み着いてやる計画。
関係の継続に必要なのは生活だよ、うん。
改めて前方の信号が青になり黄色になり、対向車が途切れて右折を果たした姉は、ちょっとほっとしたように見える。そんなに右折が怖かったのか。
「そうそう、新しいケータのアパートのそばにね、感じのいい美容室を見つけたんだよ」
話を変えたくて私は言った。
「そんなこと言って、すぐ美容師と喧嘩して行かなくなるくせに」
「それはね、今までの美容師がみんなヘタクソだったり、くだらない話題をふったりしたからだよ。でも今度は大丈夫。カットも上手だったし、なんかね、こんな人がお姉ちゃんだったら癒されるだろうなぁって感じの人なんだよ、塚原さんは」
「悪かったわね、癒しにならないお姉ちゃんで」
それは、どこか懐かしい、古い喫茶店のような外見の店だった。入り口の前には小さな階段があって、赤いペンキで塗られた手すりがかわいくて、よく手入れされた草花に覆われていて、頑丈そうなドアには控えめにステンドグラスがはめられていた。
単純に、中はどんなだろうという好奇心で近づいたらカラリとドアが開いて、ほわんと女の人が出て来て、ものすごく優しい目でまっすぐに私を見て「いらっしゃいませ」って会釈されて……
「それで、気づいたら鏡の前に座ってたとか?」
「そうそう。
私さ、お財布さえ持ってなかったことに途中で気づいたんだけど、後でいいですよって言うんだよね。その感じがすごくよかったっていうか、私、他人に信用されたのって久しぶりな気がしたんだ」
姉はあきれたっていう顔をしながらアクセルを踏んでいる。前方を見ていなきゃならないのは分かるけど、なんだかにくたらしくなる。冷淡なレーコさん。
「お姉ちゃんもさ、そろそろカットくらいした方がいいよ。ずっと伸ばしっぱなしでしょ。ちょっと見にはきれいだけど、こうやって日差しがあたってるの見ると切れ毛が目立つし、なんか貧乏くさ……」
「ねぇ、その人、ひとりでお店をやってるの?」
「え? ああ、ううん、母親のお店みたい。私が行ったときはそのおばさん、杖をついてて、立ち仕事は長くできないみたいで、もっぱら口を動かしてたけどね」
「ふーん……」
私は無性にその店の佇まいを姉に見せたくなってきた。
「もうちょっと走ったら、右の方にドラッグストアが見えてきて、ほら、あれ、あの先の信号を左に曲がって……」
本当はもう、ケータのアパートの前を通り過ぎていたけれど、姉に道が分からないのをいいことに、私は塚原美容室のある通りの方へと誘導していく。
「ここここ、ほら、さっき話した美容室。なんか、いい感じでしょ?」
いい感じでしょ? と自分で言いながら、あれ、そうでもないや、普通の美容室じゃんという気がしてくるのは、走る車の窓越しに見ているせいなんだろうか、空が曇っているせいかな。
歩行者用の信号が押されて赤になり、姉が車を止めたから、改めて私はアンディの頭の向こうに見える美容室を振り返った。ちょうど美容室の脇の道から何か白いものを抱いた若い男の人が出て来て、入り口前のステップに立ったところだった。
その人は、ほんの少し美容室のドアを開けて足の先で押さえて、手振りで中に何かを伝えている。そのグレーのセーターの肩先から、抱かれていた白いものがぬぬっと顔を出す。
あ、猫だ。抱いていたのは白い猫だったんだ。あれが塚原さんちのみいちゃん?
だとしたら、あの男の人が塚原さんの恋人なのかな。
塚原さんが聞き上手だから、私はケータの浮気を心配してることなんかつらつら話してしまって……そしたら塚原さん、「関係の継続に必要なのは生活かもしれない」って、小さな声で言ってたっけ。あの人がその相手かもしれない。
生活かぁー。愛だ恋だよりもやっぱり生活かぁー。
これはもう、一日も早くケータのところに転がり込んでやらなきゃなって思ったから、こうして大きな荷物から運び始めたんだけど……姉には話しても分かってもらえないと思う。姉は、生活でつながっているだけの夫婦を見てるのは嫌だとか言って、家を出ちゃった人だから。
だいたいお姉ちゃんは勝手なんだよね、自分だけさっさと家を出て行って、私にだけいい娘でいること押し付けてさ。
あれ? まだ赤信号? 長いね。
横を見ると、姉はサイドミラーの方を見たまま固まっていた。どうしたんだろ、後ろに幽霊でも見たのかな。
なにボォーっとしてるの? ほら、もう青になってるよ! って、笑おうと思ったけど、なんだかただならぬ気配。
これ以上姉の機嫌を悪くしてもいけないから、できるだけさりげなく、「お姉ちゃん、信号、青になってますよ」と私は言う。
Copyright(c) sakurai All rights reserved.

